�@�@�@�@�킪���I�y���E�̐��ҁE�ɒ�F
�@�@���m�E�ɒ�z���Y�̗{�q���q�́A�F�Ƃ������B�F�́A����20�N�i1887�N�j�����Ő��܂ꂽ���A���e�𑁂��ɖS�����A�ӂ��]��̈ɒ�z���Y�̗{�q�Ƃ��Ĉ�����B���̕����h�E�������N���������Ƃ���ʊw���Ă����{����ꒆ�w�𒆑ނ��A�Z�̂�����Ɉڂ�Z�B
�@�c�����납�琼�m���y�ɐe���݁A����̊y���e�����Ȃ��A�p��ƃh�C�c��ɏG�łĂ��ăL���X�g���ւ̊S���瓯�u�А_�w�Z�܂Ői�B�������A�@���݂ē��u�Ђ𒆑ނ��㋞����B�����ĕ��e�Ƃ͈���Č|�p�̓���I�B
�@�@�͂��ߑn�����̐V���^���ɐg�𓊂������A�V���Ђ̎�ɂȂǂ��ւāA�A�����J�A��̕��x�ƁE���ؓ��q��Ɖ̕��������ݗ����ć��I�y�����������A���̍�ƁE�ƁE�剉�o�D�E���o�Ƌy�юx�z�l�Ƃ��Ĕ��ʘZ�]�̑劈��������B
|
|
�@�I�y�����Ԃ��ƁA���a�Q�N�ɋ߉q�G���E�x���h�O�ƃ��W�I�ʼň����������ȂǁA�킪���̃I�y���E�̐��҂������B�܂����a�T�N�ɓ��{�y�����������A�C�^���A�A��̃\�v���m�̎�E�։��q�q�ƃe�m�[���̎�E�����`�]���剉�����̕�����Łu�֕P�v���㉉����ȂǁA���y�E�����E���x�𑍍��I�ɃR���g���[���ł����l���́A�����l�������Ȃ������B����́A�t�����ɂ��������{�̊y���E�̑n�n�҂ł��茠�Ў҂ł��������B
|

�ɒ�@�F�i1887�|1937�j
|
|
�@�@�����r�Ȃ̈ɒ�@�Ő����y�����_
�@�@�F�́A�s�m�̑��q���������đ������ŎႢ�l�����̖ʓ|�����悩�����B���܂�l�t���������������ł͂Ȃ��������A����̉��y�E�����E���x�S�ʂɂ킽��y�����_�́A���҂̒ǐ��������Ȃ��Ƒn���_�ł������B
�@���y�͉��y�����ł͂Ȃ��B�������W���邵�A�_���X���W����B�_���X�ɂ��Ă��A�����I�\�����Ȃ��Ƒ���ɓ`���邱�Ƃ��ł��Ȃ��B�̂ɂ��Ă��_���X�I�ȃ��Y�������K�v���ƁA�g�ɒ�y���w�Z�h�̖����������҂����ɂ��̊֘A�����������ނ̂ł������B
�@�ɒ�F�̉Ƃ́A���X�Ɛ����������������r�̒[�A�������u�̏�ɂ������B���̓�瑩2���ځA�����r����������B
�@�����֑�c��L�̖ɏZ��ł����c����o�̓��Y�@���i�����j�Ƃ����l�Ԃ��A�d�ԂŒʂ��Ă��Ă͂����ŏ��������Ă����B�쎍�Ƃ��u�����Y�́A���y����S�ʂ��w�Ԃ��߂Ɉɒ�F�̂��Ƃœ����Ă����B���ł����}�l�[�W���[�A�ނ̐g�̉�肷�ׂĂ̂��Ƃ�萷�肷��̂��B���߂̓��Y���̖ڂɂ��Ȃ�ʎ҂́A�ɒ�F�̖剺���ɂ͂Ȃ�Ȃ������B
|
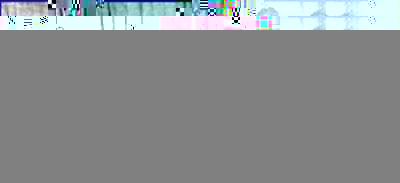
�u�J�������v�o���҂ƈɒ�F�i���[�j
|
|

�܂��e���r�̖�������A�m�g�j���W�I�̊Ŕԑg�u��\�̔��v�̃��M�����[�҂������쎌�ƁE���Y���@
|
|
|
�@�@���Ƀ_���X�̓V�ˏ��N�A�o��
�@�����u�`���[���X�g���v�Ƃ����_���X���A���{�ő嗬�s�A���̑��܂ŊJ�����قǂ������B���́u�`���[���X�g�����v�ő���15�̏��N���D���A�_���X�̓V�ˏ��N�Ƒ����ꂽ�B�����̒���O�Y�ł���B
�@�@����́A�㋞���Ń_���X�̉��`���ɂ߂����Ɛe�Z��ɐؖ]�����̂������B���܂��ܒ���̎o�́A�V���v��Ƃ������|�̌��c�iSKD�j�̉̏��̈ꓙ���t�ƌ𗬂��������B
�@�V��Ƃ����A���́A�u���ɓ��͗����ā@��ƂȂ邱��v�Ƃ������{�ŏ��̗��s�̂��̂����l�B�ޏ����ɒ�剺���ł��������Ƃ���A����͓��Y�@���ɔF�߂��A����ď㋞�A�����r�̈ɒ�@�̖�����������Ƃ��ł����̂ł���B
�@�@���E�k⩁E�`�]��A����߂�������
�@����O�Y�����債�����a5�N�A���łɐΈ䔙�͓��債�Ă��āA�����o���G�ЂƋɐ�����ƌ��S���Ă����B�ɒ낪���V�A�̃��[�V�[���Љ�Ĕ��͏C�s�̗��ցB
�@�x�������������y�w�Z���o�đ吳3�N�ɂ킪���ŏ��̌����y�c�ł��铌���t�B���n�[���j�[��g�D�����R�c�k⩂��A�悭�ɒ�@�ɗ���������B���ƍk⩂͖���19�N���܂�̓����N�A�ɒ���1�ΔN��ł��������A�k⩂Ƃ͓��{�y������������ăI�y���^�������������Ԃł���B
�@���������ЂƉ��Ⴂ�����`�]�́A���[�V�[�̌��c�̌����������Ċ����A���������I�y�����肵�Ĉɒ�̂��ƂŐI�y���Ƀf�r���[�B�����̓C�^���A���w�Ŕ����@�͏K�����Ă������A�I�y�����ǂ̂悤�ɍ\�����邩���w�Ԃ��߂ɖ剺���ƂȂ��Ă����B
�@��������x�����債���̂��A�M�����B�̂��ނ́A���_���_���X�̔��˒n�h�C�c�ɗ��w�A�A����͓n�Ă��ăJ���t�H���j�A��w�̃_���X���_�����ɁB
|
�@�ݕ��D45���Ԃ̗��Ńj���[���[�N��
�@����O�Y�����l�`�����p�o�i�i�̗Ⓚ�D�ɏ���ĒP�g45���Ԃ̑D���ɔ������̂́A�c����Q�N�𒆑ނ������a�T�N�̎��B
�@1000�~�����100�̉Ƃ����������ゾ�B�u���A��邩�킩��Ȃ��B������̂����1000�~��������v�Ɨ��w���e��e�ʂɃZ�r��B
�@�}���n�b�^���ɒ�����A�ɒ�̕��ʒ��Ԃł���_���X���G���̕ҏW���̂��ƃw�^�N�V�[�ŁB����̏Љ�ŃW���[�E�}�`�\���Ƃ����~���[�W�J���̐U�t�t���t�Ƌ����ƂƂȂ����B
�@���ꂩ��͖��m�Ƃ̑����A�������Ƃ���B�e����̃X�^�b�t�����_�����킵�ăe�[�}�̌����A�~���[�W�J����̂̐���ߒ��A�|�p�]���_�ȂǁA���{�Ƃ͓V�ƒn�قǂ̍����������B�Ȃ��ł��V���[�}���́A�݂�Ȃ��爤����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B����ɂ͂ǂ�����ׂ����A�Ƃ�����O�S���w���_���X�Z�@�����M�S�ɕ�������ꂽ�B�j���[���[�N�s����w�ւ��̕���1�N�Ԓʊw�����̂��B
�@����Ɍ��킹��ƁA���ꂪ�����p��g�ɕt���邤���ō��ł���ϖ𗧂��Ă���Ƃ����B
�@���ł�72�ƂȂ�������́A�����Ȑt����A�M�d�ȊC�O�̌��̋@���^���ł��ꂽ���t�E�ɒ�F���݂̍肵���̎p���]�����痣��Ȃ��B
|

���a�W�N�A�j���[���[�N�E�u���[�h�E�F�C�̌���ŃV���t�H�j�b�N�E�^�b�v������������O�Y
|
|
|
�@�@�@�@�����l���ݗ��������{���̎�������
�@����O�Y�́A�ɒ�F���ÂсA�����r�ɋ߂��剪�R�w����ɉ���������Ă邱�Ƃ����S�����B���a26�N�̂��Ƃ��B
�@�܂��S�l�̒��Ԃɑ��k����B�쌀���Ƃ܂ŌĂꂽ�G�m�P�����ƁA�|�{����B����������r�̓�A��J�ɏZ��ł����B�G�m�P���ƕ��ъ쌀�E�̑�X�^�[�A���b�p���ƌÐ�Δg�B������܂��A�r�̓���̒[�A�����̏Z�l�B
�@�̗w�ȁw�N���̋���z�킴��x���q�b�g�������������������X�������ɋ߂��c�����z�B�w�錜�̌a�x�w�W�����̃}���S����x�ňꐢ���r�����n���C���܂�̉̎�E�D�c���F�B�݂Ȋ��Ŏ^�����A���N�l�ƂȂ����B
�@���ꖼ�́u�剪�R�R�[�p�v�ƌ��܂�B�o���҂̒��Ԃ́A���̂�炶���͂��ĒT���Ă��W�܂�Ȃ����l�C�X�^�[5�l�B�ϋq�̍s��͉��X�Ƒ����A�剪�R�w�O����ЂƉw��̉���w������܂ő������ւ̗�B
�@�����27�N���s�[�N�A30�N��̃e���r���y�ɂ�A���s�͏��X�ɉ��ɁB�ǂ��ł���������悤�Ƀ��b�p�̎��A�G�m�P���̉E����ؒf�Ƃ����s�K���d�Ȃ�A����46�N�����̉͏������B
|
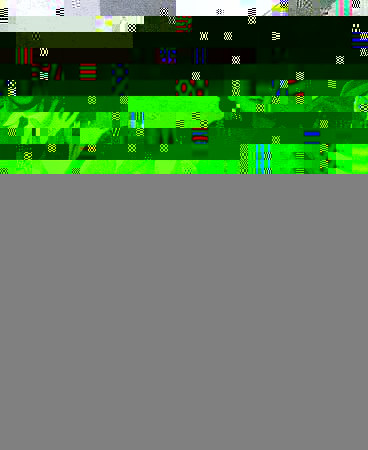
���a25�N�A�����Œ���O�Y�����}���V���[
|
|
|
�@�@�@�@�����r���ӂɌQ�����鉹�y��
�@���@��l�����������Ƃ����`���̂�������r�B�L����30���������[�g���A�Ɉ͂܂ꂽ�r�̋߂��ɋ߉q�G��������m�g�j�����y�c�̗��K�ꂪ���������Ƃ��瑽���̉��y�Ƃ����͂ɋ����\���Ă����B
�@�@���D�E�k�����q�̕��E�k�����M�A�����O�q�̕��E������ԁA���{�����y�c�������ݗ�������q�̋߉q�G���ƎR�c�k⩁B
�@���͉̗w�E�̑�䏊�E�W�J�̂�q�A��ȉƂ̕����Lj�ƒ������́A�W���Y�̎�E�����͂݁A���y�]�_�ƁE����v���A�������m���E�̃h���E����O�Y���B
�@�吳�E���a�����A�r�̂قƂ�̈ɒ�@�̋��Ԃɂ͘A�鉹�y�≉���A�_���X�k�`�ɂӂ���y���E�̎Ⴋ���q�������Q�����Ă����B
�@���̒r�Ȃɂ́A�����̔����Ђ炢�����C�M���A���O���̒r�̕���������Ȃ������A��̉��Ŗ����Ă���B�킪���{�̉��y�E�����E�m���̖閾�����A�����r�Ȃ���n�܂낤�Ƃ��鎞��ł������B
|
|