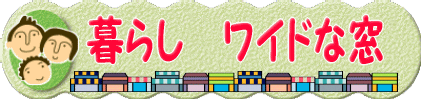 |
| �@�ҏW�x���F�������G�@/�@���S�F�z�����q |
| �ҏW�F��c�����@�@�@�m�n.271�@2014.10.05�@�@�f�ځ@ |
|
�@�@�@�@�@�@�@�@���摜�̓N���b�N���g�債�Ă������������B
|
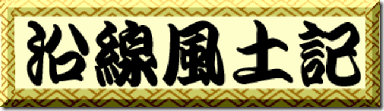 |
  |
�@�ʐ쑺�̗V�s
�@�@�@�@���E�L�c�����j�i���y�j�ƁE���c�J�擙�X���j
|
|
|
|
|
�@�@�����Z���Q���̃R�~���j�e�B�[���w�Ƃ��悱�����x�B�D�]�A�ڂ́g�����Łh
�@�@�@�f�ڋL���F���a63�N�Q��15�����s�{���m��.41�@�����u�Ёi����j�v
�@�@�@ |
|
|
�@�j���̖�̗V�яꂾ�����V�s�́A���ē����E���E���l�̂��������ɑ��݂��Ă������Ƃ͎����ł��B
�@�@���������̎��Ԃɂ��ẮA���y�̗��j�𐔐�y�[�W�ɂ킽���ďڍׂɎ�肠�����ǂ̎s�����j��ǂ�ł݂Ă��A�w�ǐG��Ă��܂���B����͂Ȃ����\�\�B
�@�V���Ƃ����e�[�}�������w�Z�̎Љ�ȋ��ނƂ��Ă͔�I�ōD�܂����Ȃ��Ƃ������R����^�u�[������Ă��邩��ł��B
�@�@������A�{���̊�c�ҏW���́u�L�����̂ɂ̓t�^�ł͂Ȃ��A���R���鎖���͂ǂ�Ȃ��Ƃł������j���B�����𒉎��ɋL���A�㐢�Ɏc�����I�v�Ƃ��������M�O�̎�����ŁA���̌��t�ɓ������ꎄ�͔ؗE���ӂ���ăy��������܂����B
�@�]�ˎ���ɂ͗��l�����̇����̂͂������Ƃ��ē��C���\�O���̂��ׂĂ̏h�ɗV���������t���Ђ����Ő������Ă��܂����B
�@�ʐ쑺�̔_�Ƃ̎Ⴂ�O����������z���Đ��h�̊s�֍s�����A���邢�͕i���a�J�̐��s��̋A�蓹�A�i��̗V������a�J������̍r�؎R��ƒn�i���a�J��~�R���j�ŗV��������Ă���̂��V�т̃R�[�X�������̂ł��B
�@
�@���ꂪ��������ɓ���ƁA�����߂��̏ꏊ�Ň��s�V�i����킠���j�ч����ł���悤�ɂȂ�܂����B���̋ʐ쑺�ɂ����K�͂Ȋs������l�����������n�߂��̂ł��B
|
�@�@�@������1���̑�{�O
�@�ʐ쑺�̗V����1���ƂȂ������̓X�́A����20�N��ɓ��X�͕s�����̑�ڂ̓����Ɍ������n���i���傤����j�ȂQ�K���ĂŁA�^���V���̍L�����ɂ܂œo�ꂵ���قǂ��̖��͍����L���X�ł����B
�@��ڂɒʂ���Βi�͖���22�N�v�H�ł����A����ȑO���J�i�Ђ�ǂ�j�z���̂悤�ȊR���Ԃ��ʼnH���R�̍r�C���҂���������Ƃ��Ă������ł����B�����A�����̍��i1804�`1829�j�͓��X�̖͂��ƁE�ˈ�c�d���q��𒆐S�Ƃ���H���u���g�D����A�ʐ쑺�S��̂ق����݂̑�c��L�̖A�����A�Α��i���ڍ���̈ꕔ�j�Ɏ���L�͈͂ȉH���u�����̌��R���ڂōr�s��ς�ł����̂ł��B
�@��{�O�̌o�c�҂͋ʐ쑺���̋��q�E�ؑ��ċg�ł����B�Βi�v�H��́A�O�ɒʂ��V��Y�i�䂤��낤�j�͂Ђ������炸�A�����͖k�扤�q�≡�l�s��������܂ŏ�A�q�������V����10�]���ɋy�ԂقǁB���̔ɐ��Ԃ�͍����Ȃ��ØV�̌�葐�ƂȂ��Ă��܂��B
�@�{���A�_���ȑ�ڂɗV���Ƃ����g�ݍ��킹�́A�ϗ��I�ɋ�����Ȃ��Ƃ���B�������k�J�̓y�n���L�҂����̓����{�c��c���E�L�c����ł�������A���҂̖����̂قǂ͓ǎҏ����̗e�Ղɑz���ł���Ƃ���ł���܂��傤�B
�@ |
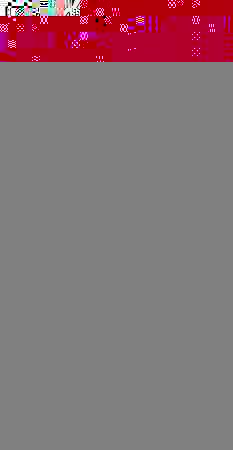
�ʐ쑺�̗V�s
�}�b�v�F�Ζ�p�v |
|
|
|
�@�@�@�@�����l�v�Ƀ��e��������
�@�@����30�N��̌㔼�A���̓X�͓��X�͕s������̒���������A���݂̖L�c�Y�w�l�Ȃ̐^���ɂ���܂����B�ʐ쑺���h�c��4�����X�͂̏����i��������j�ł������L�c�����Y��2�K����10�]���̊s�����āA���a���N�܂őS�����ւ��Ă����̂ł��B
�@���q�̎���́A������̍����̌@�ɏ]������l�����ł����B�����_�Ƃ̐l���������N������ň�Ă�������ԂɎR�قǂ̏o�ׂ����Ă�10�~�̎���1������ɂ���̂͗e�ՂłȂ������̂ł����A�����@��l���̓����Ƃ��ĂQ�A�R�~���҂��҂͒������Ȃ������Ƃ�������ł��B
�@���w�Z��w�N�̍��̎��́A���̑V�����悭�L�����Ă��܂��B���C���A�S�{�E�A��ؗނ̂ق��A�C���V�����������炢�̂��̂ł����B���ꂪ���������ۂ聍�����̉Ƃ֗V�тɂ䂭�ƁA�����E�ؓ��̂ق��Ɏ��E�r�[���тї����Ă���ł͂���܂��B
�@�s���̔_���̔߂��݂��q���S�ɂ��悭�킩�������L�ł��B
�@�@�_�Ƃ̒U�ߏO����A�A���݂̂�
�@�ʐ쏬�w�Z����𓌂Ɍ������ē��X�͂ɍs���ד�������܂��B���̒ʊw�H�̔�������ɑ吳10�N�̍��A�����݂̂⇁�Ƃ����s���ł��܂����B
�@�X�̃I�[�i�[�́A�Ȃ�ƍ��̐��ł͍l�����Ȃ��n���������̌o�c�A�ʐ쑺����̗����ł���������č�Ƃ����l�ł����B�����Ђ傤����҂̂�������ŁA�b�̒��ɕK�����[���A�������镗���l�B�w�Z�̋߂��ɂ��������߂ɍ����@��A�n���̂悤�ȍr����̋q�͋H�ŁA�_�Ƃ̒U�ߏO����A�������悤�ł��B
�@�@�������_�ƁA����
�@�ߔN�A���X�͂Ƃ����n������w�L���ɂ����Ă���{�݂̈�Ƀ��u�z�e����a������܂��B���̂�����͐̂��炻�̂悤�Ȓn�����������̂����m��܂���B
�@�吳���㒆���A�Â�����̔_�Ƃő����h��̈�l�ł������F�c�약�ܘY�́A�������_�Ƃ����̂܂܉������č����Ƃ����V�����J�Ƃ����̂ł��B�ꏊ�͌���ŗV������a�����瓌�֖�60���[�g���̒n�B�������牜�ɖʂ��Ă������߂ɖڍ��≜��̋q�����������Ɠ`�����Ă��܂��B�s�̎�A���ܘY�͋��̉Ύ�����֎��]�Ԃő��s���A�g���b�N�ɂ͂˂��ď}�E���Ă��܂��܂����B
�@�@�����M���i�����傤�j�ɋP���l�̓X�A��؉�
�@���݂̖ڍ��ʂ�ɖʂ����X�[�p�[�I�ɍ�����O�Ƀo�X�⇀���X�͎����ځ�������A����ɂ��̎�O�O���H�ɋ��Ƃ̈�A��؉Ƃ�����܂��B
�@�@���Ƃ̑c�E��ؕċg�͓��I����ŋ����M�͂��������܂������A�吳�S�A�T�N���A�V���́u��؉��v��n�Ƃ����̂ł��B���̂����A�_�ƂƐA�ؐE�����Ƃ���Ƃ��������҂ł����B
�@�@�����̍��R�Ɠ����p�@�@�߂��̗V�s
�@���щw�ɂقNj߂������ܒ��ڂ̑�n�ŋ��n���A���R�Ƃ������̈��ɓ����̊s������܂����B���̂��Ƃ�70�Έȏ�̘V�l�Ȃ�悭�L�����Ă���܂��B
�@�Ȃ��܂��A���݂̗p��ڂƂȂ��Ă���������w�Z�̋߂��ɑ�Q�����E����A����Ƃōi��Y�ƂȂ��������p�@�̎��@���������̂ł��B�������A���̋߂��ɂ��u�V�s�v�Ƃ������̊ŔX�Əo���Ă����_���}�������������̂ł��B
�@�@���тɂ���щ�
�@���ł͍����Z��n�̒��Ƃ����C���[�W����������蒅�������тɂ��A���́g��щ��h�Ƃ����W�O�����a�����܂ň��̏�ɂ��������Ƃ͎j���ł��B
�@�@�@�O�ƒn�A��ƒn�A��ƒn
�@������V�s�X�ɇ��O�ƒn���Ƃ����܂����A�O�ƒn�Ƃ͌|�W���A�ҍ������A����������Ȃ�O�Ƒg�����g�D����Ă���n��̂��ƁB�|�W���Ƒҍ������͕��I��A�w�苖���O�ł͉c�Ƃ��F�߂�ꂸ�A�܂����̋��ł͌|�W�̕����A�Z�|�̌𗬂̂��߂Ɏ����̊��B�◿�����܂߂ĎO�ƒn���`�����Ă����̂ł��B�����Ď�Ɍ|�W�����������������Ă���n�������ƒn���ƌĂт܂��B
�@������l���͋g���ʂ��̏M�h����ԊX�ւƔ��W����������Ƃ����O�ƒn�ł����B������̉~�R���͖��炩�ɓ�ƒn�ł���A��q�ʐ�ԊX���r�����Ĉꕔ�͎O�ƒn�ƂȂ�ꕔ�͓�ƒn�ɂƂ������j���������X�ł����B
�@�ҍ������Ƃ����̂́A���܂萈�łȂ��A�����Z�b�N�X�݂̂����҂��ď��V�ш�ɂ���������ƒn���@�ł��B
�@�ʐ쑺�̌l�o�c�̊s�͂��ׂđҍ��݂̂̈�ƒn�ł����B��������̋ʐ쑺�́A�i��x�@���Ǔ��̍x�O�ɂ���u����i���݁j�̂��ڂ��ڂ��v�������Ċs�̉c�Ƃ����₷������ł������̂ł��傤�B
|

�C���X�g�}�b�v�E�G�F��p�v�i���Z�g�j
|
|
|
|
|
 |
�u�Ƃ��悱�����v�s�n�o�ɖ߂� |
 |
���y�[�W�� |
 |
�u�ڎ��v�ɖ߂� |
|
|
|
|