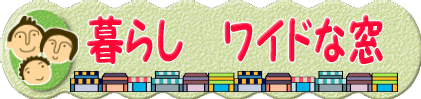 |
| �@�ҏW�x���F�������G�@/�@���S�F�z�����q |
|
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�ҏW�F��c�����@�@�@�@�@�m�n.269�@2014.10.04�@�@�f�ځ@�@�@�@
|
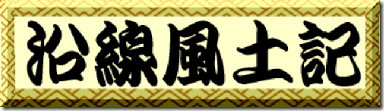 |
 |
�@������̓n��
�@�@�@�@���E�L�c�����j�i���y�j�ƁE���c�J�擙�X���j
|
|
|
|
|
�@�@�����Z���Q���̃R�~���j�e�B�[���w�Ƃ��悱�����x�B�D�]�A�ڂ́g�����Łh
�@�@�@�f�ڋL���F���a62�N�V��20�����s�{���m��.39�@�����u���i�ނ����j�v
�@�@�@ |
|
|
|
|