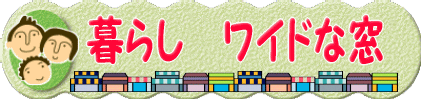 |
| 編集支援:阿部匡宏 / ロゴ:配野美矢子 |
| 編集:岩田忠利 NO.263 2014.10.02 掲載 |
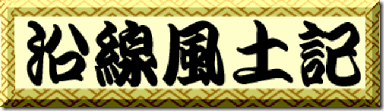 |
 |
奥沢・開発の歴史
文・西野裕久(会社員・世田谷区奥沢)
|
|
|
|
|
沿線住民参加のコミュニティー誌『とうよこ沿線』。好評連載の“復刻版”
掲載記事:昭和61年7月10日発行本誌No.34 号名「樺」
|
|
|
天野家の埋蔵金
郷土史研究家・鈴木宗さんの「奥沢史年表」によれば、鎌倉時代の文治5年(1189年)、源頼朝の家臣の天野茂右衛門が奥州に下ろうとした際、持病に苦しみ、奥沢の地に留まったというのが奥沢に在住した最初のようである。
この天野氏にかかわることでおもしろい話がある。
「郷土史おくさわ」(奥沢神社発行)に「天野家は初代の遺書により軍資金を鎌倉よりこの地に埋めたと伝える」とある。
明治の中頃、当時目黒にいた天野家の末裔がこの埋蔵金を探したが見つけることができなかった。ところが、それではあきらめられなかったのだろう。関東大震災の後、地盤が変動して見つかると思ったのか、再度人夫数十人を連れて一丈あたりの棒で掘ったというが結局見つからなかった。
昔の奥沢村は・・・
今でも商店街名に残る〝諏訪山〃の名は、昔あった諏訪神社の名からとられたものであろう。
現在神杜はなくなってしまっているが、今でもその御神体を和田泰治家で祀っている。この和田家の先祖、すなわち鎌倉時代の武将和田義盛の後裔が元亀年間(1570年代)に奥沢を開いたと言われている。
しかし、奥沢にはもう一つ村があった。それが「奥沢新田村」で、「奥沢本村」の閑地を万治元年(1658年)開いたところが、現在の奥沢4~8丁目にあたる。
さて当時の奥沢はというと、決して楽な生活をしていたのではなかったらしい。当時の様子を伝える文書によれば、田が少ないうえ、地味も悪く、ときには食糧不足のため奉公に出なければならなかったところだという。それでいて主要道からもはずれていたからか、商売にも不向きであった。このためか明治期まで人口もほぼ横ばいを続けていた。
|
目蒲線の開通
奥沢がようやく脚光を浴びたのは、両隣りの調布村、洗足村が、田園都市株式会社(現在の東急)の渋沢栄一が唱えた「田園都市構想」によって開発が計画されて以来である。
田園調布、洗足への交通の便として計画された鉄道の開通(大正12年、現在の目蒲線)は、いやが応にも奥沢に画期的な変化をもたらしたのである。
本誌イラストマップにも載っているが、現在の奥沢二丁目に、いまでも「海軍村」と呼ばれる一角がある。大正の未頃、当時の若手将校たちがまだ金力に余裕のない時代、借地をもって家を建てたものである。都心の海軍省にも横須賀にも両方出られる位置にあったことなどがこれほどまでに将校連が集中した理由であろう。
また同じように「ドイツ村」というのもあった。トイツ帰りの人々が住んでいた一角で洋風の建物が何軒か建ち並んでいたらしい。
この「海軍村」と「ドイツ村」の子弟たちが〝陸上競技大会〟で互いに競い、また親睦を深めたという話も聞く。当時の奥沢新住民ののどかな時代の一コマである。
|

イラスト:石野英夫(元住吉)
|
|
|
先見の明――耕地整理
人口の伸び具合いをみると、グラフのとおり大正から昭和にかけての伸びは大変に大きい。
しかし、奥沢の開発史の中で現在を形づくった最大のものといえば、まさに「玉川全円耕地整理事業」に他ならない。
「耕地整理」とは聞き慣れない言葉であるが、要は土地を耕作しやすいように土地を整形化したり、水路や道路をつけたりして農業の振興をはかるものである。しかし、玉川地区での耕地整理は、決して農業振興を最終目的とするものではなかった。この計画を遂行した豊田正治氏(当時玉川村長)は、隣接の調布、洗足が東急によって開発されたのを見聞きして、農民自らの手で開発を行ない、将来やって来るであろう宅地化の波に対処しなければならないと考えたのである。
さて、実際事業を進めるにあたっては、当然のことながら、玉川各地区で猛烈な反対があった。ある地区では賛成・反対の両派が部落寄り合いの時に激論の末、つかみ合いになり警察沙汰になったり、反対派が自分の子どもたちに同盟休校させたりといった具合で、なかなか困難を極めたらしい。
ところが玉川地区にあって奥沢はスムーズに事業が展開されたのである。それは、すでに周囲が開発され必要性が高かったからであろう。諏訪分(現在の東玉川)、尾山につづいて昭和15年に全て完了した。
耕地整理組合の2代目理事長で九品仏在住の故毛利博一氏は、
「最初は整理実施により農業は亡びてしまうと危倶した人たちも、住宅向けの土地は住宅地として賃貸し、半ば不毛に近かった湿田埋立地を最高度に耕すようになり、農業を続けようとする者には少しの不便も与えなかった。農家の子弟は土地の開け行くにつれて勉強もして、自然に世の中の進運によって職業も変わってきた。(中略)このように社会状勢の推移に順応することが出来て、ここに全く共同開発による福祉増進の実が結ばれたものといえよう」
と述べている。
現在の碁盤の目状に発達した奥沢の地図を見るにつけ、先人たちの苦労と先見の明を偲ぶ思いである。
|
|
 |
「とうよこ沿線」TOPに戻る |
 |
次ページへ |
 |
「目次」に戻る |
 |
沿線風土記-7へ |
|
|