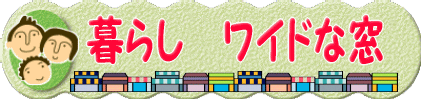 |
| �@�ҏW�x���F�������G�@/�@���S�F�z�����q |
| �ҏW�F��c�����@�@�@�@�@�@�@�@�@�m�n.262�@2014.10.02�@�@�f�ځ@ |
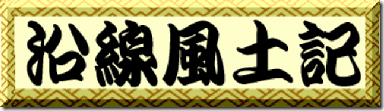 |
 |
�@�@�ӂ邳�Ɓ@�_�ސ�h
�@�@�@�@�@�@���E�@�Ɩ{�@���i���_�ސ�F��_�Ћ{�i�j
|
|
|
|
|
�@�@�����Z���Q���̃R�~���j�e�B�[���w�Ƃ��悱�����x�B�D�]�A�ڂ́g�����Łh
�@�@�@�f�ڋL���F���a61�N�T��1�����s�{���m��.33�@�����u���v
�@�@�@ |
|
|
�@
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�_�ސ�h�̎v���o
�@�_�ސ�ɐ��܂����āA�͂�60�N�B��O�E���̖ڂ܂��邵���ϑJ�\�\��ЁA�����R�ڎ��A��搮���A�����ύX�A�������H�ƃr�����݂Ȃǁ\�\�B�������A���Ă̐_�ސ�h�ł������Ƃ͑z�����y�ʕς��l�ł���B
�@��O�ɋ���ꂽ�l���v���Ԃ�ɖK�˂Ă��āu���̋������͂ǂ̂�����ł����v�ƕ�����邪�A���܂�̕ς��l�ɋ����Ȃ���A���Ă̘̐b�ɉԂ��炫�A���̌o�̂�Y��Ă��܂��������̍��ł���B
�@�����Ō����u�_�ސ�v�Ƃ́A�_�ސ�h�̂��ƁB��̐�����ɓ����_�ސ쒬�A�����ؒ��ł���A���ꂼ��ɖ{�w������A�Έ�ƁA��؉Ƃ����߂Ă����B
�@���̎q���̍��͖����h��̖ʉe���c���Ă����B�Ɛl��e�ʂ̘b��̒��ɁA���Ƃ̖����o�Ă���@�\�\�@�������A�O�͉��A�V�H���A�������A�≮��̏�������A�����̖����A�����̎O������A�K������c�c�B
�@�_�ސ쒬���]�ˎ��ォ�炢���ɓ��킢�A�����̏��Ƃ��e�n���W�܂��ė��Ă��������z���ł���B�����Q�N�i1855�N�j�̐_�ސ�h�ƕ��}�ɂ��ƉƐ�1477���A���Ăƒ�����96���Ƃ���B�i�V�������Ő����܂Łj
�@���Ƃ̔Ԓn�����x���ς�����\�\�������k���S�_�ސ쒬�A��a���A���_�ސ�꒚�ڂƁc�B
�@���a�Q�N�ɋ搧��������A�_�ސ��ƂȂ�B�����̐_�ސ��͌��݂��L���A���̍`�k��j������g�A�������ʂ��̕����A���쒬�A��Ԓ��Ȃǂ��܂܂�Ă����B
�@���a�U�N�ɂ͒��E��������������A�V�����ɂȂ��Ă��A�܂��܂��̖̂������p����Ă����\�\�@���̒��A���̒��A��Ԓ��A�\�Ԓ��A�t���A���`�n���A�r�h�A�V�h�Ȃǁ\�\�Ȃ��������ł���B
|
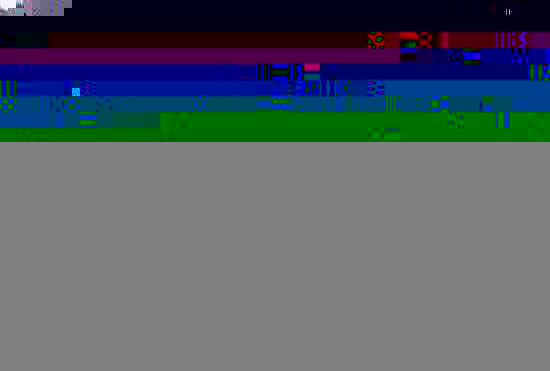
�]�˖����A���C���E�_�ސ�h�̓����ɂ��肻�̐����̐_�ސ��֖��@�@�@�F�����䗅�_�Ёi�_�ސ��䒬�j
|
|
|
|
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���D���i�������j�̕���
�@���N�ɂȂ��Ă���̘b����E���Ă݂�ƁA�v���Ԃ�̐�ł������Q���W���A�_�ސ�n��Z���^�[���J�݂ƂȂ�A���̖T�ɗ��h�ȍ��D�ꂪ�������ꂽ�B�{�w�E�Έ�Ƃ̎����Ɋ�Â��_�ސ��w�u���E���������Ɉ˗����A�����T.�V�b�A�����R.�T�b�Ƃ܂��Ƃɑ傫�Ȃ��̂��B
�@����Ɍ��≮��̏����Ƃ̂��D�ӂɂ��A�c���S�N(�������N�@1868�N)�̐��D�Q����q���A�W���������Ƃł���B�ܘ_�A���D�͐_�ސ����ɂ��������c���Ă��邪�A����͎��ۂɑ�̋��ۂɊ|����ꂽ�����ł���A�������N�̐_�ސ��A�֓���k�ЁA���l��P�̂R�x�̍ЊQ�ɂ��߂��������������̂ł���B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�w�_�ސ�w���}�G�x�Ɓw���썻�q�x
�@������̘b��́A�]�˖����̕����N�ԁi1818�`1829�N�j�ɏ����ꂽ�w���썻�q�i���Ȃ��킷�Ȃ��j�x�Ɓw�_�ސ�w���}�G�x���_�ސ�n��Z���^�[�ɓW�����ꂽ���Ƃł���B
�@�w���썻�q�x�́A�������y�j�����ɂ͋M�d�Ȏ����ł��邪�A160�N�O�̕����U�N�i1823�N�j����W�N�ɂ����āA���̒��ɏZ��ł������Ǒ��쑑�i������₫���傤�j�ƌ����A�ʖ����u�����܂��͏����Y�v�ƌĂB�_�ސ�h�i������������ۓy���J�����Ǖ��܂Łj�̎Ў��A���ցA�������G�ƕ��ł���킵�A�ڂ����h�����Ƃ炦�Ă���G�}�ł���B
�@�����w���썻�q�x�Ƃ��������͂��߂��̂́A50�N�قǑO�Ŗ������w���̍��������B�����A�������݂ŐΖ�l�搶�i�������E�������Z�n���ҁA���y�j�Ɓj���A�����Η��Ƃ���e�����������悤�ł���B
�@���傤�njF��_�Ёi�����l�j�̌����850�N�Ղ̑O�N�̍��������B���ƂŎ��q����ł�������`�O�Y���i�����j�̓y���̒�����A�����T�N�i1793�N�j�́u�F��O�Б匠���v�̃{���{���̛�o�Ă����B���̎��Ɂw�_�ސ�w���}�G�x�����߂Đ��ɏo���̂��Ǝv���B���͑�ςȊ�т悤�ŁA�����A���{����点���B�G�͎Q���̑��ɂ������̎R���쑾�Y����ɁA�����͎��̕ꂪ���������Ƃ��o���Ă���B�����c�O�Ȃ���A���̎ʖ{�͋�P�ŏĎ����Ă��܂����B�K���A��Ƃ̌��{�͏�����A����A�W�����邱�Ƃ��ł�������ł���B
�@���Ǒ��쑑�͒��̒��ɏZ�݁A���ǂ������Ƃ��Ă��������l�ł������炵���B
�@�u�_�ސ�w���}�G�v�͕����U�N�Ɋ쑑���ŏ��ɋL�������̂ŁA�ʐF���قǂ�����Ă���B���N�Ɂw���썻�q�x�O���{�i�ѓc���O���Ƒ��j���ł��A�Ō�ɕ��c�{�i�K�����c�Ƒ��j�����������悤�ł���B�Ζ�搶�̐_�ސ�j�v�w���썻�q�x�ɏ��ڂ̂��̂́A���̕��c�{�ł���A�O���{�͖��R�O���ƂɌ��L����āA��������M�d�ȋ��y�����ł���B
�@160�N��̍����A���珑�����}�G���A���̂悤�ɒ��d����Ă���Ƃ́A����≌�ǒ�������v�������Ȃ��������Ƃ��낤�B
�@�@���̎R�̂Ȃ��Ȃ閘�́@�͂Ȃ���@�i���Ǒ��쑑�j
�@�@�ѓc���@�Ɋy���̈�̏h�@�肤�@�l�͎��܂Łi���Ǒ��쑑�j
|
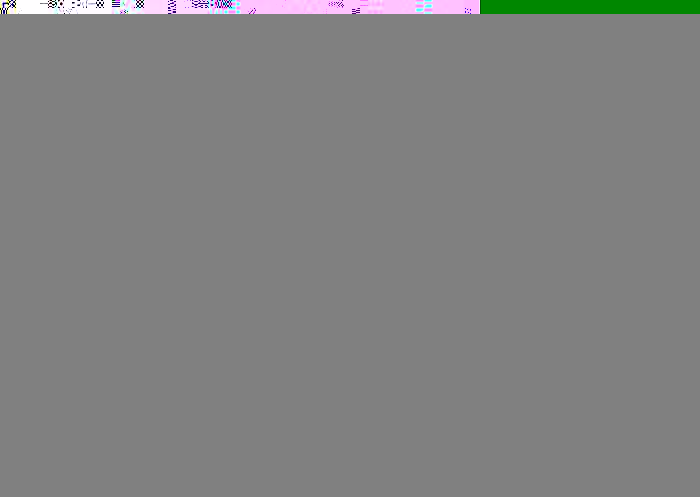
�@�@�w���썻�q�x�́u�c���V���v�E�E�E���Ǒ��쑑�̊G�Ɍ���̘H���E�����E�������L��
�@����́A������160�N�O�̓����y���ʂ̐}�B�E�������肪�����y�w�B�������c�ɏ㖃�����H������B�G������킩��悤�ɁA�����͍��̕��쒬�ʂ肪���C���̒ʂ�ł������炵���B
�@�܂�����́u��{���v�́u�������V�����̏��v�Ə̂���A�吳�N�Ԃ܂ł��̎p�����邱�Ƃ��ł��������ł���B�Ȃ��A�u��{���v�̂Ƃ���͒˂ɂȂĂ��āA�Q�A�R�N�O�܂Ŏc���Ă������A���݂ł͏Z��ɂȂ��Ă��܂����B
�@�}���̂悤�ɂ܂��ɓc�┨����ŁA���݂̓��킢�Ƃ͑�ςȕς��悤�ł���B
|
|
|
|
|
 |
�u�Ƃ��悱�����v�s�n�o�ɖ߂� |
 |
���y�[�W�� |
 |
�u�ڎ��v�ɖ߂� |
|
|
|
|