25年間に日吉内を2度引っ越し
日吉に住むようになってから、そろそろ25年になる。そして東横線にはもっと古くから乗っている。
昭和26年、上京した私は、岡山の高校時代の友人の家が自由が丘にあったので、そこを訪ねる時、はじめて東横線に乗った。それまではほとんど山手線や中央線など国電しか利用したことがなかったので、東横線は明るくスマートで、乗り心地がよく、私はすっかり気に入ってしまった。それに「自由が丘」という名称は、えらく魅力的だった。
まだ敗戦後の飢餓の色が濃く残っていた時代に、そこへ行って遊べば、何か夢とうるおいがあるように感じられたものである。駅に隣接したマーケットでは、アメリカ占領軍の放出物資などが手に入り、そこでパイプ煙草を買って、喫茶店で音楽を聴き、2本立、3本立の映画を見て、充実した時をすごした。
その頃の印象が胸に残っていたのだろうか……数年後、日吉に住むことになる時、私は「東横沿線」というだけで定めてしまったようなところがある。
昭和34年から約25年……その間に住居を2回移転している。およそ10年ごとに1回、下田町から日吉本町へ、日吉本町から同町のやや西北の丘陵地へと移動しているが、2回とも700メートルか800メートルしか動いていないのだから、もう25年、この地に定着していると言っていいだろう。
人間にとって故郷とは…?
それは定着性の強い日本人の場合、父祖がそして自分が生まれ、育った、執着の強い土地ということが言える。
私は東京で生まれ、父の仕事の関係で、子供のとき台湾へ渡り、敗戦後帰国して、両親の故郷・岡山に住み、進学でまた上京した。学生時代は、東京の中で駒込、大塚、新宿、淀橋、牛込と、転々として移動に慣れきった。
その頃の私にとって、定着することは何か不安でもあった。生きることは移動することによって成り立つのだとさえ思われた。生涯移動しつづけてやまぬことがロマンチックなことに感じられた。
しかし、やがて恋愛から結婚ヘ―― 人なみのいとなみをすることになった時、現実は定着すべき住居を必要とした。
何回も落選をつづけた住宅公団の入居応募……その空屋抽選に当って入ったのが下田の日吉団地(※現公団住宅サンヴァリエ日吉)だった。
昭和34年10月、はじめて私と妻は日吉の駅に降り立った。駅から中央通りを下田の団地へ向って歩いた。街並みはすぐに途絶えて、両側は畑地になり、細い道が一本、だらだらと坂になってつづいている。行く手に砂塵が舞い、その風にのって若い掛け声や歓声がきこえてくると、道から慶応大学野球部のグラウンドが見える。家並みはいっそうまばらになって畑がつづき、周辺に小高い丘陵が見渡せる田園地帯……それは、若い二人が家庭をもって、働きながら定着する土地としてはけっして喜ぶべき光景ではなかった。東京の山手線の中で生活してきた、いわば都会貧乏症の二人には淋しくて、不便で……、正直そう感じながら言葉もなく歩きつづけた。やがて坂道を登りつめると、下田の大団地がひらけていた。
住むほどに日吉への愛着
それから10年、その団地の2DKに私たちは定着した。一つ所に10年とどまって、その土地の自然と四季の変化を味わうという生活を、私ははじめて知った。
自然のたたずまいもさることながら、4階の窓の真下に下田小学校の運動場がひらけ、春は卒業式や入学式、秋は運動会と、子供たちの元気を声や姿が、季節や時の流れにけじめをつけてくれた。夏は一般に開放される慶応のプールで泳ぎ、冬は、寒く晴れ上った日に、ベランダから遠望できる富士山が美しかった。
やがて二人の子供が生まれ、元気に成長すると、幼稚園や小学校、中学校と次第に地域とのつながりがひろがって、私の日吉定着は強いものになっていった。
その後、南へ下って日吉本町へ移ってからは、休みの日に子供を連れて、近くの丘陵地帯をよく散策した。雑木林の中に畑が点在し、草花の咲く小道を歩くのは楽しかった。
|
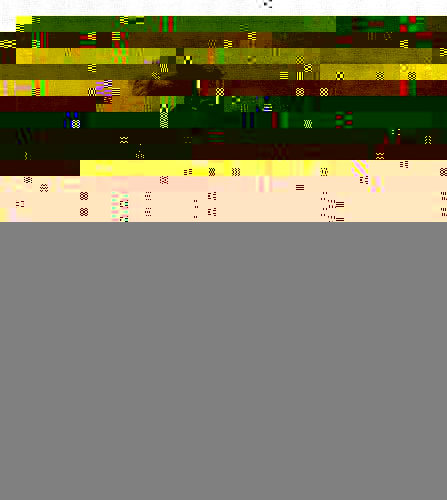
南日吉や綱島方面が一望の森谷邸の玄関先で
撮影:岩田忠利 |
|
|
|
映画監督・森谷司郎(もりたに しろう)さんの代表作には『八甲田山』、『動乱』、『日本沈没』、『海峡』などがある。最近公開された『小説吉田学校』も、みずから脚本を手がけるなど、話題をよんでいる。
|
|
草花を踏みしだいて歩いた丘陵が
しかし、周辺に家並が次第にふえ、緑にあふれていた丘陵がブルドーザーで崩され、次々と造成地に変わりはじめた。舗装道路が丘の奥深くまでつづいて、土や樹木の匂いが徐々に薄らいでいく。
かつて草花を踏みしだいて歩いた丘陵――その造成地の一隅にいま私は住んでいる。
春の強い季節風の中、丘の上に立つと、日吉は一面の家並に埋まって、その向うを東横線が走っている。
この25年の日吉の変貌を目のあたりにして、私はただ感慨にふけるのである。
|
|

★イラストマップ内の白丸内の数字は、本誌「とうよこ沿線」の普及協力店または普及協力の医療機関、計24カ所です。
|
|
|
|
 |
「とうよこ沿線」TOPに戻る |
 |
次ページへ |
 |
「目次」に戻る |
|
|
|
|