|
3百年の風雪に耐え、305体の羅漢さんご健在
|
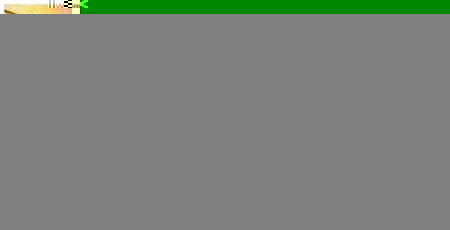
羅漢堂に整然と並ぶ等身大の羅漢さん
|
|

丸みのある近代的デザインの羅漢寺
|
|
昭和27年この寺を訪れた亀井勝一郎(※文芸評論家で日本芸術院会員)は、「埋もれた仏たち」と題し『芸術新潮』に寄せている。
――目黒不動のちょうど裏山にあたるところに羅漢寺という破れ寺がある。不動さんの方は戦火で丸焼けになったが、この裏山の一角はまぬかれて、羅漢さんの方は無事であったわけだが、その荒れようは頗るひどい。本堂というのも名ばかりで、屋根ははがれ、壁は落ち、内部から青空がみえる程だから、むろん雨もりも甚しいだろう。崩壊しかかった倉庫と思えばまちがいない。
この中に等身大の羅漢木造三百数十体がギッシリつまっているのである。狭いから桟敷を組んで、天井あたりまで雑然と押し込んである。(中略)。
左側にはこれ又荒れ果てた僧房があり、年とった尼僧が住んでいる。尼僧としての初代は※桂公の愛妾お鯉さん(安藤妙照)で、明治の美女は晩年をこの廃寺に羅漢を守って過したわけである。
4年前に、没したそうで、それ迄15年聞ここに住み復興に力をつくしたという。
関東大震災と今度の戦禍で、江戸の名残は殆ど潰滅したが、目黒の焼け跡の一角に、このように零落の姿で残っているとは、一層佗びしい感じを抱かせる。――
現住職・斎藤晃道氏から見せられた33年前のこの記事、みごとに復興した今の寺院からみると全く信じられない。これは、並々ならぬ努力と忍耐で築きあげた日高宗敏貫主の功績によるといわれる。
※「桂公」は本名・桂太郎。軍人で政治家。軍人として陸軍大将、政治家としては桂内閣の総理大臣3期歴任、公爵。大正2年(1913年)没。
人気のある高級茶屋「らかん亭」
昭和56年5月本堂は丸味を帯びたモダンな建物に一新、「これが霊廟ですよ」と教えられない限り、内部に納骨仏壇が納められているとは、誰も気づかないだろう。
金色に輝く三つ葉葵の寺紋を仰ぎ、右側入口に銅板の標柱が立っている。右手に参詣客や法事の人たちに食事や湯茶を供する「らかん亭」がある。
落ち着いた雰囲気のなか、精進料理や会席料理、お弁当、喫茶も楽しめるお寺さん。恐らく、こうした高級茶屋のあるお寺は沿線では見当たらないだろう。
一体ずつ異なる表情、305体
その奥にコの字型の羅漢堂があり、305体の羅漢さんが整然と並んでいる。像の表情は一体ずつ違う。中心に「仏はわが腹中にあり」と開腹してみせる羅怙羅(らこら)尊者像。一番奥に本堂があり、童顔につくられた怙華の釈迦牟尼仏を真ん中にして左右に、文殊・普賢・阿難・迦葉・白衣観音・延命地蔵・菩提達磨。左右6段には、さながら釈迦の説法を聴き入るかのように静坐した羅漢像が並
んでいる。
|

536体の羅漢像を作った開祖・松雲元慶 |
|
開祖・松雲元慶は京都の仏師で22歳のとき鉄眼禅師に師事、五百羅漢製作を思い立ち自力で一体一体寄木群像を十数年かけて536体を完成させた。
元禄8年(1695年)本所五ツ目(現江東区大島)に6千坪の境内を有した江戸最大の禅寺を築き、一時は徳川5代将軍綱吉公から寺地と山号を賜った。
その後、本所緑町(墨田区)に移されたが、明治42年現在の目黒の地に場所を変え、以後衰退の一途をたどり都内でもボロ寺で有名だった。
|
本堂の左手に歴代住職の石塔、聖宝殿、法堂と続き、その隣のホールから上下に通ずる階段があり各階の霊廟にと続いている。廟内はいくつものブロックに分かれ、納骨仏壇が2500基。ここには宗旨宗派を問わず納骨でき、毎朝夕勤行で供養されている。
その誦経の声が朗朗と堂内に響く音響効果はすばらしい。
あの羅漢像の一体一体の表情とともに、誦経の声が今でも心の底に染み込んでいるようである。
|