|
世田谷区にワサビを育む湧水
初冬のうららかな日の午後、或る湧水を求めて歩き回った。
住所は、世田谷区上野毛二丁目で、番地・所有者までわかっている。すんなりその場に行けたが、新しいマンションが建っており、すでにその面影はない。また、地形からみても、こんな所に自然と水が湧いていたとは到底考えられない。所有者がこのマンションと駐車場を挟んだ反対側に住んでおられることから、一応念のために尋ねてみた。やはりそんなものはなかったし、知らないという答えだった。
聞き違いだったかとがっかりしつつも、あきらめきれず、地形上から探してみることにした。
現在地は大井町線・上野毛駅から徒歩5分の覚願寺の山門前。路上はイチョウの葉と実が埋めつくし、いやな臭いに追われるようにして多摩川左岸の武蔵野台地から稲荷坂を下って丸子川沿いに歩くことにした。
かつての六郷用水であり、台地と比高差は約10㍍もある。その崖地には家が建ち並んではいるが、湧水が丸子川に注いでいると思われる箇所が数カ所あった。また、この時期なのに、紅葉と常緑樹のコントラストがたいへん美しかった。
そうこうしているうちに、住居表示は〝上野毛〃から〝野毛〃になり、第三京浜国道をくぐり、野毛二丁目にはいった。幾人かに湧水のことを尋ねた。どの人もわからないという。予定した時間は、とっくに過ぎているので、等々力駅への最短距離を歩いていると、台地の外れにある小さな支谷に入り込んだ。
湧水の匂いがしそうな、とても条件の良い所である。周りの様子をうかがい表札を見たら、冒頭の上野毛の方と同姓の方があちこちにいらっしゃる。ちょうどその時、配達にみえた酒屋さんがおり、祈るような気持ちで「ワサビを栽培している家がこの辺に?」と尋ねた。すると、「あっ、そんならあのお宅ですよ」と教えてくれた。
時間を気にしながら、さっそく訪ねてみた。樹木の手入れをしていたご主人の案内で、みごとな水量の、ワサビがフキとともに流れに沿って一面に生えている2つの湧水を見せていただいた。
一方の湧水は、池に流れ込み、大きな鯉が気持ちよさそうに泳いでいた。以前は、3つの水源があったが、そのうちの一つを飲料水にするため埋めてしまったという。また四季を通じて水量、水温に変化はないという。
都会の中のワサビ田を求めて2時間。上野毛と野毛は一字違いで二丁目と同じながら、番地が違って、同姓異名の屋敷内にそれがあったのである。
|
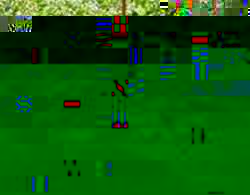
湧水の流れに沿って生えるワサビ
|
|

筆者がついに見つけたワサビを育てる湧水
|
|
民間伝承が残る湧水池
大井町線大岡山駅構内に、[太古より清水湧出の秘境大田区文化財 清水窪湧水(洗足池唯一の水源)請願成就に不思議な霊験 清水窪弁財天]という広告看根が出ている。
北出口から大岡山商店街をしばらく行くと、右に折れる所に急な坂道があり、この坂を下りきった低地がその場所である。清水はケヤキの大木の下、石組の間から湧き出ている。ここは現在、或る宗教団体の敷地になっており、弁財天ほかが祀られている。
大岡山駅に戻り、大井町線の戸越公園駅下車、戸越公園に向かう。この公園一帯は、かつて熊本藩のお
抱え屋敷であった。品川用水はこの屋敷に水を引いたのが始まりといわれており、その庭園の名残として2つの池がある。
公園の池は、現在は人工の水源だが、国文学資料館裏の池には湧水が見られる。どちらの池なのかわからないが、池の蛇にまつわる伝説が残っている。また、公園周辺には、下蛇窪・大間窪・薮清水など、湧水に関係する地名が残っている。
戸越公園でのんびりしたあとは、大井町まで足をのばしてみたい。
大井町駅からはちょっと距離があ
るが(途中までバスの便あり)、大井の水神(品川区南大井5-2026)と大井出石(いづるいし)の水神(西大井3・1)は、一見の価値がある。
境内に溶岩を約2㍍の高さに積み上げて人工の石窟を作り、そのなかに木造の祠を入れ、水葉乃売命を祀っている。他の石祠には、雨乞いを行なったことが刻まれている。また、ここの湧水は、虫歯を癒す御利益があるといわれてきた。
|

かつては熊本藩細川家のお抱え屋敷だった現在の戸越公園
撮影:一色隆徳(祐天寺) |
|
|
洗い場として使われた湧水
東京の区部は都市化とともに畑地が消滅し、今では野菜づくりすらできない状態となった。それとともに洗い場も埋め立てられ、宅地や公園にかわってしまった。
大田区馬込にはかつて各谷戸ごとに湧水を利用した洗い場があった。そこは、2㍍位の深さに池を掘り、その半分のところに竹の“さいの子”を敷いて、中へ落としたものはここで受けるようにしていた。ネギ・小松菜・ニンジンなどの出荷の時期になると、洗う人々で大変混雑したようである。
また、大田区南雪谷5丁目には、水神様を祀った洗い場があった(『とうよこ沿線』No.44参照)。お祭りの日にはオコワ(赤飯)を炊いて、竹の皮に包み、お参りに来た人たちもこれをいただき、それを食べると風邪引きが直るといわれてきたという。(水神宮は、現在雪ケ谷八幡神社境内に遷座している)
今でも洗い場の名残をとどめている湧水としては、
◆大田区南馬込5・7・10菅田家の湧水
◆大田区久が原2・4110中島家の湧水
◆大田区田園調布本町25・18 パラッツオ田園調布の湧水
などがある。とくに中島家の所のものは、[農場用洗い場]と書かれた札が柵に掛かっていて、その健在ぶりがうかがえる。
|
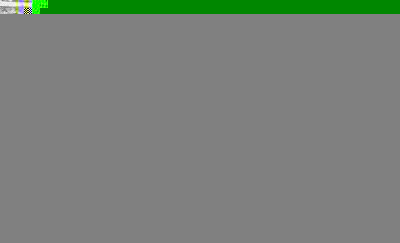
今も畑の中にある久が原の中島家の湧水 |
|
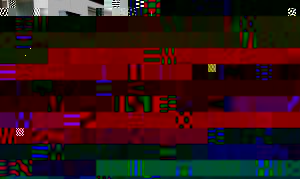
沼部駅近くのマンション敷地にある湧水
東京の名湧水57選の一つです
|
|
今も久が原台地からコンコンと湧き出るウマい水
今から2000年前の弥生時代、久が原台地には1000軒を超える大集落があったという。これは竪穴住居跡の“久が原遺跡”が物語る。これは、生活上、何よりも大切な“水”が豊富であったことの証拠である。
久が原台地の斜面からは地下水が随所に湧き出ていた。池上線千鳥町駅近くには清水が六郷用水に流れ込んでいたことから橋の名が〝清水橋″。久ガ原5丁自の宮田静雄家には清水が湧き出ていて屋号を〝清水″と呼んだ。
久が原の大田区役所特別出届所の下にある本光寺、その境内にある〝七面堂の湧水″は今でも、どんな日照りにも絶えることがない。しかも、保健所の水質検査でもお墨付きの適水である上に、じつに美味しい水だ。
この味を知っている人が、ほっておくはずがない。晩酌のウイスキーの水割り用にもらいに来る旦那衆、ポリタンクを車に積んだ喫茶店・寿司店・スナックなどの主人たちが、いくばくかのお賽銭を置いては定期的に汲んで行く。
|

イラスト:江川 久 |
|
|
ここから北へ数百㍍離れた三木兼吉さんの敷地内からも清水が湧き出ていたが、この地が今、久ガ原清水坂児童公園内の泉となって一般公開されている。
誌面の都合でここまでとするが、最後に、これらの湧水が東京砂漠の心のオアシスとして、いつまでも湧き続けてほしいものである。
|