大河ドラマ20本目の新機軸『峠の群像』
|
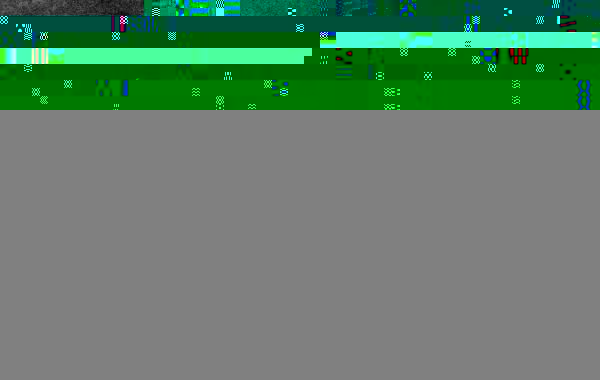
NHKスタジオ『峠の群像』撮影風景のひとコマ
|
|
|
NHK大河ドラマは日曜夜8時。重厚な男性路線歴史劇として世の亭主族の圧倒的支持のもと、デンと腰を据えている看板番組。並み居る民放が束になっての急追も許さぬ独走態勢である。
とくに本年度の『峠』は従来の忠臣蔵をがらりとイメチェンした大胆な構成で、当初誰でも小首を傾げたに違いない。
ところが回を追うごとに忠臣蔵らしくなかったこれが、ひょっとしたら最もらしいのでは、と思うようになったのだから大した説得力。
これは一つ、そのへんのところを探訪しなくてはと思ったのが渋谷の街へやってきたゆえん。
7月下旬のある日『峠』のチーフプロデューサー小林猛氏と妹尾・藤木両広報係にお話をうかがったのだが、相手は名にし負う天下のNHKのお歴々。こちらは名もなく貧しく美しき(?)巷の一主婦。さすがの私も叩けばコテンの感じ。
昭和38年に『花の生涯』を第1作として登場した大河ドラマは軌道に乗った安定感あり、20年目としては思い切った企画を、と構想を練った。
今までの忠臣蔵は話の面白さだけを追い、義士たちも芝居がかった英雄に祭り上げられていたが、彼らとて普通の人間、悩みも、迷いも、失敗もあったはず。優柔不断と見えても最後まで迷い抜くのが人情であり、単なる英雄活劇でなく、よりリアルにより人間臭くと方向を打ち出した。
今までは12月14日討ち入りでラストを飾ったが、『峠の群像』では11月の予定。それ以降は石野七郎次を始めとする討ち入らなかった家臣を描く。彼らはこれまでは一も二もなく卑怯者の格印だったが、討ち入りせぬほうにもそれなりの正義あり、それをキッチリみつめてみたい。ま、11月以降を期待してください! と小林チーフは自信ありげ。
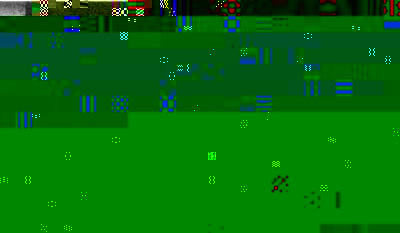
お食事中、ちょっと失礼して・・・
|
|
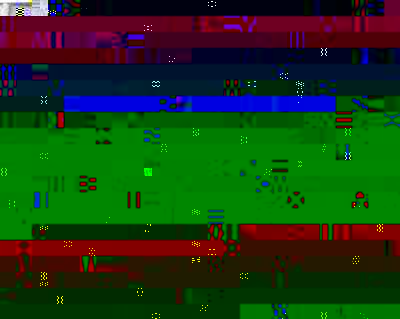
お色直しの真っ最中 |
|
汗と怒号飛び交うスタジオ内
続いて録画撮りの日、“106スタジオ”を訪れた森 邦夫カメラマンと私は報道班の腕章を渡される。本番スタジオはこれがないと入れない。はるか上部のガラス窓には鈴なりの一般見
セットは大石の郭(くるわ)狂いのくだりか…。郭通りと茶屋座敷。黒の絽着流しの緒方拳はスッキリ細身。敵娼の小林麻美はもっと細い。諌言に来た主税(ちから)に「まあよい、貴様も一人前ではないか、こっちへ来て呑め!」と息子を見やるやさしい大石の眼。そこへヒョコヒョコ幇間(ほうかん)登場。いかにもそれらしいと感心したら、駄目出し百出。も少しゆっくり、いやもっと小走りに、果ては「チガウ、チガウ、チャウヨッ」と怒声。
あんな1秒で終るシーンなど、あれでいいじゃないか、と私など思うのだが、プロの目には、なかなかどうして。その度に遠景に映る廊下を渡る遊女たちも歩き直すのだから、もう大変! やっと副調整室からOKが出たらしくフロアディレクターの大声「タイソウスバラシイということです!」。今までの労をねぎらう意味をこめてのユーモラスな言い方に、満場ドッとくる。
スターというものは、そこに居るだけである種の雰囲気を漂わし、見事な存在感があるものだが、緒方拳さんはまさにその通り。
ディレクターはキビキビした面持ち、動作もまことにどうもカッコヨク、女優や歌手たちが、収入的には一介のサラリーマンに過ぎない彼らに惹かれる芸能記事が頭をよぎり、うむ、ワカルワカルと独りうなずく。
|

「おひとつ、ど〜ぞ!」
|
|

和室のセット。天井に注目! 機材がずらっと
|
|
スタジオはドラマ産み出す生産工場
セットは画面に映る所は凝りに凝ってあるが、映らぬ所は手抜きもいいところ。
余分な金はビタ一文! の気構え充分で、聴視料支払者としては大いに頼もしい。庭の笹をそよがすための大型扇風機はフル回転し、庭石も敷石も踏めばグニャグニャの偽ストーン。
フロアは、3台のカメラ、ライト、録音機その他のコードが、蜘蛛の巣のごとく、天井は煙々のライトが雑然。そのライトに浮かぶもうもうたるものは、行燈の煙か、はたまたホコリか。ともあれスター居並び、華麗なドラマが生まれるスタジオとは、汗と怒号飛び交うまさに生産工場そのもの。
しかし、ピーンと張った緊張感は部外者の我々にとってもたまらぬ魅力! おそらくこの虜(とりこ)になって、制作者も俳優も渾身の力を振りしぼるのだろう。
メーク室では次のシーンに備えて若侍や遊女がズラを合わせ、紅を塗る。食堂では、お巡りさんと侍とナウイ女の子、アンバランスが妙にマッチした一連中が仲良く食事中。
そんなお馴染みテレビ局風景を後にしながら、次の日曜夜、自慢タラタラ夫に説明している自分の姿が目に浮かび、思わず肩をすくめた。
|

お化けでも出そうな竹やぶ
|
|
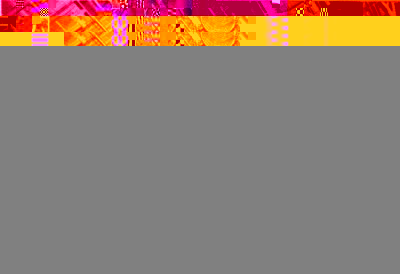
天井を見上げると、まさに工場のよう・・・
|
|
|