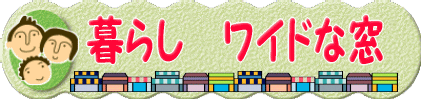 |
| �ҏW�x���F�������G/���S�F�z�����q |
| �ҏW�F��c�����@�@�@�@�@�m�n.201�@2014.9.06�@�f�ځ@ |
|
�@�@�@�@�@�@�@�@���摜�̓N���b�N���g�債�Ă������������B
|
|
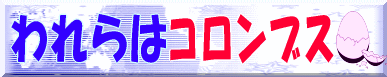 �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ |
 |
|
�@ �@���j�̍�ƐX�̓��@�@
�@�@�@�@�@�@�s�l�₩��ڍ��s���@�@�@�@�@
|
|
|
�@�@�@�����Z���Q���̃R�~���j�e�B�[���w�Ƃ��悱�����x�B�D�]�A�ڂ́g�����Łh
�@�@�@�f�ڋL���F���a56�N11���P�����s�{���m��.�W�@�����u���v
�@�@�@���E�ʐ^ �F�O�˓c�p���i�t���[�J�����}���@���Z�g�j
|
|
|
|
�@�@�@�@�@�@�]�ˎO���̉Ό��A��~��
�@�ЂƂ�̗���҂́A���ܘY�Ƃ������B�T���قǑO�����~���ɏh����B�J�l�ڂ̂��̗~�����Ɏ��ɉ���B
�@���̂Ƃ����a�X�N�i1772�j�Q��29���A���߁B�܂���̋����ɐ����͐����𑝂��A���c��т̑喼���~���瓒���A�A��Z�̏��ˌ��ɂ�����܂ł̕��S�L���A����24�L�����Ă������A�����]�˔��S�����̂���630���������ɂ��炷�A�]�ˎO��Ύ��̈�ƂȂ����B
|
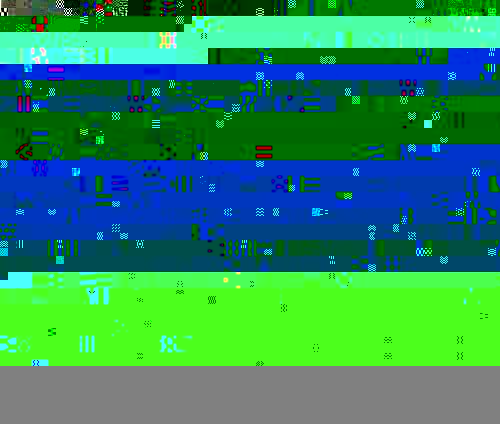
�]�˖��{����70�N�Ԃ��Č���������Ȃ�������~���{��
|
|
|
�@�@�@�@�@�@�s�l��ƌ��V����
�@�ڍ��Ɗ��c�����Ԗڊ����B���}���̕�̂ƂȂ����H���ł��邪�A�ڍ��w�Ƃ����Ă��ڍ���ɂ͂Ȃ��i���ɑ�����B
�@�ڍ��͖ڍ��쉈����ڍ��k�J�Ə̂������炢�N���̌������Ƃ���B�ڍ��w�͂��̍���ɂ���A���̍����т͍]�ˎ���ɂ́u�[�z���u�v�ƌĂ�A�g�t�ƕx�m�̒��߂̔����������ł������������B
�@�w���o��ƍ���ɂ�邭�����čs���������V����B�O���s�̗�������ɍ��x��25�b�قǂׂ̍��}�ȉ��肪�s�l��B���̍s�l������肫���Ă��炭�s���ƁA�L�������̖ڍ��s�����B
�@���܂肱�̍₪�}�ȍ⓹�ʼn����ɓ�V����̂ō]�ˎ���̒�����A���̈�т̖���E���J���V�����ɂ₩�ȓ����Ђ炢���Ƃ��납��u���V����v�����t����ꂽ�B���̓��͒��ڍ���S�V�����ʂ��������ł���B
|
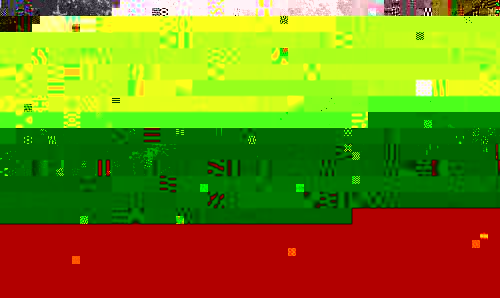
�ڍ��s���͎Q���������B�L�������͐Î₻�̂���
|
|
|
�@�@�@�@�@�@��~���ƌܕS����
�@��~���͋}�ȍ⓹�A�s�l��̓r���ɂ���A���i�̍��i1624�j�A�o�H���i�R�`���j���a�R�̍s�l�A��C�@��i���������ق�����j������@�����������ĊJ���ꂽ���ŁA��ɏC���s�l�h�̖{�R�ƂȂ�A�����̍s�l�̍s�������Ƃ���ƂȂ�A���ꂩ��s�l��̖������܂ꂽ�B
�@���a�X�N�̍]�ˑ�̉Ό��ƂȂ�����~���́A�]�˖��{�ə�i�Ƃ��j�߂��A70�N���̊ԍČ���������Ă��Ȃ��B���̖��a�X�N���u���f�i���C���N�j�̔N�v�Ƃ��ĔN�����i��������Ƃ����Ӗ��Łg���i�h�Ƃ��炽�߂��A�����u�L���z�̋֎~�A�J�����u�L����s�����悤�ɂȂ����Ƃ����B
�@���̉Ύ��ɂ��]���҂̗�����{���邽�߁A�߉ގO���A�\�Z���q�A�ܕS�����̐Α��Q���J���Ă��邪�A���܂��ɔ߂��݂̉����R���Â��Ă���悤�ŁA�K�˂�҂����|�����ɂ͂����Ȃ��B
�@�����Ƃ́A���߉ޗl�̋������āA�C�Ƃ������J���A����̋��n�ɏZ�ސl�̂��Ƃ��w���āA�l�̐��̋ꂵ�݂��Ԃ߁A�����Ă���邻���ł���B
�@��~���̌ܕS�����̂Ȃ��ɂ͐Ԃ�V����������e�̑��A���ł͗L�肦�Ȃ����̂��݂��A�e���̑���ɂ͑�̂Ƃ��̋]���҂̖@���Ƒ��������܂�Ă���A�l�̐��̊�т�߂��݂ȂǁA���܂��܂Ȋ�����i���̂Ƃ��̒��ɕ������߂Ă��邩�̂悤�Ɏv����B�܂��A���̎��̕�n�ɂ́A���^�i��������j�Ƃ�����l�̕悪����B
|

�ܕS�����̒��ɂ͎����̐g���̐l�����o�����Ɓc�c
|
|
|
|
|
�@�@�s�l�≺�̉돖���ɔ��S�������̗��l���c
�@��~������s�l�����������ƁA�s���ł��L���Ȗ����Ƃ��Ă���ڍ��돖��������B���̕~�n�ɖ����@�Ƃ������@������A���Ă����ɂ͔O���O���̑m�A���^���Z��ł����B���̑m�����A�ߗ��̔��S�������̏�l�A�g�O���̖{�l�ł���B
�@�g�O�́A����10�N�i1683�j��������P�X�ʼnΌY�ɏ�����ꂽ��A�m���ƂȂ�A�����u���^�i��������j�v�Ɖ��߁A�����@�ɓ���B�ڍ��s�����Ɛω����̊ԁA����10���̓����A�O�����ƂȂ��A�u����Q�P�����̎Q�w�𐬂������A�����̕������B
|
|
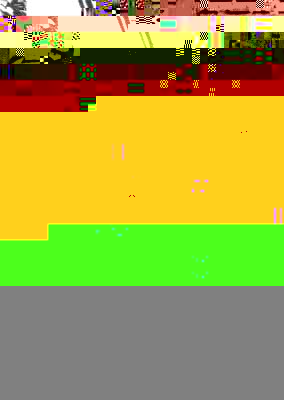
�Ⴂ���͔��S�������̗��l�A�����ĔO���O���̑m�E���^��l�̕�B��~���ɖ��� |
|
|
|
�@�@�@�@�@�@���Ƒ��̋��������ڍ���
�@�����̎s�X�̔��W�͒����ԁA�ڍ���̐��Ŏ~�߂��Ă����B��̓s�S�����}�ȊR�ɂȂ��Ă������߂ŁA�ڍ��̃^�P�m�R�ɑ�\�����_�Y���Ȃǂ��s���ɉ^�Ԃ̂ɂ��A���̂����肪��ł������B
�@���āA�s�l��������Ƃ���A�ڍ���ɉ˂����Ă��鑾�ۋ��B���ł͕��}�Ȃ����ŁA�����������ł��邪�A�]�ˎ���ɂ͈����L�d�������]�˕S�i�ɕ`���قNJG�ɂȂ�A�[�`�^�̐����˂����Ă����B
�@�؋��l�ɂ��A�U�N������Ŋ����������������ۋ����^���ŗ�����A�т����C���ꂽ�����ł��邪�A���ł͖��̂Ɨ����݂̂��̂�`���Ă���B
�@���̋�����ڍ��s�����܂ł̓��ɂ́A�������㖖����̈���ɔ@�����̂����y�@崗����A�ؑ��ܕS��������L���闅�����ȂǑ����̎����W�܂�Ƃ���B
�@�w�ɂ��߂��A�����̓͂��Ƃ���ɂ���Ȃ���A�R�̎�̊��q�������킹��悤�ȐÎ₳���������B
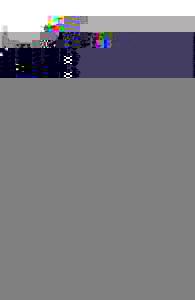
���͖��݂̂̑��ۋ�
|
|
|
|
|
 |
�u�Ƃ��悱�����v�s�n�o�ɖ߂� |
 |
���y�[�W�� |
 |
�u�ڎ��v�ɖ߂� |
|
|
|
|