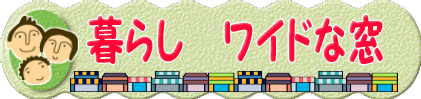 |
| �ҏW�x���F�������G/���S�쐬�F�z�����q |
| �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�ҏW�F��c�����@�@�@�@�@�@�m�n.187�@2014.8.30�@�f�ځ@�@ |
|
�@�@�@�@�@�@�@���摜�̓N���b�N���g�債�Ă������������B
|
|
|
�@ �@�@�@��ы��̌��㊯���~�@�ɓ���
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i���s����q����j
|
|
| �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ |
|
�@�@�@�����Z���Q���̃R�~���j�e�B�[���w�Ƃ��悱�����x�B�D�]�A�ڂ́g�����Łh
�@�@�@�f�ڋL���F���a56�N�X���P�����s�{���m��.�V�@�����u���v
�@�@�@��ށE�� �F�a�J�ЗY�@�i���Z�g�j�@/�@�ʐ^�F�O�˓c�p���i���Z�g�j
|
|
|
|
�@��������܂ők���N�i����˂��j�S���B���̌�㊯
�@�@���Z�g���琼�������A�K�荕����u�~�Z���v��O�̍⓹���u�q����L�ˁv���ʂ֓o���Ă䂭�ƈɓ��Ƃ�����܂��B
�@���X���钷������\�����ɓ��Ɓi�����E�������Ȃ��⁄�j�͐����t�͌��̒r��ƁA�����撷���̗�؉ƁA���Ë敽�̐��c�ƂƂƂ��Ɂu��N�S���v�ƌĂ�Ă��܂����B�����j�b��聄
�@�R�����邱�̕t�߂ɂ́A���{�����ƒ�k�Q�i���Ƃ����ȂЂ߁j���J�����k���_�Ђ�A�@��@�A����Ɍܗ֓����̎c��ɓ��ƕ�n�ȂǁA���X�̎j�Ղ�����܂��B
�@��N�S���Ƃ�����Ƃ���A��������ɂ܂ł����̂ڂ�ɓ��Ƃ̗��j�͂������łȂ��_������܂����A���Ƃ̌���i�����Ёj�ɂ��ƁA���q���{�̎����������Ă����k���Ƃ̎��ォ�獂�і����q���d�i�]�˒����A�q������E��c���̈ꕔ��m�s�������{�j�܂ő㊯�̔C�ɂ������Ƃ̂��Ƃł��B
|
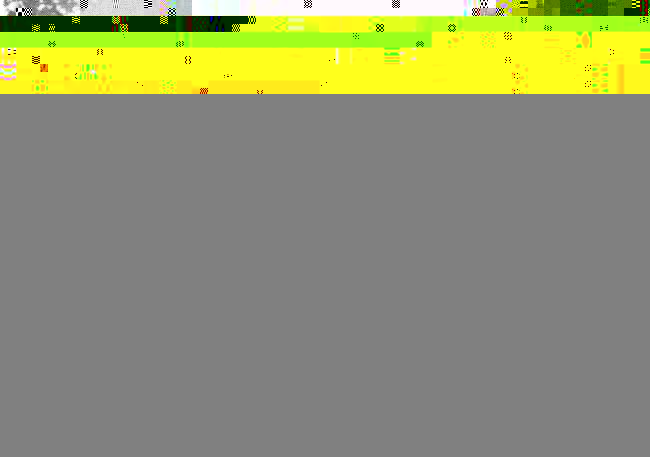
���ʂɎ��䂪�݂��A���~�ɏオ��鋌�ꉮ�B���a39�N���
|
|
|
�@�@�@�@�@�@�n�k���S�̖����A�ɓ����i�{���F���\�쎁�j
�@�u�V�ҕ������y�L�e�v�̎q������̍��ɂ́A
�i���ƎҕS���������Ƃ������������쎁�Ȃ荟���̋��ƂȂ�c�c�L���S�������i�����E�����j�@�B���̘k���i��ɂ����j�̖��ɓV��10�N�i1582�N�j�p�߂W���P����ы��a���i�q����j�x��i��������j���ɏ���҂Ƃ��邹��A���ꓡ������c�Ȃ�ׂ��A�����͒x��Ə����A���̍���蓖���ɋ��肵���Ƃ͒m���j
�@�ƋL����Ă��܂��B
�@�܂��w�����ƌn�厫�T�x�ɂ́s�k���S�̖��������쎁����r�ƍڂ��A�퍑�����A�k�����Ɛb�Ɏq��������\�쎁�y�шɓ���������A�w���c���O���̖x�ɂ́q��яa���A���啪�O�ѕ��r�ƋL����Ă���܂��B
�@����Ƃ͈ɓ����ł͂Ȃ����A�Ƃ����Ă���A�����E�����Ȃǂɂ��A���݂́u�ɓ��v���ɂȂ������̂Ǝv���܂��B
|
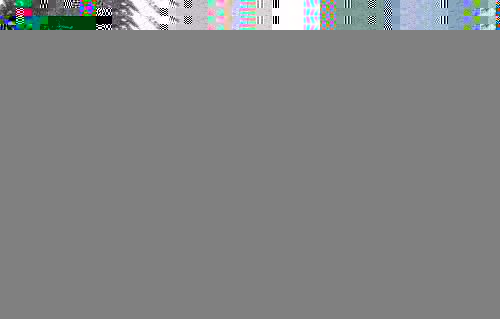
�Q�K�͔N�v�Ă����Ă���������
|
|
|
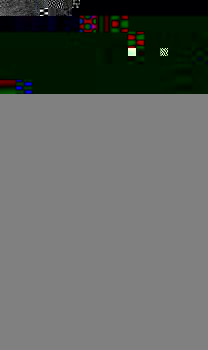
�����������ɂ́u���ґ��v������A���q���������Ă����Ƃ���
|
|
�@�@�@�@�@��̕ꉮ�͍]�ˎ�����i�N�Ԃ̌��z
�@�u�V�ҕ������y�L�e�v�̎q������̍��ɂ́A
�i���ƎҕS���������Ƃ������������쎁�Ȃ荟���̋��ƂȂ�c�c�L���S�������i�����E�����j�@�B���̘k���i��ɂ����j�̖��ɓV��10�N�i1582�N�j�p�߂W���P����ы��a���i�q����j�x��i��������j���ɏ���҂Ƃ��邹��A���ꓡ������c�Ȃ�ׂ��A�����͒x��Ə����A���̍���蓖���ɋ��肵���Ƃ͒m���j
�@�ƋL����Ă��܂��B
�@�܂��w�����ƌn�厫�T�x�@�ɂ́s�k���S�̖��������쎁����r�ƍڂ��A�퍑�����A�k�����Ɛb�Ɏq��������\�쎁�y�шɓ���������A�w���c���O���̖x�ɂ́q��яa���A���啪�O�ѕ��r�ƋL����Ă���܂��B
�@����Ƃ͈ɓ����ł͂Ȃ����A�Ƃ����Ă���A�����E�����Ȃǂɂ��A���݂́u�ɓ��v���ɂȂ������̂Ǝv���܂��B
�@��c�̕��ɏ����琔���A���݂̎��ꂳ���18��ڂ������ł��B
�@���Ƃ́A���B�E���c�����ʂ���ڏZ���Ă���ꂽ�Ƃ̐�������A�����̑c�u�ɓ��������z���i���i�U�N��1777�N���j���单���Ɏc���Ă������ꉮ�́A���a39�N�ɉ�̂���܂����B
�@���j�����܂ꂽ���������̔_�@��⓹��ނ́A���c�́u���{���Ɖ��v�Ɋ���A������̉������́A�֓���k�Ђŗ������Ă��܂��A�C������܂����B
�@�����E�吳����܂œ��n�������Ă̑�n�傾�������Ƃ́A��O�܂Ň��N�v�ć���������̂Q�K�ɐς݂��܂�Ă��������ł��B
|

�M�҂Ɠ������̎Ⴂ����E�ɓ����ꂳ���
|
|
|
|
|
|
�@�@�@�@�@�i�D�̎U��X�|�b�g
�@�ɓ��Ƃ̎��ӂ́A��O�ɂ́w�{�{�����x�Ȃǂ̉f�惍�P���s���A�ߔN���e���r�h���}�̎B�e������܂����B
�@�������Ղ��ӂ�Ɏc�铖�n�ɂ́A�u�e�����v�u�\�����v�Ȃnje�̏ꏊ������܂��B
�@������̖ʉe���c���A�Ñォ��̃��}���̂��ӂ����s�w��ۑ����Ɉ͂܂ꂽ�ɓ��Ǝ��ӂ��A�쒹�̂���������Ȃ���A�k�����������߂ău�����Əo�����Ă݂܂��B
�@ |
|
 |
�u�Ƃ��悱�����v�s�n�o�ɖ߂� |
 |
���y�[�W�� |
 |
�u�ڎ��v�ɖ߂� |
|
|
|