|
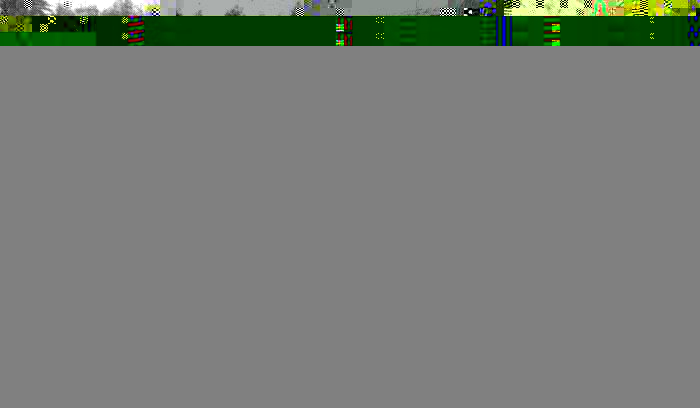
この木造の民家に関家のご家族は、代々400年以上生活しています
|
|
|
3代将軍・家光公もお休み。その置き土産が関家の“家宝”
創刊号でも紹介したが、中原街道は相模国中原(平塚市中原)と江戸城・虎の門を結ぶ道。江戸への最短距離の街道で束海道の裏道として武士や商人の往来は激しく、かつては繁栄した道である。徳川家康がタカ狩りや駿府(静岡市)との往復の便のため平塚市中原に御殿を建てたのは1598年(慶長3年)。以来この道を「中原街道」と呼ぶように。
中原街道に面した関家は、江戸時代から先々代、曽祖父・関八郎右衛門(神奈川県議、県軍部会議長)まで〝名主と代官〟であった名門。なかでも3代将軍家光が、タカ狩りの行き帰りには関家を休憩所としていた。その書院は間口5間~奥行4間で今なお現存、当時家光公が置き土産とした三つ葉葵の紋入り〃御弁当箱〟は同家の家宝となっている。
|
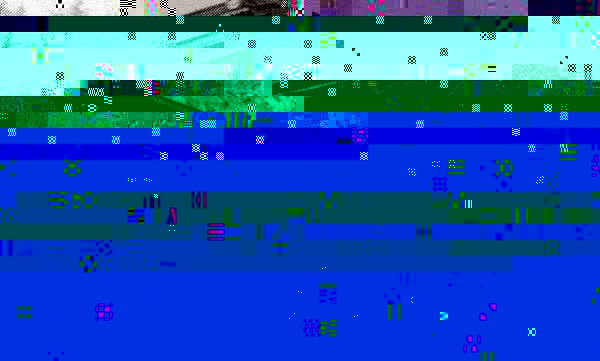
3代将軍家光公がタカ狩りの行き帰りに休息した書院も現存
|
|
|
長屋門は安政の大地震で崩壊。半分に縮小したのが間口20㍍
4000坪の敷地内で目立つ長屋門は、江戸後期の造りで間口11間(20..1㍍)~奥行2・5間の2階建て。しかも、この門は安政の大地震で崩壊、明治の頃半分くらいに縮小して再建したのだという。往時の代官の権勢がうなずける。
昭和62年完成をめどに開発が急ピッチで進む港北ニュータウン。ブルがうなる現場は関家から200㍍の至近。あの代官の栄光の歴史と祖先の積年の苦労が、失われてゆく自然に何かを語りかけているように思えた。
|
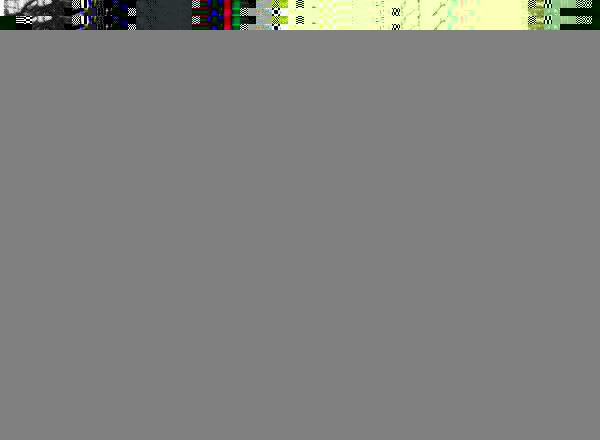
安政の大地震で崩壊。明治後期に半分に縮小して建て替えてもこの大きさ、20.1㍍
|
|
|
|