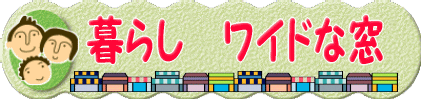 |
| 編集支援:阿部匡宏/ロゴ作成:配野美矢子 |
| 編集:岩田忠利 NO.182 2014.8.28 掲載 |
|
★画像はクリックし拡大してご覧ください。
|
|
|
13代続く長屋門、珍しいお篭も栗山重治家(目黒区緑が丘)
|
|
|
沿線住民参加のコミュニティー誌『とうよこ沿線』。好評連載の“復刻版”
掲載記事:昭和55年9月30日発行本誌No.2 号名「秋」
取材・文 :大崎京子(菊名。写植自営)
|
|
|
名主の長屋門
自由が丘駅から車が全然通らない静かな道を歩いて10分ぐらい。見えてきました、あれが名にしおう長屋門です。電信柱の住居表示を見るまでもなく、目黒区保存樹のケヤキの大木と、前日グラビアやら資料やらで頭につめ込んできた長屋門のホンモノのいかめしい門構えが視野に飛び込んできました。
これだ、これだ! そういえば田舎のおじいちゃんのうちにも、こういうような門があったんだなあ。なつかしい気持ちでいっぱいです。入り口には「旧名主宅」の立て看板。それを読んでいるうちに、だんだん歴史が身近なものに感じられてくるのです。
とこうするうちに、栗山家の第13代の当主・栗山重治さんが出先から帰ってこられました。髪に白いもののまじる初老の紳士です。お宅へ上がって早速いろいろな資料を持ち出して詳しく話してくださいました。

昭和53年、栗山重治家。徳川時代の名主屋敷の長屋門
後方が母屋。昭和五十年代初頭には長屋門は都立大駅〜自由が丘駅間に5カ所あり、その見学会が目黒区主催で開かれたことも。
提供:栗山重治さん(緑が丘1丁目)
|
|
|
母屋は区に寄贈、すずめのお宿緑地公園に移築
茅ぶきの母家の老朽化が激しいので惜しいながらも去年解体して、それは目黒区に寄贈し「すずめのお宿公園」に移築され一般公開されていること。去年の春篤志家が集まって「長屋門見学会」が発足し、都立大から自由が丘まで5カ所ある長屋門を約100人の参加者が見てまわったこと。戦後間もなく、街を明るくするために「街路灯維持会」をおつくりになって、それが碑文谷警察の防犯組織の一つ、太平緑(たいへいろく)という支部、つまり大岡町、平町、緑が丘を網羅して支部になったこと、今も残っている350年前の年貢米取り立ての記帳のこと……等々。
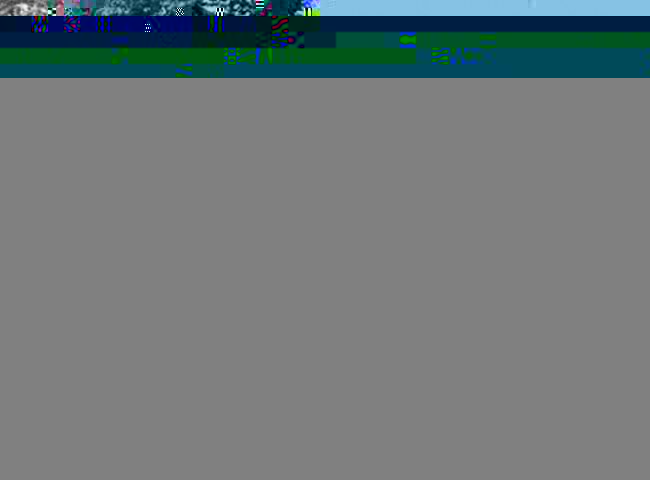
昭和54年8月、解体移築工事風景
この長屋門は解体され目黒区文化財として碑文谷の「すずめのお宿緑地公園」に移築され保存されています。
提供:栗山重治さん(緑が丘1丁目)
|
|
そして文化14年(1817)卯年7月に、あるお坊さんによって書かれた栗山家の「御戒名曼陀羅」という系図を見せていただきました。私が中学2年の夏休みにつくった、たった5代しかさかのばれない、つたないわが家の系図を思い出します。
名主のお出かけは、このお篭で
栗山さんのお宅で、特に私の興味をそそったものに、長屋門の下につるしてある「お篭」があります。エッサ、ホイサと担ぐあの篭で、キリの板や竹の釘などから出来ています。内部をよく見ると、あぐらをかいて座った時に、頭をもたせかけるへこみのついた板がうしろにあって、前には手でつかまる所やら折り畳み式のテーブルも、ついているんです。
そこに座って江戸時代に思いを馳せながら、若い衆に担いでもらいたい、という気分が押え難くふくらんできました。一体どんな乗り心地のことでしょう。
お篭に未練を残しながら、タイムマシンをおりて、おいとますることになりました。
お孫さんをおんぶして、門の外まで送ってきてくださった栗山さんは、一人の優しいおじいちゃんなのでした。
|

昭和53年、篭と13代当主・栗山重治さん
栗山家の長屋門に吊るされてある“おかご”。先祖の名主の方はこれに乗って出かけたそうです。
提供:栗山重治さん(緑が丘1丁目)
|
|
|
|
|
 |
「とうよこ沿線」TOPに戻る |
 |
次ページへ |
 |
「目次」に戻る |
|
|
|