“小杉御殿”の跡
中原街道は、五反田で第二京浜に発し、まっすぐ丸子橋に延びる。橋を渡ると、道は左へ大きく曲がるのと直進するのとある。左折が綱島街道の元住吉・日吉・綱島方面。直進が平塚市中原に通ずる“中原街道”である。
家康は慶長9年(1604年)相模の中原(現平塚市中原)に別荘を建て、休養と地方視察の基地としたといわれる。このときから平塚・中原~藤沢用田~瀬谷~中山~小杉~雪谷~三田をへて江戸へ入る道路を中原街道と呼ぶようになった。
この歴史が物語るように、丸子橋から直進、東横線の踏切りを渡り、直線で西明寺というお寺の入口に突き当たるこの街道は、どことなくその家並みに昔日の面影をしのばせる風情が残っている。
小杉御殿は1万2千余坪、家康、秀忠、家光、家綱など4代の将軍がタカ狩りをしながら民情視察、ここで休養したという。そのため、当時この界隈はめし屋などが並び、城下町のような賑わいだった。
かつてのその地の一画に原平八家は建っている。時代劇に出てくるような〝武家の土壁づくり〟。庭は1000平方㍍…、きれいに刈込んだツツジが色とりどりに満開。築山には樹齢250年のイトヒバやカシの木、どちらにも「川崎市指定保存樹」というトタンのラベルが幹に付けてある。暗黙のうちに名門旧家とわかる。
|
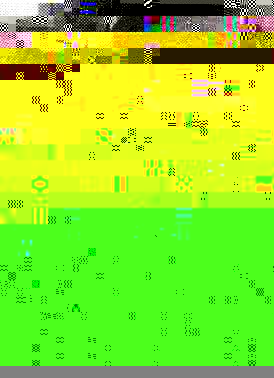
「大陣京」当主・原 平八さん
|
|
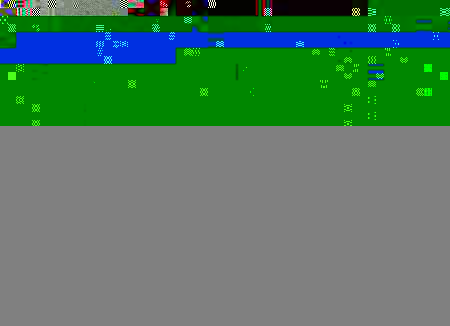
土壁づくりの原家の入り口
|
|
|
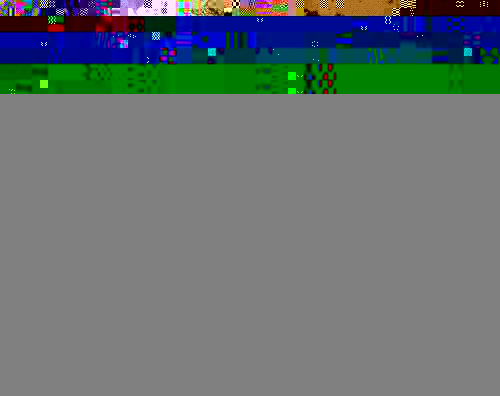
庭には十数本の松の大木。その下の築山に樹齢250年で川崎市指定保存樹のイトヒバとカシの木が生える。築山越しにインタビュー中の縁側を望む |
|
|
|
大名の遺品や太田南畝の文献も
ご当主・原平八さんは71歳というのに、かくしやくとして地下タビ姿、腰に木鋏をさげ、
「ウチよりもっと古いのは、安藤義久さんの家だよ。徳川時代から代々名主をやってたんだから…」
といって植木の手入れをひと休み、縁側に腰かけた。
そう話しながら、地下タビの〝こはぜ″をはずし、家の中へ。
西明寺の参道入口の右手が、2代将軍秀忠がつくった〝小杉御殿〟があったところだ。いま、その角は会沢畳店であるが、御殿の表門だった所だ。
「こんなもんが、家の中を片付けていたら、棚にゴロッとしてたんだよ」
見ると、いかにも年代ものらしい1㍍ほどの板。そこにはハッキリと(<8月7日松平出羽守様休>と毛筆で黒々と記されている。これは、大名が御主殿に休んだとき、玄関に掲げる〝宿札″というものだそうだ。つい最近まで<松平伊豆守様御泊>も残っていたという。
また当家のことは、太田南畝の作『調布日記』にも出てくる。南畝は「蜀山人」とも称し、今日の評論家のはしりともいわれ、その書に、
<又細道をゆきて小杉村にいり、原平六が家にやどりとる。比所の鎮守は神明宮惣社権現杉山明神なり……。調布日記(文化5年19日>
|
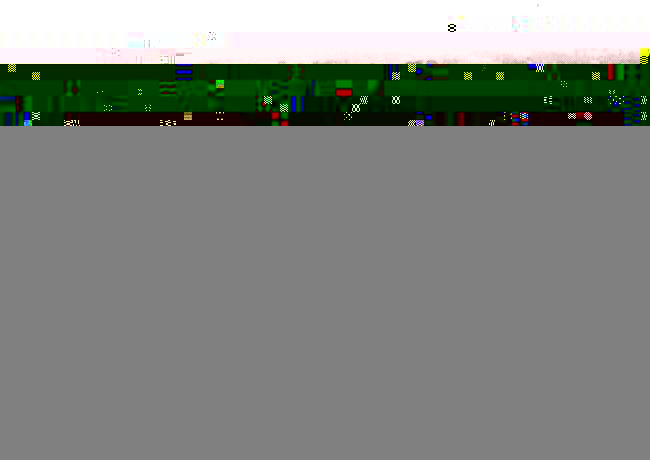
大正12年6月、原平八家前の中原街道から東横線開通3年前、一面水田の現武蔵小杉駅方面
手前の道が中原街道。街道は手前で直角に曲がり、さらに100㍍ほど先で直角に右折する。2度もカギの手に曲がる場所は中原街道ではここだけ。2代将軍。秀忠が小杉御殿を良からぬ輩から防御するためカギの手の構造にしたという。
提供:安藤十四秋さん(小杉陣屋町) |
|
|
原平八家は、鎌倉時代には北条家の流れをくむ武士だった。その証拠には鎌倉時代に着用した、よろい、かみしも、大刀・小刀(関孫六作)などがいまでも保存されている。
当家の屋号は、現在「大陣京」と呼ばれているが、かつては〝大尽隠居″(大金持ちの隠居)とか〝平六大尽″で通っていた。が、「わしの代になって、建設業者の登録を取るのに“大陣京”としたんだよ」
と話されるように、現在の家業は建設業。それも原さんは、気っ風のいいトビ職の頭で、川崎市内や神奈川県内の同業組合の会長や副会長を務める人。さらに町内会長や民生委員なども兼務、なかなかお忙しい。
同家の一族には、神奈川県議・原正己さん(元神奈川県議会議長)、その父・原正一さん(元神奈川県議会議長。横浜の天婦羅の老舗〝天吉″の創業者・原庄蔵さん、また「人生劇場」「赤城の子守唄」など数々のヒット曲を生んだ作詩家・佐藤惣之肋もその血が流れている。
|