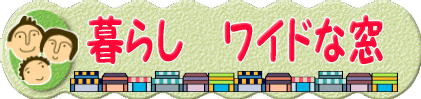 |
| 編集支援:阿部匡宏 |
| 編集:岩田忠利 NO.178 2014.8.25 掲載 |
|
★画像はクリックし拡大してご覧ください。
|
|
|
| |
|
沿線住民参加のコミュニティー誌『とうよこ沿線』の好評連載“復刻版”
掲載記事:平成2年1月20日発行本誌No.49 号名「梧(あおぎり)」
構成・編集 :岩田忠利(編集長) / イラスト ・マップ:石野英夫(元住吉)
|
|
|
|
滝ノ川物語
文:故山室健作(六角橋2丁目。宗作氏厳父)
今の地図を見ると六角橋の北原公団付近や、三ッ沢のゴルフ場の辺りまでも、下水の落し口としてこの川を利用しているのがわかる。今こそ上流も下流もこんなに濁っているが、昭和の初め頃まではこの上流は子供の水浴びの場であり、ドジョウやフナやモクゾウガニ、時としてはウナギの棲家でもあった。
この水源は江戸時代後期の記録によると、六角橋の二ツ池(今の市民プールを含む一万八千平方メートル)と片倉・神大寺・斎藤分・三ッ沢の六つの溜井とされるが、このほかに田のしぼれ水や幾つかの湧き水が集まり注いでこの川を形作っていた。
湧き水の一つと伝えられる権現山の滝水もこれに注いだ。この滝も安政3年(1856)暴風のあと涸れ果て、前記溜井とともに原形を求め難くなってしまった。
この川や水は、付近の人々から愛され、利用されてきた。開港時には成仏寺門前まで船便があったという。そしてそこに、ささやかではあるが史跡や、史実や物語が残された。
天保2年(1831年)鶴見川一件願書御写し、下書きもその一つで、鶴見川の氾濫に苦しんだ幕府がその分流を白幡村、六角橋村その他に流そうともくろみ、測量をしているのを知って関係村々の村役人は、連名で陳情を重ね、ついに計画を断念させ、子安・神奈川一帯の田を守ったことがあった。
こうして滝ノ川は古くから関係者たちによって守り育てられてきたが、町の発展とともに人家が増え、下水を賄うこの川の川底は上がり、大雨の時は下流地域の浸水も頻発するようになった。
前記の護岸も、この対策として震災後の国の横浜復興工事の一部として行なわれたもので、河口より栗田谷辺まで川底をさらい幅員を整えてかくのごとく立派なものとなった。
市電六角橋終点前後のコンクリートの護岸は、川底の土やゴミを取り除くことができた。六角橋終点の境橋下の上下流の護岸工事は昭和初期に行なわれた。これは川底までコンクリートで固めたもので、流速は文字通り「滝ノ川」の名に恥じないものとなった。
その後逐次、関係者の協力によって部分的に改修され現在に至っている。その時その時代の人々の努力によって改修され利用され続けているこの川は、古く、また永久に生き続けてゆくことであろう。 |
|
|
|
|
|
|
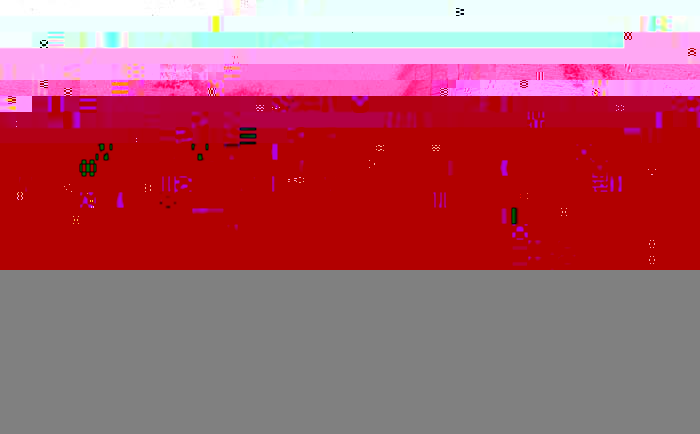
明治43年(1910)、現六角橋交差点付近にあった房陽舎牧場
飲食店の末広園先代鈴木春吉さんと先々代・喜之助さんが2代にわたり、この牧場を経営していました。昭和20年5月の横浜大空襲で全焼し、この場所で飲食業に転業しました。
提供:末広園(西神奈川3丁目)
|
|
|
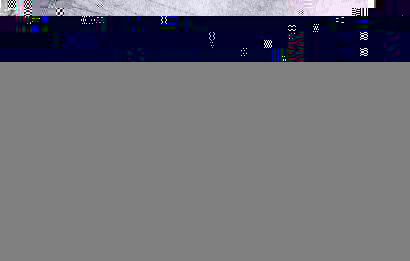
昭和29年横浜市電六角橋停留所と外食券食堂
写真は現在の六角橋交差点ですが、電車の後方は、開通して2年目の「行政道路」と呼ばれていた現在の上麻生道路。右手は「外食券 厚生食堂」の現在の末広園です。
戦時中や戦後、米の統制下では外食券は外食する者のために発行された券で、外食券が無い者は外食できず、旅館に泊まって食事するときもこの券が必要でした。「外食券食堂」は券持参者に食事を提供することを指定された食堂です。
提供:神奈川大学(六角橋3丁目)
|
|
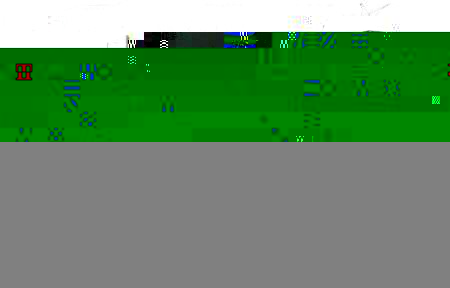
昭和43年この年廃止になる市電。終点・六角橋停留所
この路線は、横浜駅・保土ヶ谷橋・弘明寺を通り、尾上町・高島町をぐるっと回る循環路線でした。
市電が開通した昭和3年当時の料金は、市内均一6銭。廃止になった昭和43年は、同じく均一料金の20円でした。昭和18年までは朝7時までに乗ると安くなる早朝割引がありました。
「朝7時を過ぎた、過ぎないで、揉めたことが随分ありましたよ」と話すのは、横浜市交通局出身の元横浜市議・川俣勝一さん。
提供:川俣勝一さん(白楽)
|
|
|
昭和25年の世相と六角橋停留所前
壊滅的打撃を受けた敗戦からわずか4年余、ようやく人々の心に明るさを取り戻しつつある昭和25年――。
前年24年には第3次吉田茂内閣成立。1ドル360円の為替レートが設定され、街では食糧事情も好転し料理店が再開。
また湯川秀樹博士が日本人で初のノーベル賞受賞などの明るいニュース。ちまたに「トンコ節」「長崎の鐘」「銀座カンカン娘」などの流行歌が流れ、伴淳の「アジャパー」そして「駅弁大学」「ヒロポン」が流行語となっていた。10代の少女、美空ひばりが映画初の主演「悲しき口笛」でデビューし、話題となる。
白楽の話題では「ヨコセン」の名で親しまれてきた横浜専門学校が昭和24年の学制改革で「神奈川大学」と改称し、いよいよ白楽の地に“大学”が誕生する。
翌25年には1000円札が発行され、魚や衣料の統制撤廃、そして熱海市では1015戸が焼ける大火。さらに6月、朝鮮戦争の勃発‥…。5年間特需景気が続き、戦後初の好景気を迎えた。
白楽駅周辺では名物の“市電”が空襲で線路や電車が破壊されたが、これもすっかり復興。市電の運賃はどこへ行くにも格安の均一料金というのが魅力。それも手伝って駅の周囲や六角橋には空き地を利用して“闇市”が移転してくる。それ目当ての市電利用の来街者も日ごとに増える。市電六角橋停留所界隈は、俄然賑やかになったきた。(岩田忠利)
|
|
|
昭和25年の六角橋停留所前(西三商興会)
復元:岩田忠利(編集室)
協力:星野卯平(星野陶器店)/斉藤 巌(斉藤用品店)/鈴木喜也(末広園)/平林吉造(柳屋フルーツ)
|
|
|
|
|
|
 |
「とうよこ沿線」TOPに戻る |
 |
次ページへ |
 |
「目次」に戻る |
|
|
|