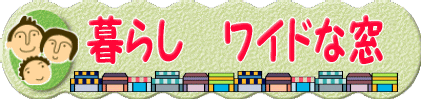 |
| 編集支援:阿部匡宏 |
| 編集:岩田忠利 NO.173 2014.8.20 掲載 |
|
★画像はクリックし拡大してご覧ください。
|
|
|
| |
|
沿線住民参加のコミュニティー誌『とうよこ沿線』の好評連載“復刻版”
掲載記事:昭和60年9月28日発行本誌No.30 号名「楠」
構成・編集 :岩田忠利(編集長) / イラスト ・マップ:石野英夫(元住吉)
取材:文:福田智之(編集室・大森)
|
|
|
|
かつて城南最大の規模を誇った目黒銀座
「中目黒」が本来の目黒であることは、JR目黒駅の所在地が品川区であることからも分かる。目黒の警察署や郵便局も、目黒銀座の近くにあった。目黒銀座は当時の目黒という街のメインストリートであったのである。
昭和2年、東横線が開通するに際して、まだ普通の一本の道にすぎなかった伊勢脇通りが、商店街として祐天寺駅方面から売り出された。そして昭和7年、山手通りまで通じる全長1キロの大商店街、目黒銀座商店街が開店した。
現在約230店、当時はそれ以上の店の数があったという店の並びは壮観で、今でこそ渋谷や自由が丘、武蔵小山に規模や施設で一歩ゆずるが、そのころはもちろん城南最大と呼び声高く、遠く蛇崩(現、世田谷区下馬付近)や油面(現、目黒区中町)さらに大橋方面の先からも、お客さんが絶えなかったというから、その繁盛ぶりはものすごいものだったろう。(★当サイト「とうよこ沿線物語」の「中目黒編」をご覧ください)。
強制疎開と商店位置入れ替え事件
〈目黒銀座通リノ北側ヨリ、東横線の線路マデノ範囲内ニ、強制疎開ヲ命ズ〉。
昭和20年3月、戦局は次第に悪化、このあたりも爆撃を受ける可能性が強くなってきた矢先の命令である。中目黒小学校に通う子供たちは、福島県棚倉町へ学童疎開しているので、残っいる大人たちも思い思いに疎開した。
なぜ、道路の南側は強制疎開(建物取り壊し)しなくてよかったのか…。
早い話、敵機は空から攻撃するとき、目につくものに爆弾を落とすわけであるから,その点線路は格好の目標物になる、しかも強いダメージを与えることができるからだ。それを想定して、あらかじめ燃えるものをなくしておけば、被害は最少でとどめられる。それには道幅のある目黒銀座まで家や店を取り壊しておけばいい。まるで江戸の町火消しである。
長かった戦争も終わって.強制疎開させられ店を取り壊された人たちが戻って来た。この付近は結局爆撃が少なく、若干焼夷弾で燃えたところがある程度。だから元の自分の店の位置も分からない訳ではないのだが、いつまでも帰って来ない人がいるので、半ば勝手に新しい場所に店を建てる人が続出。さらにふさがってしまった人が帰って来て、また新しいところ‥とキリがなく、かくして世にも稀な、商店位置入れ替え事件が起きたのである。
下記イラストマップのそれぞれの下側(北)に白丸(○印)が多いことからも、店の位置を入れ替わった店がいかに多いかがわかるであろう。 (福田智之)
|
|
|

昭和7年10月、山手通りで目黒区発足記念パレード
右手、山手通りの先に東横線のガードが見えます。写真左の木の脇あたりが目黒銀座通りの入り口。
提供:小林朝次郎さん(上目黒2丁目)
|
|
|
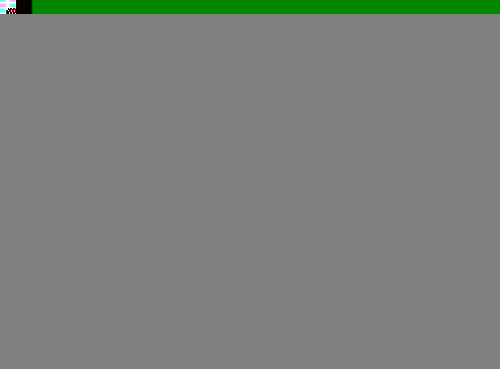
目黒区最大の児童数の中目黒小学校。昭和11年の校舎
昭和10年に児童数1846人、同15年に2297人、区内最大の児童数でした。
提供:秋元竹次郎さん・尾崎次郎さん(上目黒2丁目)
|
|
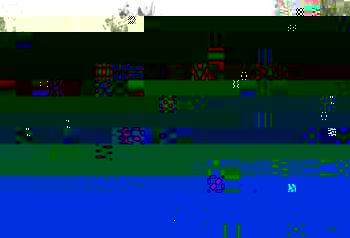
昭和12年新調の神輿で八幡神社のお祭り
この神輿は新調したての総白木造りで、非常に重く、その重量と製作費は都内屈指のお神輿だそうです。
提供:秋元竹次郎さん(上目黒2丁目)
|
|
|
|
|
|
|
 |
「とうよこ沿線」TOPに戻る |
 |
次ページへ |
 |
「目次」に戻る |
|
|
|