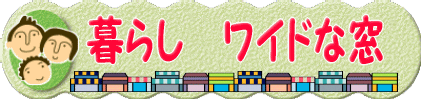 |
| 編集支援:阿部匡宏 |
| 編集:岩田忠利 NO.169 2014.8.17 掲載 |
|
★画像はクリックし拡大してご覧ください。
|
|
|
| |
|
沿線住民参加のコミュニティー誌『とうよこ沿線』の好評連載“復刻版”
掲載記事:平成2年12月15日発行本誌No.52 号名「楡(にれ)」
構成・編集 :岩田忠利(編集長) / イラスト ・マップ:石野英夫(元住吉)
取材:菅間映二(編集室) / 復元:中山市郎(なかや呉服店)
|
|
|
|
駅前から多摩川の土手が見えた
話す人:中山市郎(町並み復元者。なかや呉服店店主)
栃木県から上京し鵜の木で呉服屋を開業したのは、昭和16年10月、独身の27歳のときでした。
目蒲線は1両電車でした。駅のホームは掘立小屋に5〜6人が腰を掛ければいっぱいのベンチがあるだけ、全くの田舎駅でした。
やがて将来を見越して移転してきた人たちが一気に増え、駅前の店数も増えだしました。そのうち、戦争が激しくなり、店主の召集で商売ができず、代替わりする店も目立ちました。
当時は東口より西口のほうが賑やかでした。とは言っても駅売店前の畑には製材所があるだけで、駅前からもわが家からも多摩川の土手が見えました。
お客さんも隣近所も、その人情は今よりずーっと豊かでした。
|
|
|
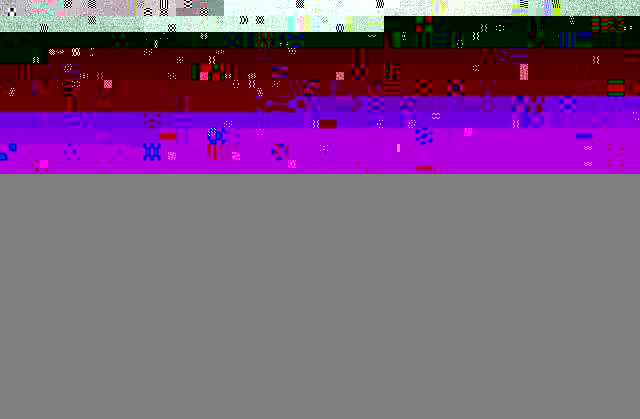
昭和9年冬、雪の鵜の木。蒲田行きの目蒲線1両電車。左手に東京中学(現東京高校)
この雪原の撮影場所と思われる地点を探しましたが、今はどこも住宅が密集し遠望が利きません
提供(3枚とも):東京高校
|
|
|
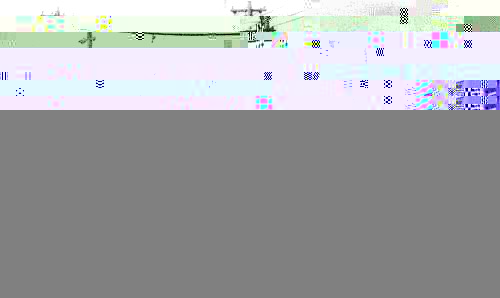
昭和9年((1934)東京高校開校当時の鵜の木駅
畑の中にあった鵜の木駅。同校は前年11月25日に地鎮祭を行い、翌9年の新学期から授業を開始しました。
当時の先生、近藤広さんはこう回顧しています。
「校舎敷地に小屋を建て、神田から毎日交代で教員が詰めて応対しました。なんといっても、周りは一面の畑で家はほとんど見当たらない鵜の木でした。心細いこと限りなく、冬の最中の生徒募集だけに寒さがひとしお身に染みました」
|
|

昭和9年西口駅前からの東京中学通り
鵜の木駅西口から右手に同校校舎を望む。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
「とうよこ沿線」TOPに戻る |
 |
次ページへ |
 |
「目次」に戻る |
|
|
|