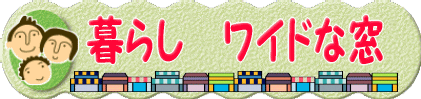 |
| 編集支援:阿部匡宏 |
| 編集:岩田忠利 NO.164 2014.8.16 掲載 |
|
★画像はクリックし拡大してご覧ください。
|
 |
|
昭和3年・20年の菊名町並
|
|
| |
|
沿線住民参加のコミュニティー誌『とうよこ沿線』の好評連載“復刻版”
掲載記事:昭和62年3月10日発行本誌No.37 号名「柚(ゆず)
構成・取材・編集 :岩田忠利(編集長) / イラスト ・マップ:石野英夫(元住吉)
調査・復元:本田芳治(編集室・篠原北1丁目) 協力:青木宗次 / 金子清太郎
|
|
|
「菊名」という地域
東急線89駅のうち花名をつけた駅名は5つある。その一つが菊名・・・。
現在の菊名・篠原・錦が丘などの地域は、明治22年(1889)の市町村制施行で8か村が合併してできた橘樹郡大綱村の一部である。
大正元年(1912)大綱村の戸数は655戸、うち農家は579戸で全体の約9割弱を占める純農村地帯であった。
明治41年(1908)9月横浜線が営業を開始し、大正15年(1926)2月には東横線が開通、菊名駅ができた。その年12月横浜線にも菊名駅が設置された。
菊名地区の都市化は、こうした電鉄会社の沿線住宅開発に負うところが大きい。昭和2年の篠原町が6年間で3・03倍、隣の大豆戸町が1・13倍にしかなっていないように菊名駅設置による人口増加傾向がはっきり表れている。
映画館のない街、世俗的な娯楽施設の少ない街、これが菊名の特徴でもあった。住民が町内の道路に桜335本、楓100本を植えて町名を錦が丘としたような町である。
そのような街の中心地、菊名駅付近の約60年と40年前の町並を再現してみた。現在と比較し、その発展の足跡を考え、昔を偲ぶよすがとなれば、と思う。
(岩田忠利)
|
|
|

昭和44年4月、菊名駅東口旧駅舎と交番
この駅舎を懐かしく感じられる方も多いでしょう。当時の駅入り口は東口に1か所だけで西口にはありませんでした。篠原北、錦が丘、大豆戸など西口の住人は、北側の踏切をくぐって東口に回らねばならず、朝の忙しいときはイライラしたものです。
この交番は昭和24年8月ここに開設され、昭和44年駅舎改築工事で郵便局の隣に移転しました。
提供:本田芳治さん(篠原北)
|
|
|
|
|
昭和3年 菊名駅周辺
|
|
|
★画像をクリックし拡大してご覧ください。
白抜きの個所は取材時(昭和62年)に同じ場所で現存、灰色のアミ掛けは転業または移転し現存しています。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
「とうよこ沿線」TOPに戻る |
 |
次ページへ |
 |
「目次」に戻る |
|
|
|