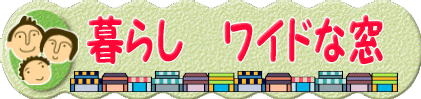 |
| 編集支援:阿部匡宏 |
| 編集:岩田忠利 NO.160 2014.8.14 掲載 |
|
★画像はクリックし拡大してご覧ください。
|
 |
|
終戦直後の祐天寺駅前
|
|
| |
沿線住民参加のコミュニティー誌『とうよこ沿線』の好評連載“復刻版”
掲載記事:昭和62年7月20日発行本誌No.31 号名「樅」
企画・取材・文・編集 :岩田忠利(編集長) / イラスト ・マップ:石野英夫(元住吉) /取材 :本田芳治・天野利弥
復元協力:小杉栄(小杉彦太郎商店) / 富永文子(日本堂) / 長江秀子(来々軒)
|
|
“昔”が残る祐天寺
むかし目黒の名物は、サンマではなくてタケノコだといわれています。このあたりは竹林が多く、そこを切り開いで昭和2年目黒を背骨のように貫いた東横線が渋谷〜丸子多摩川間に開通しました。特産タケノコが鉄道に場所を明け渡した格好になったわけです。
ここには駅名にもなっている明顕山祐天寺が近くにあります。芝の増上寺の住職を高齢のため退いた祐天上人が、享保3年(1718年)83歳で遷化されその徳に報いるために廟所として建立された名刹刺です。
農村地帯であったこの地域が住宅地として脚光を浴びてきたのは震災後、都心の宅地の値上がりが激しく、この辺まで都市化の波が押し寄せてきたからです。目黒村と碑衾村が昭和2年に町制を布き、同7年10月には周辺の5郡82か町村が東京市に編入したのです。このとき目黒町と碑衾町の地域を目黒区としました。くしくもその年、この地域は宅地面積が耕作面積を上回ったといわれます。
東横線開通当時の回想録にはこんなことが載っています。
「駅前には銀行も洋菓子店もなく、通りは砂利道で狭かった。四角な白地の“水”と赤く染め出した旗がガラス立ての暖簾の上でたなびき、通りを牛や馬が荷車をひき、周りは殆ど畑であった」。
祐天寺地区は、幸い戦災で大きな被害をうけなかった。そのせいか、昔の名残がまだ随所に見られます。今どき珍しい看板の店、東横線開通時そのままをしのばせる建物、駅を少し離れると鬱蒼とした大木に囲まれた旧家など、まだ“昔”がみつけられ、ほっとします。
|
|
|
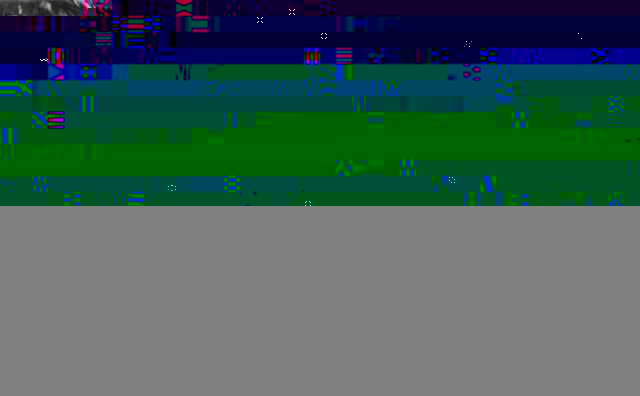
昭和30年代初め。ゴミ収集は大八車。お寺・祐天寺の横道から駒沢通りを望む
提供(3枚):目黒区役所広報課
|
|
|
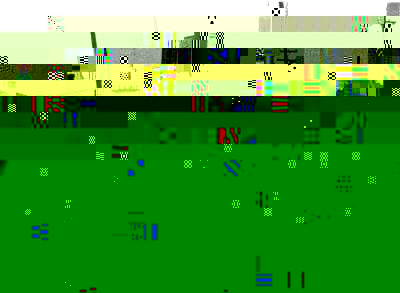
昭和27年祐天寺駅前の歳末風景
|
|
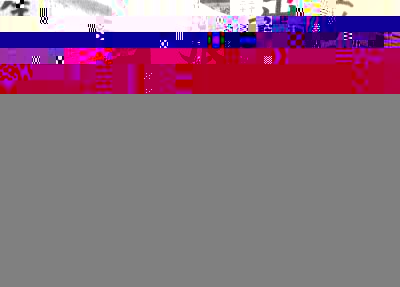
昭和27年歳末、写真左のテント中の相談所
|
|
|
|
終戦直後の祐天寺駅前
|
|
★店名の白抜き文字は編集時(昭和62年)に現存、営業中の店。灰色のアミがかかっている店は転業または移転し現存する店。
|
|
|
|
|
 |
「とうよこ沿線」TOPに戻る |
 |
次ページへ |
 |
「目次」に戻る |
|
|
|