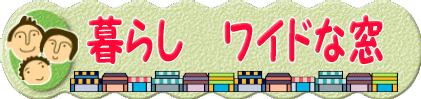 |
| 編集支援:阿部匡宏 |
| 編集:岩田忠利 NO.159 2014.8.13 掲載 |
|
★画像はクリックし拡大してご覧ください。
|
 |
|
伊勢佐木町と馬車道の町並
|
|
| |
沿線住民参加のコミュニティー誌『とうよこ沿線』の好評連載“復刻版”
掲載記事:昭和60年12月1日発行本誌No.31 号名「樅」
企画・文・編集 :岩田忠利(編集長) イラスト ・マップ:石野英夫(元住吉)
復元協力:伊勢佐木町一・二丁目商和会 / 子安精司(万国橋ギャラリー) / 今井信夫(イブ・エバ・イマイ)
|
|
伊勢佐木町の歩行者天国は「世界初」、
馬車道の車歩道分離は「日本初」
伊勢佐木町商店街の最盛期は、昭和3年から8年頃でした。当時は繁華街といえばイセザキだけ。人びとが「ヨコハマに行こう!」と誘えば、ここ伊勢佐木町の街のこと。伊勢佐木町という言葉は使わなかったほど、県内、市内を代表する街だったのです。
伊勢佐木町通りと馬車道は、吉田橋(通称鉄<かね>の橋)をはさんで向かい合っています。現在、このあたりの最寄り駅はJR関内駅ですが、この“関内” という地名は吉田橋に明治4年11月までここに置かれていた関門に由来します。ここから海岸寄りは外国人居留地で、関門の内側という意味から“関内”と呼ばれました。すなわち、馬車道側が関内、伊勢佐木町側は“関外”であるわけ。
双方とも、文明開化の地だけあって興味深い町ですが、ふだんあまり語られることのない面についてふれておきましょう。
まず、伊勢佐木町通りの明治末期からの歩行者天国は世界中で最も早く、もちろん世界初です。また、馬車道は、日本で最初に歩道と車道を区別した道。これは東京の銀座よりも早く、明治初頭、日本で最初のことでした。
|
|
|
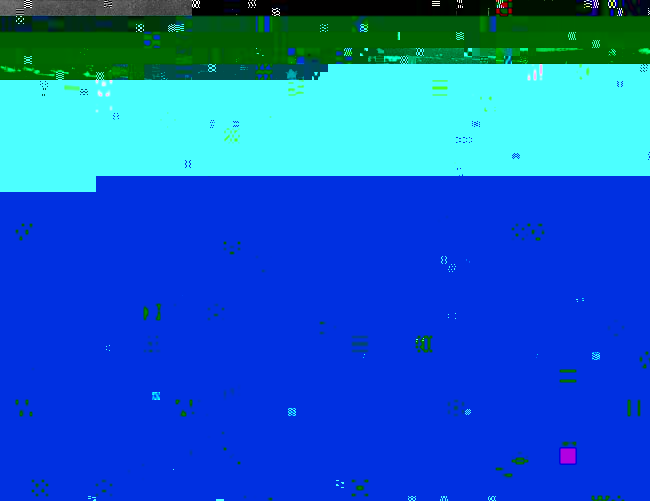
昭和39年(1964)伊勢佐木町上空から横浜埠頭を望む
提供:伊勢佐木一・ニ丁目商和会 |
|
|
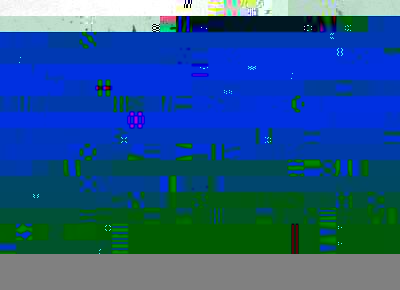
明治末期の伊勢佐木町通り(野沢屋付近)
左上の“入歯”の看板は歯科医です。
提供:伊勢佐木一・ニ丁目商和会
|
|
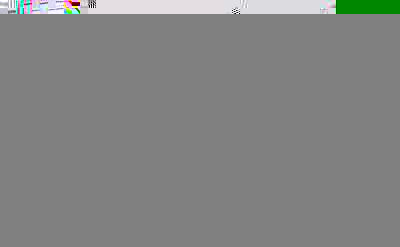
大正15年関東大震災から復興した写真左の場所
提供:伊勢佐木一・ニ丁目商和会
|
|
|
|
昭和10年の伊勢佐木町一・二丁目町並
|
|
★下記の上部の通り左端が下部の通りの右端に繋がります。
店名の白抜き文字は編集時(昭和60年)に現存、営業中の店。灰色のアミがかかっている店は移転し現存する店です。
|
|
|
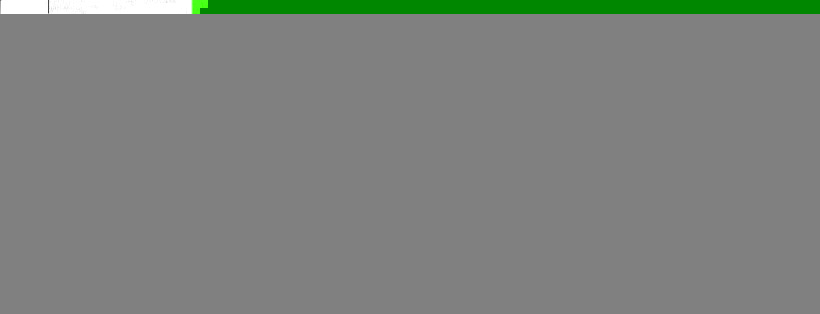
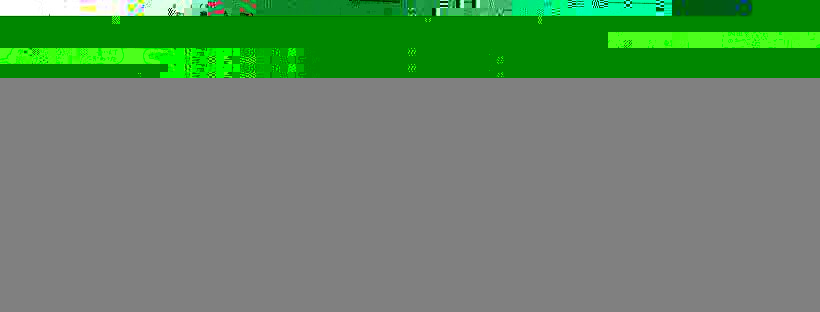
常設の映画館2館、横浜唯一の寄席「花月亭」。横浜を代表する百貨店の野沢屋と寿百貨店。本なら有隣堂や弘集堂書店。スイート党には不二家や森永ストア、羊羹や甘栗の店なども・・・。ご婦人方なら通りの両側の店をウインドウショッピングするだけでも一日を充分堪能できました。
老舗港屋時計宝石舗の主人・渡辺政次さんは最盛期の商店街の活況ぶりをこう話しています。
「一日の来街者は15万人から20万人。とにかく人混みで10メートル先が見えないほど……。私の店では、戸板の上で夏は帽子、冬は足袋などを売りましたが、子供の帽子が1500個、大人のカンカン帽が2000個ほど毎日売れました。冬の足袋は1ケースで2足が5000ケースくらい飛ぶように……。とにかく売れに売れて、近くの倉庫ヘリヤカーで何度も取りに行きました。まあ、あの当時が、わが世の春でしたねぇ」
|
|
|
|
|
|

「馬車道」というと、尾上町から本町通りまでだとお思いの方が多いのではないでしょうか。本当は、吉田橋から万国橋までを指しているのです。上のイラストマップの端から端までが馬車道です。
この町並には、いかにも“みなと横浜”らしい場所が多く見られます。たとえば、熊本屋・紀州屋などの旅館はいわゆる「移民宿」で、中南米などへ移民する人びとが、船出の前夜に泊まった宿。また停泊する船舶に食糧や船具などの資材を商う回漕店や「シップチャンドラ」も目立ちます。万国橋の先は新港埠頭で、まさに海外への玄関口だったのです。
本町通りに面して“空き家”がありますが、これは単なる「人の住んでいない家」ではなく、ビルの建て替えなどの際の仮事務所・仮店舗として使われていたもの。また、横浜正金銀行・第一銀行・不動銀行・安田銀行・川崎銀行・渡辺銀行と銀行が6行も集中、当時からビジネス街であったことがうかがえます。
|
|
|
|
 |
「とうよこ沿線」TOPに戻る |
 |
次ページへ |
 |
「目次」に戻る |
|
|
|