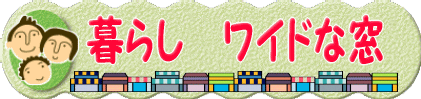 |
| �ҏW�x���F�������G�@/�@���S�F�z�����q |
| �@�@�@�ҏW�F��c�����@�@�@�@�m�n.156�@2014.8.10�@�f�ځ@ |
|
���摜�̓N���b�N���g�債�Ă������������B
|
|
|
| �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ |
�@�@�����Z���Q���̃R�~���j�e�B�[���w�Ƃ��悱�����x�̍D�]�A�ځg�����Łh
�@�@�@�f�ڋL���F���a62�N�U���P�����s�{���m��.38�@�����u��v
�@�@�@���M�E�B�e �F��F�����i�S�V���E��w���j�@�@�n�} �F�ɓޗ��v�i���ؒ��E�c�̐E���j
|
|
|
�@���c�J�E�ڍ��E�i��c�c���ł��������Z��n�̑㖼���ƂȂ��Ă��邱���̒n����A���a�ȑO�́A�x�O�̔_���ɉ߂��Ȃ������B
�@���̎���ɂ͉͐�E�p�������炩�̌`�Ŕ_�Ƃ������Ă����킯�ł��邪�A�����͍��A�s�s���̒��ʼn�����A�����͖��߂��ėΓ��ƂȂ���̖��߂��ʂ����Ă���B
�@�i��p�������̈�ł��邪�A���̗���͂��ׂĖ��߂��A���H�ƂȂ�A���Ղ��c���Ă��Ȃ����Ƃ���A���Ă̑��݂�����قƂ�ǒm���Ă��Ȃ��B
|
|
|
|
|
�@�@�@�i��p���̗��j�c�c�ʐ�㐅����_�Ɨp����
�@ ���������̂��ׂĂ̗p���H�́A��тōő�͐삽�鑽��������Ƃ��Ă���B
�@��P�̗p���i�m�n.141�Ōf�ځj�A�Z���p���i�m�n.142�j�A�ʐ�㐅�A�����ċʐ�㐅���番�����ꂽ�O�c�p���i�m�n.154�j�A���l�ɕ������ꂽ�ڍ����i�m�n.140�j�̏㗬���̉G�R�p���Ɩk��p����������ɂ�����B
�@�i��p�����܂��A�ʐ�㐅��蕪�����ꂽ���̂ł���A���Ƃ��Ƃ�1664�N�i����4�N�A����S�㏫�R�ƍj�̎����j�i���ˉz�̍א�z����E�����~�i���ˉz�����j����r�Ɉ������邽�߂Ɍ@��ꂽ���I���H�ł������B�@�����ˉz�㐅�ƌĂꂽ���̂�����ł��邪�A�قړ������A�א�Ƃ͔����̉����~�ɋʐ�㐅�������l�̐�p�㐅�i��̎O�c�p���j�����L���Ă����B����́A�Ƃ���Ȃ����������̍א�Ƃ̗͂����̂ł���B
�@�ˉz�㐅�́A���m�ɂ͋ʐ�㐅�i�������E��t�߁j�����������Ă������{���i���̂��Ă̏㗬���j����̕����ł������B
�@���̏㐅�́A�ێ��ɗv���锜��Ȍo��̂��߂ɋ͂��Q�N�Ŕp�~����Ă��܂������A1667�N�̈�_���̊肢�����{�ɕ����Ƃǂ����āA�V���ɕi��p���Ɩ���ς��A�_�Ɨp���Ƃ��čĐ����邱�ƂɂȂ����B
�@���̌o�܂͍א�㐅���O�c�p���̗�ƍ������Ă���B
|

�����{���i�E���H�j����̕����_�Ɏc�鐅�H�Ձi���j
|
|
|

�ʐ�㐅�E�������ꉡ�̗p���搅�_�B�p���p�~�������i�E�j���������̂܂c��
|
|
|
�@�@�@���H�c�c�������`��䒬���ʁ@30�`�@
�@�i��p���a����A�O�L���{���͔p�~�B����ɂ��A�ʐ�㐅����̎搅�_�Ƌ��ˉz�㐅�����_�̊Ԃ̐��H�ɂ��ẮA�i��p���������Ƃ��ē]�p����A���̂܂ܑ��������̂ł���B
�@�i��p���̗��H�ɂ��Ă͏�̒n�}�̂悤�ɂȂ��Ă����B
�@����������O��E��ΉG�R�E��ΑD���E���V���ցA����n�i����246�����j�ցA����������V�����E����ԂցA�����Ċw�|��w�E�������R���o�āi�s���⏕26�����j�ˉz�����ւƑ������[�g������ł���B�ˉz�ł͗p���͂Q���ɕ�����A����͑��Ŗڍ���ցA�����͑�䒬���o�ĎL�F�E�������t�߂ŊC�ւƗ����Ă����Ƃ����B
|
|

�s�s��ʂ̑哮���A��V�����i���j�B�������ɂ��Ă̕i��p�����c�c
|
|
|
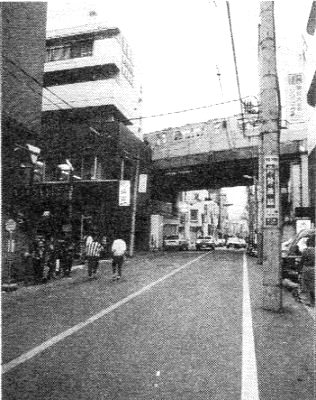
�������w�|��w�w�߂��̓s���⏕26�����B�S�V���w���́i�E�j�����i��p���̐��H������
|
|
|
|
|
|
�@�@�@���͂Ȃ�����c35�N�O�̍Ŋ�
�@���m��̋K�͂Ƃ���ꂽ�g��ԁh��p���č��������Ђ����ԋƂ��c��ł������c�J����̍��݉Ɠ���E���݈�F����i57�E������ЎВ��j�́A�i��p���̐̂��������B
�@�u���a10�N�O��̗p���͌��\���ꂢ�ŁA�z�^��������قǂł����B�t�i���G�r�A�n���ȂǁA�q���̍��悭�߂������̂ł��B���a15�`16�N�����肩�版�݂Ɍ����Z������A���͉���A���a27�N�ɂ͂��ɓs������W�܂�S�~�Ŗ��߂��Ă��Ă��܂����̂ł��v�B
�@�p���̉������Â�����̂͋͂��ɋʐ�㐅����̎搅��i�������j�A�����{������̕����a�i�O��s�V��j�A���ԋ��i���c�J����j�╽�ˋ��i�i���j���̃o�X�▼�Ɏc��݂̂ł���B
�@�Â��͕��Ɨp���E�_�Ɨp���Ƃ��Ė𗧂Ă��A���̗����E�R���ɂ���ĉG�R�p���␅����i�ڍ���̏㗬���j�A�ې�A�J���i���X�͌k�J�㗬���A�m�n.147�Q�Ɓj�A�֕���Ɨ�������i�ڍ���x���j���̐����̈ꕔ�ƂȂ�ȂǑ����ʂɉe�����y�ڂ��Ă���������A���͂����Y�ꋎ���Ă䂭�݂̂ł���B
|
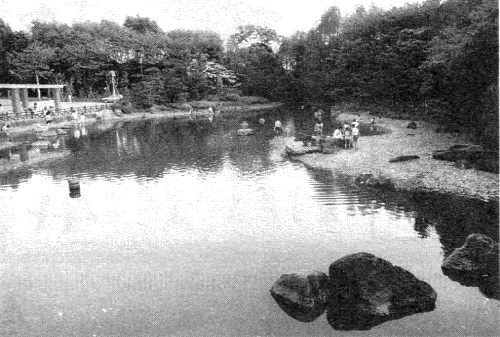
�ˉz�㐅����̏I�_�i�א�Ƃ��������~�j�A���͌ˉz�����Ɂc
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
�u�Ƃ��悱�����v�s�n�o�ɖ߂� |
 |
���� |
 |
�u�ڎ��v�ɖ߂� |
|
|
|