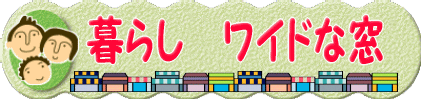 |
| �@�ҏW�x���F�������G�@/�@���S�F�z�����q |
| �ҏW�F��c�����@�@�@�@�@�@�m�n.142�@2014.8.02�@�f�ځ@ |
|
���摜�̓N���b�N���g�債�Ă������������B
|
 |
|
 |
�@�@�@�Z���p���� |
|
| �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ |
�@�����Z���Q���̃R�~���j�e�B�[���w�Ƃ��悱�����x�̍D�]�A�ځg�����Łh
�@�@�@�f�ڋL���F���a59�N�R���P�����s�{���m��.21�@�����u�w�v
�@�@�@���M�E�B�e �F��F�����i�S�V���E��w���j�@�@�G�F�R�e���q�i���@���E���w���j�@
�@�@�@�@�@�������W�F����c�v�E���@��
|
|
|
�@�����A�_�ސ�̓s�������Ȃ�������B���������ōł��傫�ȗ���ŁA�]�ˎ���̐l�X�͂��̐��������ĕ邵�ɖ𗧂Ă��B
�@���p���Ƃ��Ă͋ʐ�㐅���L�������A���������ɂ́u�Z���p���v�Ɓu��P�̗p���v�̂Q�{�̔_�Ɨp�����A�����E���̗��݂Ɉ����ꂽ�B
�@��P�̗p���ɂ��Ă͑O���m�n.141����ǂ�ł��������Ƃ��āA�Z���p���̊T���ɐG��Ă������Ƃɂ��傤�B
�@�Z���p���́A16���I�ɏ����v�����点���Ƃ��납��A�ʖ��u�����v�x�v�܂��u�ێq��v�Ƃ��Ăꂽ�B
�@���̉͐�̗�ɂ��ꂸ�A���ł͗p���Ƃ��Ă̋@�\�������A�����̂͂����Ƃ��Ă̑��݈Ӌ`�����c����Ă��Ȃ��B
|
|
|
|
|
�@�@�@����������
�@�{���T���̕\���ɂ��o�ꂵ�������������B������͎R�S�̂������ɂȂ��Ă���Ƃ��������B�쒹�̂���������Ȃ���A������Ƃ����R�������ł���B
�@����ɓo��A��Ԑ_�ЁE���j�Ղ̋T�b�R�Õ��E�^����Ȃǂ�����B�o�h�~���g�����x�̃X�|�[�c�Ȃ�o�b�`���I
�@�t�Ȃ���A����������~�낹�A�Ƒ��A��ł��y���߂�A�s��̃I�A�V�X�Ƃ����悤�B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i�����쉀�w���ԁE�k���S���j
|
�@�@�@�@�����v�Ɨp��
�@�P�U���I���A����ƍN���]�˂ɓ��{�B���{�̗͂�{�����߂ɁA�c���̐����ɗ͂���ꂽ�B�����ŗp����s�ɔC�����ꂽ�̂������v�E�E�E�����A�Z���p���Ɠ�P�̗p���̍єz�ɂ��������B
�@����1597�N�i�c�����N�j�A�ȗ�15�N�ԁA���p�������݂Ɍ@���āA��H���͏I�����B�̖����悭�������B������ɂ͎��n������I�ɑ��������������B�ȗ��A�����v�̖��́A�u�����v�x�v�Ƃ��Č㐢�Ɏc���Ă���B
|
|
|
 |
�u�Ƃ��悱�����v�s�n�o�ɖ߂� |
 |
���y�[�W�� |
 |
�u�ڎ��v�ɖ߂� |
|
|
|