「北極の白熊を見たい」
白瀬中尉は秋田の出身である。少年時代は寺子屋へ通っていたが、「北極には白熊がいる」という話を聞き、どうしてもそれを見にゆきたいと思うようになった。こういう単純な願望も、池田高校の蔦監督(徳島県の山間の県立高校を甲子園で連続優勝に導いた名物監督)と同様、執念ともなると次々に奇跡を生み、アムンゼンやスコットと競って南極を犬ぞりで踏破し、「大和雪原」という鋼製銘板を埋めて帰港するという快挙をなし遂げたのであった。
寺子屋の塾長に、
「自分は北極へ白熊の探険に行きたいのだが、どうしたら行けるか?」
と尋ねたら、その塾長が変わった人で、
「5戒を守れば必ず行ける」
と断言したという。
5戒というのは、1.寒中でも火に当たらない 2.湯を呑まない 3.板の間か畳の上に直接寝る 4.足袋をはかない 5.手袋を使わない
以上の5か条であった。
塾長は、このくらいに言っておけばあきらめるだろうと思っていたかもしれない。しかし、白瀬少年はその5戒を実行し始めた。塾長の困った顔が想像できる。
5戒が役立った千島探検
その後も5戒を守った白瀬青年は、軍に入り、郡司大尉の千島探険隊に参加することができた。
郡司探検隊は、隅田川からカッター3隻で千島列島に向かった。貧弱な船だったので、三陸沖で1隻が沈没してしまった。やっとのことで千島列島最北の島、シュムシュ島(占守島)へ到着。越冬することになった。
極北の地での越冬経験が皆無の彼らにとって、その苦難は想像を絶するものであった。たとえば、越冬小屋の入口の戸ひとつとっても、外開きになっていたため積雪で開くことができなくなり、完全に閉じ込められてしまった。そこでは「五戒」の訓練が大いに役立った。
訓練が未熟な隊員は、折からの栄養失調のため次々と死んだ。ところが、戸が開かないため、春まで死体とともに生活するという惨鼻さであった。今は白熊どころの騒ぎではなく、生か死かの竿頭に立っていたのである。しかし白瀬は屈しなかった。
この郡司探検隊は、たくさんの極冠体験を成果に、2年間で解散になった。
南極に目標を変更
その後、北海道庁に勤務、そして日露戦争に応召するうちに、アメリカのペアリー大佐が飛行機で北極一番乗りをしてしまった。二番煎じが嫌いな豪気の白瀬は、探険の目標を急きょ南極に変更した。
これも急がないと外国勢に負けると考えた彼は、積極的に活動を開始した。
|
白瀬の良き理解者であった児玉大将の紹介で、乃木将軍さらには寺内陸相に会った結果、日露戦争で余った食糧、テント、長靴などの防寒器材を払い下げてくれた。海軍では、木造のタラ釣り船(204トン)を5万円で提供してくれた。(この船は探険後同額で引取ってくれる約束)。また、朝日新聞の後援も決まり、全国キャンペーンで8万円集めてくれた。
後援会長には大隈重信がなり、船には東郷平八郎が「開南丸」と命名し、乗組員24名も集まった。明治42年12月、大隈重信、乃木希典らの見送りを受け、「開南丸」は芝浦沖を華華しく出帆した。
|
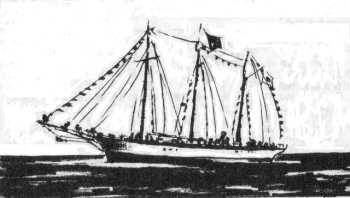
「開南丸」はわずか204トンのタラ釣り船だった |
|
猛暑・造反・高い氷壁
燃料を節約するため帆走を原則とし、船のスピードは遅く、赤道直下では、その暑いこと……。一同、寒さばかり気にしていたため、この猛烈な暑気にノックアウトされてしまった。
24頭連れてきた樺太犬は次々に死亡し、赤道を越えたときには1匹しか残らなかった。これで極点への探険は不可能となったが、せっかくここまで来たのだからということで、白瀬は南極へ向けて船を進ませた。
|
半数の船員たちは、航海に慣れていたのでよかったが、岡田事務長以下の応募組は、猛暑と船酔いにすっかり嫌気がさし、「犬の無い探険は無意味だから、船を引き返せ」と言い出した。
やがて岡田ら一派は、「この上は白瀬を海に放り込んで帰航しよう」と機をうかがい出したので、白瀬は毎夜短刀を抱えて眠ったという。
南極へ近づくと、予想を越える高い氷壁であることを知った。白瀬は上陸を断念してオーストラリアまで引き返し、再挑戦のため野村船長を日本に派遣した。また岡田事務長は解雇した。
|

白瀬 矗(のぶ)
1861(文久元年)〜1946(昭和21年)
|
|
|
極点をめざして
今度は25頭の樺太犬が無事到着した。その年は、イギリスのスコット、ノルウェーのアムンゼンらと競争になった。彼らは何年もかけ、国をあげて準備をしてきた強豪である。
南極に上陸した白瀬は、5人の突撃隊でただちに極点をめざし、明治44年1月19日午前3時、勇躍出発した。一行は、1日40キロ余のスピードで前進し、前後8日、ついに南緯80度5分の地点に達した。
これが突撃探険の限界であった。白瀬はその地点に国旗を立て、探険隊局名簿を銅箱に密閉して埋めた。
このあと南極の天候が悪化し、イギリスのスコット隊は全員死亡した。
白瀬隊は貧弱な装備をものともせず、初志をひるがえさず、苦闘25年、徒手空拳、学術的大探険を敢行、しかも1名の事故者もなく帰還しえたことは立派であった。
|
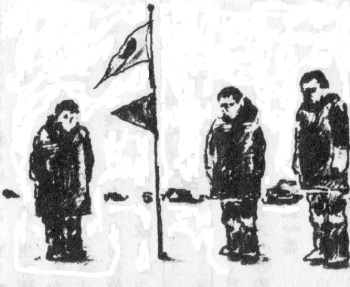
ついに南極の極点に日章旗をたてた白瀬隊
|
|
|
南極に取り残された樺太犬
目下「南極物語」という映画が大ヒットしている。南極に取り残された樺太犬15頭のうち、翌昭和34年1月14日、タロ、ジロ2頭の犬が生き残っていた事実を、物語として扱った内容であるが、昔の南極探険は凄惨なものであった。
最初に極点を制覇したアムンゼンは、4人の隊員と4台の犬ぞりで出発し、積荷の節約のため、各ソリを引く13頭までの犬を定められた計画(地点)で次々に殺し、食糧にして進んだのであった。
白瀬中尉の場合も、食糧の関係上、十数頭の樺太犬を雪原に残さざるを得なかったという。彼は亡くなるまで、ひとたび話が犬のことになると、ハラハラと落涙し、言葉が途切れたと、神部老は語った。
|
新鋭砕氷船「しらせ」
砕氷船「宗谷」(現在東京湾の船の科学館横に保存)の後を継いだ「ふじ」も、18回の南極輸送の任を果たし、新鋭砕氷船「しらせ」にバトンタッチすることになっている。本年11月に就航する「しらせ」は1万2000トン。わずか204トンの「開南丸」にくらべ、実に60倍の大きさである。
晩年、あまり報いられることもなく、85歳の天寿を全うし、昭和21年9月4日逝去された「白瀬矗(のぶ)」、新鋭船「しらせ」を泉下で知り、どんなに喜んでいることであろう。
「しらせ」は白瀬の志を乗せて、これから何十回も南極探険に行くことであろう。白瀬矗よ、以って冥せられよ。
|