|
窓外の風景
綱島を出てから大倉山までの風景は日吉から綱島までとよく似ている。まず駅を出ると電車はすぐ川を渡る。川というのは、そのあたりの最低海抜地点である。そして、しばらく平地が続きやがて小高い丘を切通して駅のホームになる。
綱島駅の場合、見上げる丘上には大きな綱島公園があり、大倉山の場合には、やはり丘上に大倉精神文化研究所があり、その周囲に有名な梅林がある。
だから窓外の景色をちらっと見ただけでは.電車が日吉〜綱島間にあるのか、綱島〜大倉山間にあるのか、ちょっと判断に迷う。
大倉山駅前付近
大倉山の駅は目下大改修中である。綱島と同様、改札前のバス通りは狭く、歩道もよく整備されていないので、命がけで歩く。
バス通りを綱島街道に向かってゆくと、すぐ新幹線のガード下に出る。新幹線の線路幅は大して広くない。バス通りに面したそのガード下にはソバ屋とクリーニング屋が相向かいで店を出している。国鉄も、こんな狭い空間をまめに貸している姿がほほえましい。
ま、大赤字には焼石に水だが、将棋対局のように万事に細かく気を遣わなければ、負局になることは必定である。
綱島街道は車輌の通行が激しい。右手に港北区役所の総合庁舎が中世の城廓のように雨に濡れていた。
駅のホームの西側の坂道を登ってゆくと、急に眺望がひらける。風にゆらぐススキの原の突端にゆくと、新幹線が往き来している。大倉山駅の少し菊名寄りを新幹線は東横線を横断して、新横浜駅へ向かっている。
眼下にたくさんのマンションが林立しているところも綱島そっくり。目の前をススキの種が風に乗って左から右へゆっくり浮いてゆく。左を見たら数本のススキの穂が揺れていた。
|
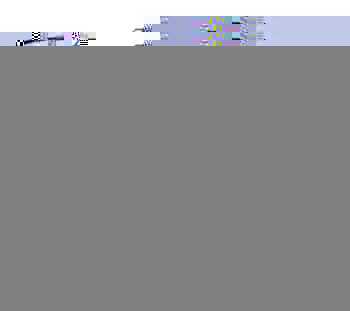
駅東口の新幹線ガード下のあたり |
|
大倉邦彦の遺産、大倉精神文化研究所
この丘から、また坂道に戻り登ってゆくと、大きな石に「大倉精神文化研究所」と刻んである。石段を登ると、そこにいやに太い門柱が左右にあり、大きな鉄鎖。そこから長い林道をゆくと、背の高いローマの宮殿のような白亜の建物に突き当たる。コンクリートは所々はがれ、白亜はうす汚れ、幽鬼の住処(すみか)のようである。
5人で庭の草刈をしていた。主任に尋ねたら、
「私らは川崎市役所の者ですが、横浜市に頼まれて草刈りをしているので、何も知りません。この一帯は横浜市が買いあげたらしいですよ」
日が沈みかけると、周囲が急にほの暗くなってきた。見ると、この廃屋にただ一か所、暗い灯が見えた。人の気配はそこだけだった。
この不思議な建物を建てた人物は、大倉邦彦。かれは若い頃中国に渡り、全中国を踏破したが、その頃の中国人の非文化的生活にショックを受け、これに対する同情と高い理想を描き、日本に帰ってきた。
ところが、その頃の日本はマルキシズムの全盛期で、人々の哲学も経綸(けいりん)も忘れ果てた姿をみて憤慨したのだった。ときに40歳を過ぎていた。かれは東大に席をおき、各学部の講義内容を比較検討し、「マルキシズムはいかに進歩的なことを言おうとも、その方法ドクトリン自体は、明らかに封建独裁であり、これではダメだ」と悟った。
大正末期から昭和にかけて、私財(当時の金で数百万円)を投じて全国から優秀な学者を招き、昭和7年財団法人大倉精神文化研究所を建てた。本誌第2号15ページに石丸裕子さんが詳しく書いておられる。
それによると、この不思議な建物は長野宇治平の設計、竹中工務店の施工であるという。
戦前には30人近くの研究員がいたが、戦時中は戦意高揚の練成道場となったり、海軍気象部に徴用されたり、戦後は国会図書館の支部になったり、平凡社の創立者・平井弥三郎が1000万円を寄付して研究所を再開した。だが、次第に研究機能が衰退してしまったという。
しかしタゴール文庫など約10万冊の貴重な蔵書が現有しているというから横浜市の善処を要望したい。
この研究所の裏に名高い大倉山梅園がある。梅園全景が見渡せる高台に、東横神社の社務所があり、梅園の管理をしている。小学生が2人、トランシーバーと黄色のパチンコを持って坂を登ってきた。近くにこういう公園のある所に住宅のある子供たちだが、この辺は住宅地としては一等地、誰でも住めるような訳にはいかないようだ。
|