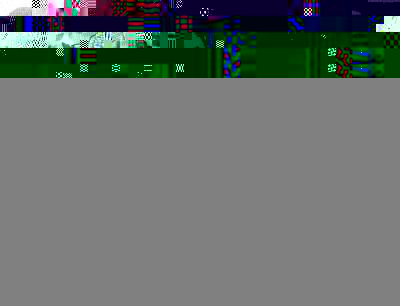
本誌「とうよこ沿線」創刊号で「井上正夫碑が駐車場に」と題し2ページの誌面に掲載
この碑は港北区の名勝図鑑にも載っていて、小中学生の遠足や一般観光客の場。周囲にはヒバの木が植えられ、碑を囲むように4,5本の樹木があり、春は梅の花、秋は赤い実の柿が生って風情を添え、碑の周囲に御影石の腰掛がある市民憩いの場所だった。ところが、本誌掲載の半年前、大型クレーンやブルドーザーで整地、有料駐車となり、石碑は片隅に移設された。
この記事に「文化財の軽視」と、こちらが驚くほどの反響の電話や文書が寄せられた。なかでも私が大事にしている手紙が初代水谷八重子さんの令嬢・2代目の水谷八重子さんと劇作家・北条秀司さん、マネジャーだった蜂野豊夫さんからの礼状です。岩田忠利
|
|
「最後の湯河原行きのときでした。夕方、私の家にきて、垣根から顔だけ出した先生が「ヤアー」といわれたので、母はオバケかと思ったそうです。髪がやけに白く見えたのだそうですね。
先生はシェパード犬のフミちゃんを舞台に出したりして、とてもかわいがりました。フミちゃん亡きあとは、雑犬のタローをいつも散歩に連れて行き、孫のようにしていたのです。
先生の死後、タローは動物のカンで知ったのでしょうか、まったく元気がなくなってしまったのです。見かねた私がタロ一に「先生は死んでしまったのよ」というと、タローの目に白く光る涙がこぼれるのを見ました。それから1週間、タローは行方不明になってしまったのです。
日吉の碑は、伊藤嘉朔(きさく)先生が設計した立派なもの。それがいま、当時の屋敷の面影もなく、駐車場の片隅に追いやられてしまって、先生に申し訳ないような気がしてなりません。
この麗人は、師井上正夫のアルバムを前に淋しそうに目を伏せるのだった。
|