明治~大正、小杉十字路辺
明治23年、第1回帝国議会選挙のときには、板垣退助が、選挙演説のため小杉の泉沢寺へきた。明治34年には中原小学校がすでに完成。明治36年安藤家は郵便局をはじめた。大正2年、溝の口~川崎間の府中街道に乗り合い馬車が走り、小杉十字路には停留場ができ、賑わった。
大正6年、小杉村に初めて電燈がともる。この時、電気は農作物に悪い影響があるというので、猛反対する者もあったが、子供たちはランプのホヤ掃除という、一番いやな仕事から開放されて大喜びだったという。一戸当たり、5燭光1燈と決められていたが、その明るさには、みな驚いた。でも、電気代が滞ると、すぐ消されてしまったという。
大正9年、河口から久地までの多摩川堤防の大工事が始まり、部落ごと移転しなければならない地区もあり、大変な騒ぎとなった。 |
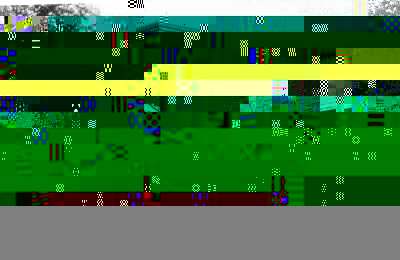
昭和6年ころ中原街道面の小杉十字路辺にあった郵便局
街道筋に茅葺き屋根が多いなか、トタン屋根でベランダ付きのモダンな郵便局は、ひときわ目立った
提供:安藤豊作さん(小杉町) |
|