地名に魅せられ集まる会社や人間
自由が丘という地名は昭和6年、自由教育主義の旗印を掲げて、手塚岸衛氏が自由が丘学園を富嶽のよく見える高台に創立したことが原因となった。
当時、武蔵境に舞踊研究所を持っていた石井漠は、一度この地を見るや、雄大な富嶽を朝夕眺められるうえ、自由が丘の名前が気に入った。昭和3年に、東横線が開通するや、この高台に石井漠舞踊研究所を設立した。その後は、自由の名が気に入ってか、芸能人や画家などの芸術家やインテリが集まってきた。
漠は、この地で、150曲にのぼる創作舞踊を書き、崔承熺、谷桃子、石井ミドリ、法村康之、巴由起子、大野宏史、和井内恭子などの俊秀を養成した。
始め、駅名は九品仏といっていたが、昭和4年に大井町線が開通すると、隣の九品仏の住民から「うちの駅の方が九品仏に近いのだから、駅名を返して欲しい」という申込みがあったので、九品仏を返して自由が丘駅となった。
昭和36年7月1日、「青空」という自由の女神像が芸術院会員・沢田政広氏の手によって完成した。8月1日には、地下2階地上9階の東急ビルが完成、既存の自由が丘デパート、ひかり街、丸井、長崎屋、ピーコック、東急ストアと続々と大店舗が参入、これにつれて、大銀行、大証券会社等も続々と開店、東京有数の異色の盛り場となっていった。
|
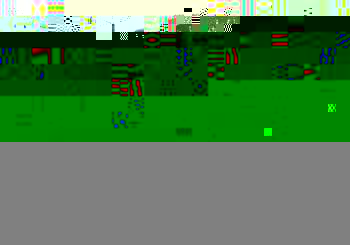
幾多の俊英を輩出した石井獏舞踊研究所 |
|
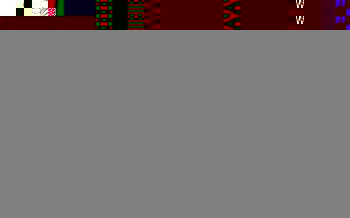
熊野神社境内にある栗山久次郎翁の銅像 |
|
碑衾村村長、栗山久次郎
この盛り場の北のはずれに、旧衾村・谷畑・中根の産土神(うぶすな)、熊野神社があり、ここに栗山久次郎翁の銅像が建つ。
明治22年から二十余年、碑衾村々長をし、私財を投げ出して、土地の発展に尽くした。この人は時間厳守の人で、毎朝役場へ行く時間は一分と違わなかった。村の人は、時計代わりにしていたという。
昔は、1年間公職につくと、一町歩売るといわれており、栗山翁は24年間やったので、24町歩を売った。それで息子さんが役場に乗り込んできて「村長をこのままやらせるなら、親父を勘当する」といったという伝説がある。
昔は、村民の税金の滞納があると、村長が立て替えたそうで、中根・八雲・宮前にあった広い土地はみな売ってしまったが、それでも大鍋の底で、今でも目黒区で2番目の大地主である。
昔はこのように、政治家はみな井戸塀(貧乏して、塀と井戸だけ残ること)になっており、村会議員は、10町歩以下ではなれなかった。村長をやるには50町歩は持っていないと、すぐ井戸塀になってしまった。
その頃、村会議員連はタバコも敷島、朝日というのを1日に2箱位喫ったから議員の給料はそれだけでなくなってしまったのだ。一般庶民はキザミ(萩)で“あやめ”さえ喫えなかったという。だから、みな井戸塀になり、銅像が建ったという。だから、深沢の三田、秋山家には 「政治に関与すべからず」という家訓があり、駒沢の谷岡村長も、深沢、等々力の各村長もすべて井戸塀になってしまったそうだ。
|
|
|
住民が恩恵をうけた谷畑弁財天
駅の近く、王助監督のコマーシャルで有名な亀屋万年堂本店の裏手に谷畑弁財天が、ひっそりと鎮座まします。昔は清水がこんこんと湧き、住民が大きな恩恵をうけた。地主の安藤与四郎さんの先祖が、弁財天を祭り、自由が丘の守護神として建立したものである。
耕地整理が早かった奥沢と駅名を変えた緑が丘
大正12年に、目蒲線が引けて奥沢駅が出来ると、この辺の人は、みな奥沢駅まで歩いて、目黒駅へ出ていった。そのため、奥沢は世田谷区内であるが、ここの耕地整理組合は、世田谷・目黒区内でも一番早く結成された。だが、奥沢駅へ行くのに田んぼの中の細い農道を行かなければならない。この道を少し拡げよう、ということから、区画整理が早く始まったのだ。
昭和4年、大井町線大岡山~自由が丘駅間が開通した時には、いまの緑が丘駅は「中丸山」といった。それは、この高台が栗山重治さんの山で「中丸山」とよばれていたからで、大正9年、駅を作るために、坪2円50銭で電鉄に売ったという。 昭和7年10月。目黒区が出来た時、現在の緑が丘は、隣が自由が丘と名前をつけたので、こちらは、未だ緑が多いから、緑が丘にしようと、ごく簡単な話し合いで決まってしまった。
“丑川”とは・・・
自由が丘駅ホームの田園調布寄りのガード下を流れていた九品仏川は、いまの東横学園の裏の湿地帯から流れ出し、九品仏の西を流れてきて、大岡山の東工大のそばで、呑川へ注いでいる。この川を、土地の人は“丑川”という人もいる。これは、九品仏建築の時、材木を引張ってきた牛が、早朝、堰を渡った時、川にはまり込んで死んだので、その地点から下流を丑川と呼ぶようになった。
古老の杉村さんが、昭和7年に、現役入営した時、熊野神社で拝んでもらってから、駅まで行進したが、その時は、両側が商店になっていたのを覚えているという。
この熊野神社の御祭神は伊邪那美命(いざなみのをみこと)、速玉之男命(はやたまのをみこと)、事解之男命(ことさかのをみこと)の3柱で、宝暦12年(1762)、220年前に建立され、当時の氏子も64戸で、昔は戸数をふやさないように指導したという。
現在の建物は、昭和42年に建立したもので、旧社は隣に移し、稲荷神社になっている。氏子の区域は、自由が丘と緑が丘で奉賛会々長は栗山重治さんでここの目黒ばやしは有名である。
|