|
自由が丘駅まで5つの踏切
代官山のトンネルを出た所から高架になった東横線は、都立大学駅を出た所で、久しぶりに地面におりる。その途端に、またしても踏切がはじまる。そして自由が丘駅に着くまでに5か所もある。そのうち、一番大きな2号踏切では、八百屋さんの三輪車の衝突即死事故があった。ここの奥さんとはよく会うが、その度に、この事故を思い出してしまう。もう一つ、自由が丘駅の近くに、大混雑で、しかも踏切をはさんで、五叉路のハラハラさせられる難所があり、そのうえガードにはなっていても高さが極めて低いものもあり、電鉄の頭の痛いところであった。
しかし、もう先へ延ばせないところまできているようだ。これが実行されると、付近の風景は全く一変するので、記録写真をたくさん撮っておいた。
最近都立大学駅が高架になる前の写真を見たが、今の喧噪の駅前からは、全く想像できない風景であり、高架という大工事が街に及ぼす影響の大きさに、恐怖さえ感じた。
街に若さを吹き込む都立大生
この街の、もう一つの大問題は、当の都立大学そのものの移転問題である。今の都立大学のムンムンするようなエネルギーは、駅から学校までの間の怒涛のような学生の登下校の行列である。
目黒通りの赤信号でせきとめられた怒涛は、青信号となるや、駆ける者を先頭に津波のように突き抜ける。街の人は、この若さの奔流にまき込まれないように道を開けて、この激流を親愛の情一杯の瞳で見送る。
小学生と違って、登校、下校の時間がまちまちである。しかも、自慢の昼夜開校制であるから、波の高低はあるが、この行列は、夜おそくまで続く。
雨の日などでは、傘が交差して、歩くこともむずかしいくらいだ。このジーパンとTシャツの学生が都立の街に若さを吹き込んでいるのだ。
|
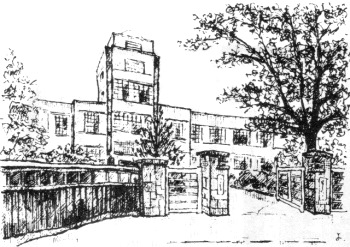
東京都立大学校舎正門 |
|
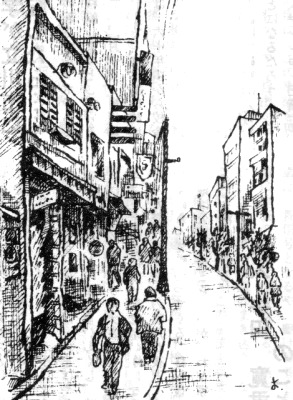
都立大学駅前の通り |
|
都立大学が立川市に移転したら・・・
この若さのルツボである都立大が立川市へ移転しようとしているから大事件だ。
昨年4月1日、楠川絢一新総長は記者会見で、立川基地跡地の新キャンパスは、60年頃から校舎の建築にかかるという。中目黒からアメリカンスクールがなくなった以上の激変が、都立大学の街を襲うだろう。商店会は、その対策研究会を設けて研究に入らないと悔を残すことになるだろう。
わたしの部屋(マンション3階)と、いまの都立大学のキャンパスとは、同じ高さのせいか東光寺、常円寺の、大樹の先のキャンパスの様子が手にとるようにわかる。
夜間には、いまはやりのテニスコートの照明燈が輝〈し、時には、海坊主のように大きな熱気球がニューと顔を出す。記念祭の頃になると、太鼓の音や若人の喚声が夜遅くまで風に乗って伝わってくる。移転後の跡地は公園になるらしいが、わが家はとても淋しくなる。
(★ こうした地元の「立川に行かないで〜!」の願いもむなしく都立大学は、平成3年(1991年)多摩ニュータウンへ移転しました。そして校名も「東京都立大学」から「首都大学東京」に改称したのでした。 跡地隣に東京都立付属高等学校が残っていましたが、同校も「東京都立桜修館中等教育学校」に吸収され校名変更。
結局、「都立大学」を冠した校名は消え、駅名「都立大学」だけが残りました。岩田忠利)
|
|
|
友人牛田 寛君のこと
都立大学の理学部は、ちょっと離れた駒沢公園のそばにあるが、以前、ここの部長の木戸教授は、わたしが横浜高工で物理学を教わった先生でした。近所の床屋の椅子で数回出会ったことがあり、お互いに動けない状態なので、横向きで、長い時間お話をすることが出来たことは幸運であった。
話題は主に先生の従弟の牛田寛君のことであった。牛田と私は、偶然小学校が同級(恵比寿駅のそばの長谷戸小学校)であり、横浜高工も同じ機械工学科という奇縁であった。その牛田が木戸先生の従弟とは知らなかった。
牛田は間もなく参議院議員になり、そして間もなくガンで死んでしまったが、その頃は木戸先生のひきで、付属高校の教諭をしていたらしい。或る夕方、台所の戸があいて牛田がヌーッと入ってきた。
「とうとう、全国区から参議院選に出ることになって……」という。
30年ぶりなので、私は、彼の足ばかりを見ていた。というのは、夕方の薄暗闇の中に立っているのは、牛田の幽霊ではないかと思ったからだった。
かれは横浜を出るとすぐ、蒲田の東京計器へ就職したが、すぐ肺結核になり、休職してしまい、音信不通になってしまった。小学校のクラス会の通知にも全く返信なく、「死亡」ということになっていたのだ。かれの話を聞くと、以来、大東亜戦争終了まで、療養していたという。
「身の回りのもの、何から何まで売りつくし、もう何もなくなった時、やっと病気が治り、戦争が終ったのでした…」と言う。
そこで、叔父の木戸先生に頼んで高校の教諭をしていたのだが、最近、女房が、創価学会に入れといってきかないという。(かれの女房は創価学会を興隆させた戸田城聖会長の姪であり、自宅は私のすぐ近くの駒沢公園の隣だという)。
女房が「社会に尽くす道はいろいろある。ぜひ学会に入り、青年部長になり、2,3年して参議院議員になって活躍しては…」と強く勧められ、木戸先生に相談したら、それもよいだろうといわれたので、ようやく決心して入信し、女房の言うとおり、青年部長になり、こんど参院全国区から出ることになったから、よろしくということだった。見事当選、今度は一升さげてクラス会にやってきた。
彼は、間もなく胃ガンで死に、駒沢公園の隣の自宅の通夜に行った。暗い夜だった。
|
|