|
カストリ焼酎屋も並んだ渋谷界隈
ザクザクと靴音をとどろかせ、機動隊がやってきた。今夜もこの宮下公園でデモがあるのだろうか。
ここから見ると、東急デパートのてっぺんの大時計がよく見える。いま午後4時13分だ。
宮益坂の中途に御嶽神社があり、その下の公園なので 〝宮下公園”と名付けられた。が、ほとんどの人は、その意味を知らない。この御嶽神社は富士山がよく見える名所として知られ、明治天皇も、富士を御鑑賞になられた、という。だから、この宮益坂を富士見坂ともいう。この神社のすこし上に、大きな都電の車庫(青山車庫)があり、国連大学用地になりそうだ。いまでも、風の強い日なら、富士山の雄姿が眺められる。
東横線、渋谷駅の下は、渋谷川が流れている。終戦後は、バラックが建ちならび、いつも将棋クラブをのぞく群衆があった。カストリ焼酎屋や赤提灯が並んでいた。
いまは、改札口を出て右に〃東急文化会館〃への大きな渡り廊下がかかっているが、公道の上に私道を渡した東急社長・五島慶太の怪談は、いまだに語り草になっている。
いまの文化会館の土地にも大きなバラックが建っており、〝第一マーケット″とよばれ、60軒ほどの飲み屋さんが繁昌していた。ここに西武の堤康次郎が目を付け、デパートを進出させようという噂が出ると、五島翁は、すぐこのマーケットと強引に交渉を始め、30軒の人には金を、あとの30軒の人には宇田川町(今の東急本店のそば)に2階建ての長屋を建ててここへ越させ、東急文化会館を建てた。
急に寂しいところに引っ越した人たちは、なつかしい 〝第一マーケット″の名前を残して〃第一栄楽街〟というアーチを作り、がんばっていた。 |
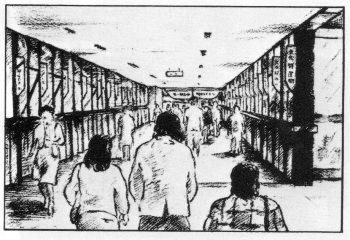
東急文化会館への渡り廊下 |
|
毎日がファッションショー
その後、五島昇の時代になって、東横デパートの成績が伸びないのは、渋谷に一店しかデパートが無いためであることがわかり、西武の堤清二に頼んで、今の西武デパートができ、渋谷が賑やかになった。そこへNHKが神南町に引っ越してきたのと、東京オリンピックのために代々木公園が整備されたのとで、渋谷→NHK→代々木公園→原宿→神宮外苑という巨大な散歩圏ができあがった。
“公園通り”(パルコ通り) は若人の通行量が激増したため、公園通りに”西武パルコ〟”渋谷公会堂〟、〝NHKホール”など、若人の参集がふえ、かつての道玄坂百軒店(ひゃっけんだな)の面影を完全に奪ってしまったとは、不思議ななりゆきである。
あの寂しい陸軍衛戌監獄(えいじゅかんごく。のち、陸軍刑務所と改称)や練兵場等で、夜など人通りの全く無かったところを、今はニューファッションの若人の波が、夜更けまで途絶えないとは…。
あの地で処刑された2・26事件の青年将校17人の霊は、さぞやびっくりしていることであろう。
大きなデモは代々木公園で、小さなデモは宮下公園で、といわれるように、全く活力ある町となった渋谷は、私の生まれた町であり、昭和12年の天長節には、2等兵として代々木練兵場(今の代々木公園)で、名馬白雪にまたがった大元師閣下の馬前を、名曲〝田原坂″の調べに合わせて勇壮に分列行進したところである。
雪の横浜駅ホーム
戦前は、宮益坂を市電が下りてきて、今の国鉄渋谷駅のガードをくぐると左折して駅前広場が終点だった。改札口前の駅前広場には、当時東京中の駅前にあった「東京パン」があり、モダーンな感じを漂わせていた。
渋谷を出ると、すぐ「並木橋」という駅があり、この駅を出るとすぐ国鉄の線路の上を大きくカーブして「代官山駅」に向かう。
私は、昭和9年4月から、横浜高等工業学校へ通い始めたが、自宅が国鉄恵此寿駅と「代官山駅」との中間地点だったので毎日「代官山」から「横浜」まで乗車した。(横浜で京浜急行に乗り換え弘明寺下車)たいがいの学生は始業ギリギリに行くので、同校通学の者は、同じ電車で顔を合わせたものだった。並木橋駅からは同級の現参議院議員の後藤正夫氏が毎朝乗車してきた。当時、飛ぶ鳥を落とす勢いの後藤内相の御息子であった。
昭和11年2月26日の雪の朝、私達は、横浜のホームを降りた時、妙な予感を身体に感じた。学校へ着くと、早朝、帝都に大事件が起こったらしい、と騒いでいた。2・26事件だった。この朝の横浜駅の雪のホームの情景は生涯忘れられない。
代官山に住む二人の大物
代官山駅を出ると、すぐトンネルに入る。このトンネルの真上に、五島慶太東急電鉄社長が住んでいた。自分の苦心した電車が、トンネルの中を通過する轟音と、振動を快い夢の間にも愉しむほどの仕事熱心な人だった。この五島・代官山邸のすぐ近くに、当時、府会議長の朝倉虎次郎が住んでいたので、何かと事業展開に便利であったらしい。
当時の府会議長(現都議会議長)の権勢は大したもので、裸一つで新潟から出てきて米屋になり、財を成した虎次郎は今でいえば田中角栄のごとく、立身出世の鑑(かがみ)といわれたものだった。
自由が丘に住む古老の一人は、父親から「朝倉」という姓のような名前をつけられたが、朝倉虎次郎にあやかるようにと、朝夕訓戒を受けたというほどである。
(当ボードNO.38、越智英夫さんの「歴史的建造物」に朝倉邸が登場!) |
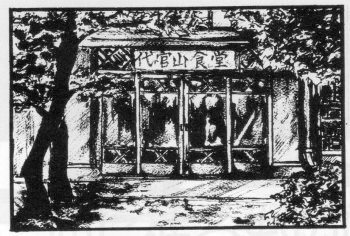
昔の面影を残す代官山食堂
|
|
思い出多い雑木林
代官山の駅名の由来は、私の家のすぐ裏の〝代官山″からきている。赤土の絶壁の山で昔の代官屋敷があったところらしく、要害の高台で、山頂は平らになっており、3分の1は雑木林、3分の2は原っぱだった。夏の終わり、この原の上には銀ヤンマや大ヤンマなどの大きなトンボが、悠悠と遊泳する。これを捕ろうと、たっぶりモチを塗った竹竿を振って追いかけまわし、6メートルもある断崖から転落した子も出た。
大正12年の関東大震災には、数箇所の崖が崩れた。が、かえってこの場所が子どもたちの、新鮮な遊び場になり、跳び降り度胸だめしが流行り、2歳下の妹は、女だてらに跳び降り、両脚を骨折して長く学校を休んだこともあった。
雑木林では、あの頃は不景気だったせいか、首吊りの名所となり、ずいぶん見にいった。ヘコ帯に首をかけて、ブランとだらしなくぶら下がった人は、みんな申し合わせたように、二つの鼻の孔から、青く長い鼻汁が下がっていた。 雑草が茂る秋口には、その長い葉を結び、近くにかくれ、夕闇にまぎれてやってくるアベックが、足をとられてひっくり返るのを待ったり、山深い草むらの中では、何組もの″濃厚シーン″が見られ、好奇心からノゾキに行ったものだった。この高台には、現在、長谷戸小学校が建っている。
(次回は「中目黒」編)
|