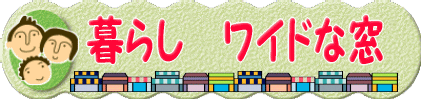 |
| ロゴ:配野美矢子/編集支援:阿部匡宏 |
| 編集:岩田忠利 NO.94 2014.7.07 掲載 |
|
★画像はクリックし拡大してご覧ください。
|
|
|
| |
沿線住民参加のコミュニティー誌『とうよこ沿線』好評連載“復刻版”
掲載記事:「地名 その8 昭和58年7月1日発行本誌No.17 号名「杏」
執筆:桑原芳哉(大倉山・学生) 絵:石橋富士子(横浜・イラストレーター) 地図:伊奈利夫(桜木町)
|
|
|
い、いそがしい。ああ、忙しい……。大学4年になると、こうも忙しいものなのでしょうか。
え、原稿のしめきりだって? そ、それはないでしょ紀子さん。この忙しい僕に向かって。もう、こうなったら神にすがるしかないですよ。神様、助けて!
というわけで(!?)、今回は「神社の名前に由来する」地名を拾ってみました。これなら、御利益、間違いなし!
|
近江ゆかりの・・・
日吉 (横浜市港北区・川崎市幸区)
「陸の王者」慶応義塾、そして『とぅよこ沿線』編集室があることで知られる(!?)日吉」。この地名は、明治22年の市町村制施行の際に生まれたものである。
日吉という地名は、近江国(滋賀県)の日吉大社を本祠とする、日吉(日枝)神社に由来するもので、多くの地で見られる。
東横線の「日吉」は、中でも全国にその名を知られている。この日吉の地にも、「日吉神社」があり、この神社が地名の起こり、と考えられるがどうやらそうではないらしい。
日吉本町に金蔵寺という寺がある。『新編武蔵風土記稿』 上駒林村・中駒林村・下駒林村の稿にも「金蔵寺」について書かれているが、その中に「山王社」の文字が見える。山王社は日吉社の別称である。そう、この「山王社」こそ、「日吉」の地名の起こりらしいのである。
金蔵寺は、近江国の三井寺に対して「東三井寺」とも呼ばれた寺。そして日吉神社の本祠も近江国と、日吉の地は何やら近江国と関係が深そうである。日吉には、いま滋賀県人が何人いるのだろう。
ところで、「日吉」という地名は、川崎市幸区にもあるのをご存知だろうか。
かつての日吉村は、今の港北区と幸区にまたがっていたが、大騒動の末、昭和12年に日吉村は東西に分かれてしまったのである。川崎市が今なお出張所や学校名に「日吉」の名を残しているのも、川崎市の「意地」であろうか。
|
|
神社が先か、地名が先か・・・
元住吉・木月伊勢町 (川崎市中原区)
元住吉駅の西隣りに、住吉神社がある。「住吉」の地名は、この住吉神社に由来する、と考えられよう。
住吉神社は、明治41年(1908)、木月村内の10か所の神社を合祀し、翌42年に改称したものである。ところが、住吉という地名は、明治22年(1889)に生まれている。これでは順序が逆である。
しかし、住吉神社の名が地名からつけられたとは思えない。おそらく、合祀された10か所の神社のうちの1つが、住吉社を祭っていたのであろう。
木月伊勢町の地には、かつて伊勢宮という小祀があった。しかし、明治41年に合祀され、住吉神社になってしまった。地名だけが小さなお宮の跡を残している。
信心深い町?・・・
上丸子山王町・天神町・八幡町 (川崎市中原区)
上丸子には、山王町、天神町、八幡町と、神社に由来する町名が三つもある。
上丸子山王町には日枝神社がある。「日枝(日吉)神社=山王社」であることは日吉の稿に書いた。つまり、この日枝神社が「山王町」という地名の起こりなのである。
また、かつての上丸子村には、天満宮、八幡社も存在していた(『新編武蔵風土記稿』)。この天満宮、八幡社に由来する地名が、それぞれ上丸子天神町、上丸子八幡町であることは言うまでもない。
それにしても、神社に由来する地名を三つもつけるとは、上丸子の人々も信心深いことである。
|
|
|
|
「みたけやま」ではなくて・・・
御岳山 (東京都大田区)
池上線の「御岳山」駅。中学生の時、この駅名を「みたけやま」と呼んで友人に大笑いをされた苦い思い出のある駅。でも、どうして「おんたけさん」なのだろう。東京の青梅の奥にあるのは「みたけ」。山にある神社ももちろん「みたけ神社」。でも木曽のは「おんたけさん」か。
ともかく、この駅名が、すぐそばにある「御嶽神社」に由来することだけは、確かである。ところでこの神社「みたけ」? それとも「おんたけ」?
このほか、神社に由来する地名としては、鹿島大神宮にちなむ鹿島田(川崎市幸区)、白山神社の白山(横浜市緑区)、白幡神社(八幡社)の白幡(横浜市神奈川区)、子安神社に由来すると思われる子安(横浜市神奈川区)、浅間神社の浅間町(横浜市西区)、そして伊勢山皇大神宮ゆかりの伊勢町(横浜市西区)と、数多くがある。
ところが、これらはすべて神奈川県側の地名。東京側には、「宮内」「上の宮」というものさえ見あたらない。これはどういうことなのだろう。東京っていうところは、神も仏もない土地なのかなあ・・・。
|
<参考資料>
「横浜の町名」「川崎地名考」
「新編武蔵風土記稿」「中原町誌」
|
|
|
 |
「とうよこ沿線」TOPに戻る |
 |
次ページへ |
 |
「目次」に戻る |
|
|
|