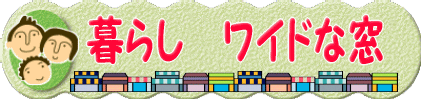 |
| ロゴ:配野美矢子/編集支援:阿部匡宏 |
| 編集:岩田忠利 NO.87 2014.7.05 掲載 |
|
★画像はクリックし拡大してご覧ください。
|
 |
 幕末の大老井伊直弼を追って 幕末の大老井伊直弼を追って |
|
沿線住民参加のコミュニティー誌『とうよこ沿線』の好評連載“復刻版”です。
掲載記事:「地名 その3」 昭和57年7月1日発行本誌No.12
執筆:桑原芳哉(大倉山・学生) 絵:石橋富士子(横浜・イラストレーター)
|
|
|
桜木町駅から紅葉坂を行き、県立音楽堂の脇を抜けたところに「掃部山(かもんやま)公園」はある。石段を上ると、まるで港を見据えるかのように立っている銅像が目につく。これが幕末の混乱の主役とも言うべき、大老・井伊直弼の銅像である。
地上からの高さが11㍍というこの像が、なぜこの地に建てられたのか。沿線に残された史跡を訪ねて、暮未の大老・井伊直弼を追ってみた。
|

掃部山に建つ井伊直弼の銅像
撮影:配野美矢子さん(港北区下田町) |
|
|
●井伊家の下屋敷は今・・・
◆代々木 (東京都渋谷区)
井伊氏ほ、平安時代の中頃、遠江守に任ぜられた藤原共資の子、共保に始まるという。共保は遠江国引佐郡井伊谷(静岡県、浜松の北)に居を構えたことから「井伊」を姓としたようである。
それでは、静岡の地方豪族にすぎなかった井伊氏が、なぜ大老職にまでつくようになったのだろうか。時代は下り、彦根藩主、井伊直孝の登場となる。
直孝の父、直政は徳川家康に仕え、関ケ原の戦いでも功をあげた。直孝も、父亡きあと家康から家綱まで、4代の将軍に仕え、大坂冬の陣、夏の陣など功多かったという。
寛永10年(1633)、直孝は3代将軍家光から、世田谷領15五か村(荏原郡世田谷村、弦巻村、用賀村、野良田村、小山村、下野毛村、上野毛村、瀬田村、八幡山村、多摩郡岡本村、鎌田村、大蔵村、岩戸村、緒方村、和泉村)を与えられた。現在の世田谷区中央部から多摩川までは、江戸時代には井伊氏の領地、つまり武蔵にありながら、近江国彦根藩の飛地だったのである。
さらに寛永17年(1640)に、上渋谷、千駄谷一帯を与えられた直孝は、この地に手を加え、庭園を整えて下屋敷を建てた。
屋敷の南東に樅(もみ)の大木があり、「代々木」と呼ばれていたという。「代々木」の地名の起こりは、この樅の大木にあるのかもしれない。
現在、この下屋敷の地は、明治神宮の森となっている。南参道の左側に、「代々木」という立て札と、一本の木が弱々しく立っていることを、何人が知っているであろうか。
●ほど近い地に眠る二人
◆豪徳寺・松陰神社 (東京都世田谷区)
明治神宮を後にして、小田急線に乗ると、時代は幕末まで下ってゆく。豪徳寺に眠る井伊直弼、松陰神社に眠る吉田松陰・・・。幕末に激しく生き、命を失った二人が、同じ世田谷区内の、ほど近い地に眠っているというのも、不思議な縁かもしれない。
豪徳寺へは、小田急線豪徳寺駅よりも世田谷線宮の坂駅の方が近い。山門の脇には、「都史跡 井伊直弼墓」 の碑が建てられている。
直弼の墓は、墓地のいちばん奥にある。花も線香も新しい。「宗観院殿柳暁覚翁大居士」という法号の彫られた墓石は、苔むしてはいるが堂々としたものである。墓の横にはきれいな説明板まで建てられている。
堂々とした墓、絶えることのない花と線香、「都史跡」の碑と説明板・・・幕末の混乱の主役、井伊直弼を慕って、この墓を訪れる人は、後を絶たないようである。豪徳寺の「招き猫」に手招きでもされているのだろうか。
豪徳寺から世田谷区民会館への道をとり、松陰神社に向かう。松陰神社の近くには大学などもあり、道路や公園は若者たちで賑わっている。そんな中に、松陰神社だけがポッンと一つ、取り残されているかのように、静まりかえっている。
鳥居をくぐるとすぐ、左側に「松陰先生の像」がある。やわらかなその表情は、松陰の人柄をよく表わしているように思える。こじんまりとした台に、ちょこんと座っていることも、いっそうその感を強くする。
松陰の墓も墓地の奥まった所にあった。横に木の立て札があるが、全く読めない。同じく安政の大獄で犠牲となった、頼三樹三郎ら4人と共に眠っているのだが、どの墓石も質素なもので、線香などは見られない。これでは、訪れる人も、まさかこの墓があの吉田松陰の墓だとは、思わないだろう。特に、豪徳寺の井伊直弼の墓を見てきた人などは…。
墓のこのような姿も、松陰らしいと言えばそうなのかもしれない。しかし、井伊直弼、吉田松陰の2人の墓を見て、歴史上での2人に対する評価を考えると、松陰の墓の実情は、どうしても納得できない。このままでは、松陰があまりにもかわいそうではないか、それとも今でもなお松陰は「罪人」なのか!
この疑問を解決すべく、再び掃部山公園へ行くことにする。 |

「都史跡 井伊直弼墓」
「吉田松陰先生の墓」
|
|
|
|
|
|
●立派すぎる銅像に人々のエゴを見た
◆掃部山 (横浜市西区)
掃部山の地は、明治5年(1872)の鉄道開通時に、蒸気機関車のための給水施設が設けられたところである。給水施設といっても、単なる水だめにすぎなかったようだが、この水だめのために、この地は「鉄道山」と呼ばれていたという。
しかし、その後この地は井伊家に買い取られ、明治42年(1909)、井伊直弼の銅像が、この地に建てられたのである。「掃部山」という名は、直弼の官名「掃部頭」からつけられている。
史実に基づいた正しい評価を
井伊家の人々は、直弼が開国に貢献したとして、開港の地、横浜港が一望できるこの地に銅像を建てたのであろう。しかし、このような11㍍もある像を建てる必要があったのだろうか。
直弼は、安政の大獄で吉田松陰らを処刑したことで、不当な評価を受けたと言われている。その不当な評価を打ち消そうと、亭徳寺の墓も立派なものにして、銅像も立派なものを建てたのだろう。しかし、不当な評価を打ち消したいのなら、史実に基づいてきちんと直弼の業績を証明すべきではないだろうか。それを行わずして、銅像を崇めるなど、まさしく人間のエゴそのものではないか。
直弼の不当な評価を打ち消すのはいいことである。けれども、松陰の評価は、今までのままでいいはずである。松陰の精神に報いるために、松陰の墓の整備を、ぜひ行っていただきたいということも、最後につけ加えておこう。
|
参考資料
「新編武蔵風土記稿」、「角川日本地名大辞典 13東京都」、「新修世田谷区史」、「せたがやの歴史」、「神奈川人物風土記」、「横浜物語」、「横浜史を歩く」他多数。
|
|
|
 |
「とうよこ沿線」TOPに戻る |
 |
次ページへ |
 |
「目次」に戻る |
|
|
|