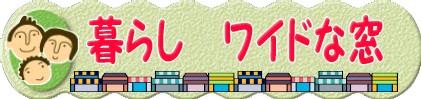 |
| ロゴ:配野美矢子/編集支援:阿部匡宏 |
| 編集:岩田忠利 NO.85 2014.7.04 掲載 |
|
★画像はクリックし拡大してご覧ください。
|
 |
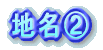 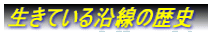 鎌倉武士と地名 鎌倉武士と地名 |
地名には、歴史が隠されている。文化が隠されている。人間が隠されている。
そんな地名に隠された「何か」を、発見しよう。 |
|
|
東横沿線住民参加のコミュニティー誌『とうよこ沿線』の好評連載“復刻版”です。
掲載記事:「地名 その2」 昭和57年5月1日発行本誌No.11
執筆:桑原芳哉(大倉山・学生) 絵:石橋富士子(横浜・イラストレーター)
|
|
人名にまつわる地名は、数限りなくある。しかし、人名からつけられた地名というのは少ない。なぜなら、自然的条件などからつけられた地名を姓とする者が、古代以来多かったためである。この沿線にも、その例は多い。
その中から、今回は鎌倉時代に活躍した人名にまつわる地名をとりあげてみた。 |
|
◆渋谷 (東京都渋谷区)
「渋谷」という地名の起こりには、大きく二つの説がある。一つは、古代にはこの地は海に面していて、人々が塩を焼いていたところから、「塩谷」という地名が生まれ、これが転化したというものである。そしてもう一つは、平安時代末期に相模国高座郡渋谷庄を領していた渋谷氏の支族が、この地に移り住んだところから「渋谷」と呼ばれるようになったというものである。
前の説をとれば、この地に移り住んだ豪族が、地名であった「渋谷」を姓としたことになり、地名から人名が生まれたことになる。しかし、後の説をとれば、逆に人名から地名が生まれたことになるのである。このあたり、人名と地名との関係がいかに複雑であるかを、如実に示していると言えよう。
なぜ渋谷氏は源氏に従ったのか
それでは、平安末期からこの地を支配していた渋谷氏とは、いかなる氏族であったのだろうか。
渋谷氏の家系をさかのぼると、桓武天皇に行きつく。つまり渋谷氏は、平氏の一族なのである。桓武天皇の孫、平高望の五男である平良文が武蔵守となり、その子孫らは武蔵一帯に勢力を持って、源頼義・義家らに従ったという。
なかでも河崎基家は、1051年の前9年の役で頼義に従って功績をあげ、その子重家は、後3年の役で功を立てた後、宮中で捕えた盗賊の姓「渋谷」を堀河天皇から賜わった。ここに平氏の流れをくむ「渋谷氏」が、歴史に登場するのである。
と、ここまで読んで、「変だな」と思わなかった方は、よほど歴史に強いのか、それともナナメ読みをしているのか、どちらかであろう。
平氏の一族が源氏に従っていたことは、どうしても疑問となって残る。渋谷重家の子、重国・金王丸も、当然のように源義朝・義平に従っている。これは、平氏一族といえども渋谷氏は、武蔵の一豪族にすぎなかったためである。武蔵の一豪族が、東国の総元締めである源氏に従ったのは、当然と言えば当然。だからこそ、現在まで渋谷氏が続いているのであろう。
◆目黒 (東京都目黒区)
「目黒」という地名の由来にも、二通りの説がある。一つは、目黒不動に由来するというものであり、もう一つは、馬にちなんでいるというものである。しかし、目黒、目白、日赤などという名で不動が呼ばれるようになったのは、江戸時代のことと言われており、目黒不動に関しては地名の方が先、と言えるだろう。
目黒氏はどこから・・・
地名の起こりに関しては、人名とは全く関わりがないようである。しかし、鎌倉時代にはこの地に源氏に仕えていた「目黒Lを姓とする武士が居住していたという。それでは、この目黒氏と地名とは、どのようなつながりがあるのだろうか。
ところが、渋谷氏が平氏一族で、桓武天皇を租としていることまでわかっているのに対し、目黒氏の祖にはさまざまな説があり、どれとも決めがたいのである。そして、目黒と目黒氏とのつながりもはっきりしていない。偶然の一致とは考えにくいから、何かつながりがあるはずだが……。
|
|
|
|
目黒と「馬」
中世以来、この付近は馬が多かったようで、「馬」あるいは「駒」 のつく地名もあちこちに見られる。そんな中に、「目黒」という地名も、馬に由来するとの説があり、これはさらに二通りにわかれる。一つは眼色・毛色によって区別される馬の種類、つまり、黒馬が多くいたところから生まれた地名というものであり、もう一つは、牧場の周りの畔道を意味する「馬畔(めぐろ)」 が書き改められたとするものである。
これらの説が正しいかどうかは定かでないが、この地が、中世以降も馬と深く関わってきたことは、確かである。江戸時代には鷹狩りが行われ、幕末から明治の初めには駒場に調練場、騎兵学枚が、そして明治40年には、競馬場が設けられたのである。
この競馬場、春・秋の競馬シーズンにはかなりの賑わいを見せ、権之助坂からの道は人力車で埋まったという。競馬場は昭和8年に府中に移ったものの、「目黒」の名は、春・秋2回東京競馬場で行われる「目黒記念」というレースの名に残されている。けれども目黒区内には、「元競馬場」というバス停の名だけが残されているにすぎない。バス停の名からかつての賑わいを思い浮かべる人が、はたしてどれだけいるであろうか。

昭和7年、目黒競馬場で第1回日本ダービー開催
目黒競馬場は、明治40年(1907)に日本競馬会によって開設されました。が、周囲の宅地化による地価高騰とそれによる競走馬の飲み水確保が難しくなったこと、広さ6万坪は競馬場として限界ということで、昭和8年府中に新設の東京競馬場に移転しました。
東京競馬場の伝統レース「目黒記念」は、目黒競馬場の名を後世に残すために昭和7年に創設されました。
写真と資料:碑衾町誌
|
|
|

目黒競馬場跡の記念碑
目黒通りの元競馬場交差点から少し東方向へ行った同通り端に有名な種牡馬の彫刻が建っています
|
|
|
|
◆井田 (川崎市中原区)
多摩川を渡って神奈川県側にも、人名に閲した地名は多い。しかし、渋谷氏・目黒氏ほどの勢力を誇った豪族の姓ではなく、田舎武士の姓に関連したものが大部分である。その中で、川崎市に残きれているものとしては「井田」があげられる。
平安末期、この他には井田摂津守某という武士がいたという。彼は源義家に随(したが)ったが、陸奥国九戸合戦で討死してしまった。現在、井田摂津守を偲ばせるものは何もないが、この地の旧鎌倉街道に源頼朝ゆかりの「鞍掛松」など、鎌倉時代の伝承旧跡などが多く残されているのは、偶然ではなかろう。 |
|
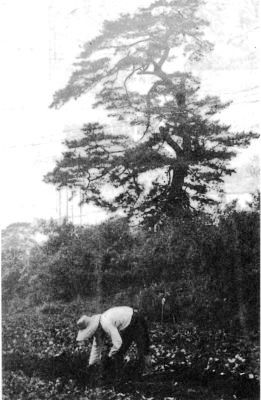
昭和17年、鞍掛の松(樹齢700年)
高さ30メートル、太さ3人抱えの大きな松が井田山の現・しいのき学園の西隣に立っていました。
提供: 田辺芳夫さん(世田谷区喜多見) |
|
◆鳥山・六角橋 (横浜市港北区・神奈川区)
鳥山・六角橋は、ともに宇治川の戦いで功をあげた佐々木四郎高綱にまつわる地名と言われている。
源頼朝は、宇治川の戦いで功績のあった高綱に所領を分け与えた。このうち、高綱が一族の鳥山左衛門という者に管理させた地が、今の鳥山であり、六角太郎という者に管理させた地が、今の六角橋であるという。
しかし、この高網にまつわる説に対して 鳥山には、小高い丘だったことを示す「嶋」という字が分かれてできたという説、六角橋には日本武尊にまつわる「六角箸」伝説も伝わっている。日本武尊など、どう考えてもマユツバものだが……。
◆◇◆
かように、地名と人名とのつながりを明らかにするのは難しい。渋谷で生まれたから渋谷氏なのか、渋谷氏がいたから渋谷なのか……。まるで 「ニワトリと卵」 だ・・・。
しかし、元をたどれば地名も人名も、自然的条件そのほか周囲をとりまく何かに由来してつけられたはずである。どちらが先か後か、などと考えることは、意味がないことのように思える。そう、地名も人名も、出発点は同じなのだ。
私の名も、あなたの名も、きっと地図の上で見つけられるにちがいない。また地図を見る楽しみがふえたことに、感謝!
◇主な参考文献
「角川日本地名大辞典」「目黒区史」「渋谷区史」「川崎地名考」
「ふるさと1町1話」「横浜町名沿革誌」 |
|
|
 |
「とうよこ沿線」TOPに戻る |
 |
次ページへ |
 |
「目次」に戻る |
 |
地名③へ |
|