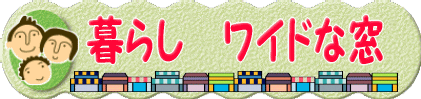 |
| ロゴ:配野美矢子/編集支援:阿部匡宏 |
| 編集:岩田忠利 NO.84 2014.7.04 掲載 |
|
★画像はクリックし拡大してご覧ください。
|
 |
 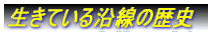 鷹狩りと地名 鷹狩りと地名 |
地名には、歴史が隠されている。文化が隠されている。人間が隠されている。
そんな地名に隠された「何か」を、発見しよう。 |
|
|
| 掲載記事:「地名 その1」昭和57年3月1日発行本誌No.10 |
執筆:桑原芳哉(大倉山・学生) 絵:石橋富士子(横浜・イラストレーター)
|
|
執筆者「桑原芳哉」の自己紹介
執筆時(『とうよこ沿線』編集参加時)は、横浜国立大学学生(2~4年時)。卒業後、横浜市立図書館に司書として勤務。
平成24年3月に横浜市を退職、熊本県に転居し、現在、尚絅(しょうけい)大学准教授として図書館司書を目指す学生を教えています。
『とうよこ沿線』との出会い、また「地名」の連載を執筆したことで、図書館に足繁く通うようになり、その後の仕事・人生に大きな影響を与えたことになりました。
ちなみに、熊本には、昔東横線を走っていた「青ガエル電車」がまだ現役で走っています。自分もまだまだ若いぞ、という気持ちにさせられます。
|
|
|
時は江戸初期、一面の野原の中に、馬に乗る将軍の姿があった。手には一羽の鷹。そのとき、目の前に飛び出す雉(きじ)。将軍は鷹を放った。鷹は雉に襲いかかる。それを馬で追う将軍……。
古代以来行われた鷹狩りは、江戸時代には将軍の行う行事として定着した。「生類憐みの令」を出した綱吉らを除いて、代々の将軍は、たびたび江戸近郊に鷹狩りに出たものである。
このような鷹狩りに由来する地名のうち、沿線に残されたものと、それにまつわる話をここで紹介しよう。
|
|
|
|
|
◆駒場・鷹番 (東京都目黒区)
江戸時代、目黒近在は将軍の御鷹場であった。なかでも駒場野・碑文谷原には、歴代将軍がたびたび訪れている。
現在の井の頭線の「駒場」という地名は、この地に江戸幕府の馬の調教場があったことに由来するようである。しかし、鷹狩りには馬はつきもの。「駒場」 という地名は、鷹狩りの際、馬を走らせた地であるということをも、意味しているのではないだろうか。
これに対して、学芸大学駅の所在地の「鷹番」という地名は、文字通りこの地が御鷹場であったことを示している。つまり、この地名は、この地が、かつて鷹場を警備する番所のおかれていた場所のひとつであることに由来するのである。
権兵衛種まきゃ 烏がほじくる・・・
「権兵衛が種まきゃ鳥がほじくる。三度に一度は追わずばなるまい」
この俗謡を耳にしたことのある人は多いと思うが、これが駒場野の鷹狩りに由来するものであることは、あまり知られていないのではないだろうか。
この 「権兵衛」さん、じつは駒場に実在していた人物で、将軍の鷹狩りの獲物にする野鳥などにエサを与えて飼いならしていたのである。つまり、野鳥らにエサを与えることを 「種をまく」と言ったのである。
ところが、このエサを狙っていたのが、図々しいカラスであった。将軍様の獲物になる野鳥のエサを、カラスに食われてはたまらない。そこで 「三度に一度は追わずばなるまい」・・・。
権兵衛とカラスの追いかけっこを想像してみるのもおもしろい。
サンマはメグロに限る
「サンマは目黒に限る」・・・。
世間知らずの将軍をネタにしたこの落語も、鷹狩りに由来している。
この将軍は3代家光か8代吉宗で、茶屋は中目黒村の通称一軒茶屋、別名爺ケ茶屋だと言われている。現在、田道小学校の横にある茶屋坂は、この一軒茶屋に由来するものである。
しかしこの将軍様、よほど腹がへっていたようで、ふだん口にしない安いサンマを、あっというまに平らげたという。
そこのあなた、将軍様を笑えますか? そう、『とうよこ沿線』を読みながら、あっというまにおせんべを一袋あけてしまったあなたですよ~。
その後、鷹番付近では、タケノコが栽培されるようになり、こちらは正真正銘の「目黒のタケノコ」として、食通の間でもてはやされたのである。
|
|
|
|
◆小杉御殿町 (川崎市中原区)
江戸近郊の御鷹場は、目黒付近のほか綱島・加瀬・小杉などにもあった。
これら近郊の鷹場などに出かける折、将軍が休憩や宿泊をする場所として設けられたのが「御殿」である。
最寄駅が新丸子または武蔵小杉である「小杉御殿町」という地名は、この地に設けられた「御殿」に由来することは言うまでもない。東海道の脇住還にすぎなかった中原街道の、一宿場のこの地が、「城下町のような賑いであった」というのも、この 「御殿」 の存在が大きかったのであろう。
◆綱島・鷹野橋 (横浜市港北区)
鶴見川にかかる「鷹野橋」・・・。この橋の名前も、この綱島周辺が御鷹場であったことに由来している。
しかしこの鷹狩り、御鷹場周辺の農民・猟師たちにとっては、重い負担になっていた。鷹匠が権威をふるい、猟は禁じられ、田畑は踏み荒らされ、人夫や馬までも取り立てられたのである。中でも鷹匠を接待することは、当時の名主にとっては、最大の負担であったと伝えられている。
このような鷹狩りに関する費用も、当然のように村の負担となっていた。こうした理由から、御鷹場となっていた農村は、発展を見なかったのである。
◆
表面は勇壮な鷹狩りであるが、その裏には、幕府の江戸防備・農民への圧力という目的が隠されていたようである。
「目黒のサンマ」で将軍を笑いものにしたことも、幕府に押さえつけられていた庶民の、ささやかな反抗であったのだろう。いつの世でも、下の者が上の者に苦しめられるということは変わらないようである。
◇主な参考文献
「角川日本地名大辞典」「目黒区史」「わが町の歴史 川崎」「新編武蔵風土記稿」「港北百話」「御鷹場」 |
|


世田谷区瀬田の両親閣東京別院に保存されているケラ桶 所蔵:同院住職・遠山観貞さん/撮影・岩田忠利
江戸時代、将軍は多摩川によく鷹狩りに来ていました。村人はそのたび、鷹の餌としてケラ(虫のおケラ)を連日子供も大人も総出で連日辺り一帯を探し回って捕り、年貢がわりに納めさせられました。そのおケラを現在の学芸大学駅あたりにいた鷹番のもとに写真のケラ桶に入れ、届けました。(岩田忠利) |
|
|
|
 |
「とうよこ沿線」TOPに戻る |
 |
次ページへ |
 |
「目次」に戻る |
|
|
|