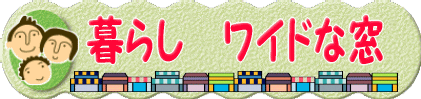 |
| ロゴ:配野美矢子/編集支援:阿部匡宏 |
| NO.83 2014.7.02 掲載 |
|
★画像はクリックし拡大してご覧ください。
|
 |
 駅誕生秘話(南武線3駅) 駅誕生秘話(南武線3駅) |
|
|
|
| 掲載記事:昭和56年(1981年)9月1日発行「とうよこ沿線」.7号から |
編集:岩田忠利 |
活動本拠地、東横沿線と武蔵小杉駅で交差する南武線。
地元の有力者たちは多摩川の川原で採取した砂利運搬の目的で民間会社「南武鉄道」を設立しましたが、昭和2年の開通に漕ぎつけるまでには用地買収が進まず、大変なご苦労があったようです。
当時の物流は水上交通が河口から稲田村菅まで利用でき、陸上交通は一頭したての4輪馬車が走っていて、地元住民は鉄道の必要性を感じていなかったのです。 |
|
結局、最初に鉄道院へ鉄道敷設免許申請を出したのが大正8年(1919)、川崎~登戸間が開通したのが昭和2年(1927)、じつに8年の歳月を要したのでした。
今や通勤通学の足として欠かせない南武線。今から32年前、地元でご活躍のお三方に以下の投稿をお願いしました。
岩田忠利
|
|
◆古くて新しい、武蔵新城
昭和2年3月9日、武蔵中原と溝口駅の間の田んぼのまん中に民営の南武鉄道「武蔵新城停留所」が造られた。
当時は無人駅で、今の北口は農道から細い道路でつながった線路に並行して北へ走る大通りや南口ができたのは、ずっと後のことである。それが今では乗降客が一日約6万人、連結駅を除けば沿線随一であろう。
昭和14年、川崎市と南武沿線の大会社とで「川崎住宅株式会社」を創立、武蔵小杉にはたくさんの共同住宅が造られ、新城には3百戸の平家一戸建て住宅も建設された。東側線路沿いの方は完成後まもなく終戦を迎え、戦災復興のため、ますます住宅の必要性が生じ、中央から西側の千年(ちとせ)・新作(しんさく)にかけて市営・県営の住宅が次々とでき、大会社の寮やアパートも矢継ぎ早に建ち、一大住宅団地が形成された。
居住者の激増に伴い、駅前及び南口商店街、アーケード通りの名店街、日光通り、新城銀座商店街、スーパーマーケットも進出、その繁盛ぶりはめざましい。商店街の近代化をはかるための立地条件もよ〈、商店同士が協力的で団結も強く、よい指導者に恵まれたことも一因であろう。
|
江戸時代発行の「新編武蔵風土記稿」に「新城は江戸日本橋より五里、家数40軒。水田多く陸田少し。男女共に農業の暇には布の糸を繰り菰(こも)を織って生業の助とす。村内に中原街道あり」と記されている。
城は、または庄を意味し、古くは稲毛本庄に対する新庄とも考えられている。南口近くに新城神社があり、ここの氏子青年の演ずる米俵の「曲持ち」は他では見られぬ妙技である。
文・小林英男(武蔵小杉・郷土史家)
|

南武沿線随一活気ある商店街が縦横に走る表玄関
|
|
|
◆中原町の名残で、武蔵中原
東横線の武蔵小杉駅から国鉄南武線に乗り換え、立川に向かって最初の駅が武蔵中原である。
南武線が昭和2年3月貨物駅として開業された当時、この辺りは今の中原区の中心地であった。橘樹郡農会や中原町役場(のちに市役所中原出張所)もあって有名な中原街道も走っている。こうしたことから駅名になったと思われるが、戦災で焼けてからは出張所も今の小杉三丁目に移転(現在は中原区役所)してしまった。
「富士通信機」や「沖電線」もある現在、空襲さえなかったら、なおも中原区の中心地として、中原駅もまた一大発展を遂げたのではないだろうか。住民の一人として誠に痛惜の感に堪えない。
いま武蔵中原駅は「富士通」のほか武蔵小杉駅で接続する東横線の近郊駅としての役割も担い、1日の乗降客は5万人を数え、職員も駅長以下37名と聞いた。
しかし、ごたぶんにもれず、周辺は自転車の洪水である。駅の北側(富士通)寄りはまったくお手上げのようだが、南口には土地の素封家、小川光春さんが市に無償提供されたのに感激して、市費で1000台収容の自転車置き場ができた。
自転車置場のすぐ南には村社の「大戸神社」があり、住民の崇敬が篤い。夏まつり(7月7日)に行われる古式も豊かな「禰宜の舞」は、この辺りではこの社だけである。また中原駅から南の方1㌔には「安楽寺」(有名私塾の記念碑)があり、西へ1㌔の地には「金竜寺」(俳聖の句碑)がある。さらに西へ足を伸ばせば重要文化財の「影向寺」、(武蔵の国分寺より18年も早く建立された)があって、東へ1㌔の所には「泉澤寺」がある。また漫画寺で知られる「常楽寺」など名所旧跡には、こと欠かない。 |

名刹の多い町も、駅前は自転車のヤマ
|
|
川崎を縦断している南武線の歴史はそこに住む市民の歴史でもある。「ジャリ電」の昔から半世紀あまりも経て、市民念願の「高架化」工事もようやく始まった。57年末と予定されているが完成のあかつきには、武蔵中原駅は250㍍ほど小杉駅寄りとなる。高架になると8~9㍍は線路が上がるので、純白の富士山を車中から眺められるのであろうが……。南武線も武蔵中原駅もひとつの転機をむかえた。
では〝迷句〟をひとつ、
<中原に 数ある駅も 中原と言うは此処だけ 大切にせん>
文・鹿島一郎(武蔵中原・町会長)
|
|
◆明治の下沼部村の小字、向河原
駅のある中原区下沼部の地は、古くは広大な流域をもつ多摩川の流水敷であった。川の流れは出水のたびごとに移動していた。だが、川筋が固定するや、川底も低下し、湿地から乾燥地となった。
その位置が主流の東側、下沼部村の地元であったので、ここは荏原郡下沼部村に属していた。しかし耕作者は隣の中丸子村の農家が殆どで、明治の頃には下沼部の農家は13軒くらいであった。公簿上は東京府荏原郡下沼部村大字向河原字玉川向及洲畑の地名であった。
明治22年下沼部は合併、調布村となり東京府荏原郡調布村大字下沼部字玉川向及洲畑となるに及び、向河原の名称は消えた。さらにその後明治45年4月1日、東京府と神奈川県境が変更されたため、下沼部の地は調布村から分離し、橘樹郡御幸村に合併、またまた下沼部……となる。
大正13年に御幸村が川崎市に編入、そして今日に至っている。 |
明治の後期まで住民に愛称されていた「向河原」が、昭和2年南武鉄道の開通で駅名となり、20年ぶりに日の目を見たのである。当時住民の日常会話の中でも下沼部をクチにする人は少なく、だれもが向河原と呼んでいた。
この人情をローカル線の南武鉄道が駅名としたのは、当然の帰結であった。
駅舎と隣合わせの日本電気玉川向工場も字名。この工場は昭和11年7月に操業を開始、従業員は南武や東横の鉄道で通勤した。年を経て移住者も多く、駅前通りは商店街を形成した。
上り方向の隣駅は無人の「武蔵中丸子」と呼んだが、昭和19年4月南武鉄道が国鉄となるや、旧武蔵小杉駅とともに廃止され、現在はない。
文・原 三喜(向河原・元川崎市議)
|

行政区分に振り回された向河原 |
|
|
 |
「とうよこ沿線」TOPに戻る |
 |
次ページへ |
 |
「目次」に戻る |
|
|
|