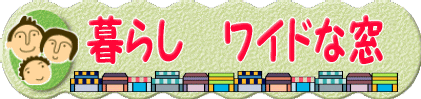 |
| ロゴ:配野美矢子/編集支援:阿部匡宏 |
| NO.82 2014.7.02 掲載 |
|
★画像はクリックし拡大してご覧ください。
|
 |
 駅誕生秘話(横浜線6駅) 駅誕生秘話(横浜線6駅) |
|
| 編集:岩田忠利 |
| 掲載記事:昭和57年(1982年)1月1日発行「とうよこ沿線」.9号 |
|
私たちの活動本拠地、東横沿線と菊名駅で交差する横浜線・・・。
東神奈川~八王子間42㌔のJR横浜線は古く、横浜鉄道という民営の会社が明治41年(1908)に開通させたのが始まり。今から106年も前のことです。
東急線で最古の目蒲線開通が大正12年(1923)、純粋の東急線と言われる東横線最初の開通区間「神奈川線」が大正15年(1926)、15年や18年も早く走っていました。
では、なぜそんなに早く開通させたのでしょうか。
当時わが国最大の輸出品、生糸を生産地の八王子や甲信越地方から運ぶためでした。
日本の生糸は海外で大人気、飛ぶように売れ、外貨の稼ぎかしらでした。横浜線は活気を呈し、わが国の“シルクロード”と呼ばれ、キッチン車両に白衣の料理人がいて車内にボーイがサービスに回って来ていたという。
そんな往年の横浜線でしたが、さて今から32年前の車外の各駅は? 今や新横浜などは信じられないほど変化しています。
岩田忠利
|
|
◆神奈川宿があった、東神奈川
東海道五十三次の第3番目の宿場が神奈川宿である。
昔の東海道は、今の青木橋の西北、本覚寺の崖が岸辺で、いま東海道線の走っているあたりは沼地であった。幸ヶ谷公園の西、青木橋の下に京浜急行の神奈川駅があり、そのあたり東西の一帯が神奈川宿のあったところで、その東方に当るので「東神奈川駅」と命名された。
その昔、神奈川通り五、六丁目の間に上無川(カミナシガワ)があり、それが訛って「神奈川」となった。
約100年前、そのあたり一帯は中村源兵衛氏(昭和13年73歳で死亡)が所有していたが、国鉄に売却して東神奈川駅ができた。
駅の東側を旧第一国道が走り、小工場や古い店があり、神奈川小学校、神奈川中学校、神奈川診療所などがある。
今は西側が発展し、24階建ての東海プラザ、スーパーのニチイ、サンコー。銀行では三井、北陸が進出し、他の鉄筋ビルも建ち並び、その発展ぶりは東側の比ではない。また近くの富塚町に昔は木造の国鉄宿舎があったが5、6年前鉄筋ハウスに建て替えられ、数百軒の家族が住んでいる。
当駅はいちおう横浜線の始発駅となっているが、一日数本は磯子~八王子間の直通電車も走り、現駅長松川充利さんは第38代目である。
文・山下二三雄(反町・会社員)
|

安藤広重もビックリ、いまの神奈川宿の玄関
|
|
|

大口駅は間口が広く、文字どおり大口開けて待っているようですが、人っ子一人いませんね
|
|
◆大商店街の入り口にあたる、大口
横浜線の東神奈川駅から一つ目、菊名駅との中間駅が大口である。新幹線に乗るには、近いうちに横浜駅から地下鉄で行かれるようになるが、今のところバスか横浜線利用によるほかはない。
さて、駅名の由来であるが、大口駅から国道一号線を越えて京浜急行の子安駅まで約1㌔が、大口通り商店街として古くから開けていた。
東京・横浜の中心街にやや不便なためで、両側にはアーケードの完備された歩道が続き、さすがに立派な店が並んでいる。横浜銀行も進出し、食料品・日用品の新鮮さ・豊富さではデパート並みの相鉄ストアが偉容を誇って繁盛している。
駅は昭和32年の開業で、駅名は「大口通りの町名」と、大口通り商店街への入り口にあたるところから、そう名づけられた。
今の駅長さんは小沢唯男さん、第16代目である。
「付近に生徒数2400人の京浜女子高校があり、そのうち1500人はこの駅を利用し、東京・横浜のベッドタウンとしてのサラリーマンを含め、一日の乗降客は2万4千人」と、駅長さんは話す。
文・山下二三雄(反町・会社員)
|
|
|
◆田んぼと湿地帯を埋め立て、新横浜
「駅前は一面の荒野、風が吹くと黄塵が舞い上がり、はきとる後から駅のコンコースは砂の山。夏ともなればホームの明りをつければ虫の大群が殺到し容赦なく顔にぶつかってくる。」(『かながわの鉄道』より)
これは昭和39年10月、東海道新幹線開通と同時にオープンした新横浜駅の開業当時の様子である。
新横浜駅は、始め菊名駅付近に建てられる予定であったが、付近住民の反対にあい、港北区篠原町の田んぼと湿地帯を埋め立て、現在に至っている。この手つかずの広大な土地を巨大化する横浜市街の副都心計画によって建てられ、駅名は新しい横浜、「新横浜」と名付けられた。
だが、開通後20年近く経た現在も、駅前周辺は当時をしのばせる原野が広がっていて、広い道路は通行人が三々五々、進出したばかりのデパートや商店街の賑わいはない。
都市計画の遅れと地価の暴騰により発展が遅れてしまったこの駅周辺も、昭和58年10月には高速鉄道3号線と新幹線交差部が完成予定、横浜南部の上大岡駅から横浜駅を経由した地下鉄が乗り入れ、駅周辺は近代的なビジネス街として発展していくことだろう。その時が楽しみだ。
中本英美(白楽・学生)
|
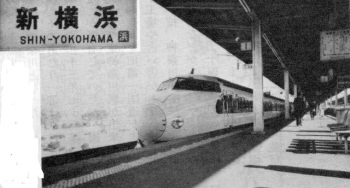
数年後にはビジネス街に変わるだろう?
|
|
|

いかにも古そうな木造の駅
|
|
◆『吾妻鏡』にもその名を発見、小机
〝小机〟という地名にはどんな意味があるのか? その疑問を解決するためにまず小机城跡へ向かう。木造の素朴なイメージの小机駅とは対照的な賑わいを見せる小机商店街を西へ歩く。
何本目かの小道を右へ。途端に辺りは緑の多い静かな住宅街に早変わり。そのままずんずん歩くに従い、左右は山や田畑、ビニールハウスの目立つ農村の風景になっていく。
やっとめざす市民の森に着く。空を覆うばかりに繁る竹薮は見事なもので、足元にはドングリや松ボックリがたくさん目につく。市民にとっては格好のハイキングコースであろう。
小机城跡は、この森の中の〝二の丸〟〝本丸〟と名づけられた広場に石碑のみ残している。説明板によれば、この城は中世(9~15世紀頃)築城されたもので、その後廃城、再興を繰り返し、最後には城主の他地への移転で廃城になったという。
しかし、具体的な城主名、築城年号、城名の由来などについてはわかっていないらしい。
帰りがけに、小机城主・笠原越前守信為氏菩提寺、曹洞宗雲仙寺に寄り、地名由来を伺ったが、〝小机〟の名を『東鏡(吾妻鏡)』(★鎌倉時代の初代将軍源頼朝から6代将軍までの将軍記)の文中に見られるものの、他に特別な由来はわからない。
こんもりとした緑の小机の山に歴史のミステリィを感じる取材だった。 中本英美(白楽・学生)
|
|
◆鴨が居て、鴨居
「武蔵国都築郡新治村大字鴨居字東河内92番地」から「横浜市港北区鴨居町東河内92」に。そして昭和46年区制改正、「横浜市緑区鴨居町92」が現在の鴨居駅の所在地である。
このように駅名「鴨居」は地名からとったであろうと思われる。
地名「鴨居」には通説・俗説はあるが、また古老でも定かではないという。
駅長の阿部且利さんのお話によれば、
「昔、入江があり、多くの鴨が棲んでいたことに由来しているらしく、横を流れる鶴見川には冬、鴨の姿が見られる」という。
しかし、名のとおり鴨がいたというわけではなく、「神がまします地」という意味から、「かみい」が「かもい」となったという説もある。
地元の要望に応え、また、複線が不可能だったため単線の便を計って、約3㌔間隔に駅を設置したら、という案により開業されたのは、昭和37年12月25日のこと。
当時は、田んぼのまっただ中を電車が走っていたそうだが、田や畑が線路沿いに広がる風景はのどかで、今も変わらない。春には家族連れの花摘み、イナゴ・バッタ捕りといった微笑ましく見られる町だ。しかし朝夕は、日本電気や松下通信等の通勤者と、中高の生徒でごった返す、活気ある駅に変身する。 野沢明美(日吉・学生)
|
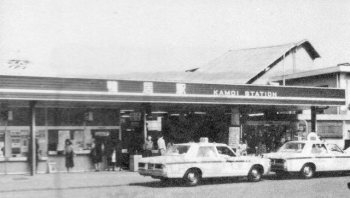
利用客は今後増加する一方だろう |
|
|
◆「中山行き」から(?)、中山
「中山なんて、すごい田舎なんだから」と、中山の高校に通っていた友人の言葉を思い出しながら駅に降り立った。私は、そこに子供のころの懐かしい〝何か〟を感じとった。
明治41年、産声を上げた駅は、この当時の人々にとって憩いの場であったらしい。生糸を満載し、八王子から横浜へ向かう途中の汽車を見に来る人、コマや羽子板で遊ぶ子供たちの姿が駅前の光景だった。
駅名由来は、中山町にあるから中山だろうと思っていたが、駅は中山の隣の寺山町に建っている。ではなぜ、中山の名がつけられたかというと理由は2つほどある。 |

明治期の開業当時、駅は人々の憩いの場であった
|
|
1. 駅建設当時、建設資材を置く場所が中山だったが、湿地帯のため資材のすべてを置けなかった。そこで丘陵地の台村町にいったん資材を置き、少しずつ中山へ運んで行ったそうである。この時、資材に「中山行き」と書いてあったのが、そのまま訛り「中山駅」となった。
2. 駅建設関係者がよく寝泊りした〝落合邸〟である日、役人の一人が「駅はできたが、名前はなし。どうするか」とみんなに相談したところ「ここが(落合邸)中山にあるから中山でいいだろう」ということで、中山とつけた、ということである。
駅名由来のエピソードは、ほほえましいものだが、自然の多いこの付近にも、開発の波が急速におし寄せてきている。減っていく田畑、増え続ける人口。願わくば、今のままの姿であってほしいものだ。
文・皆川祐美子(菊名・学生)
|
|
 |
「とうよこ沿線」TOPに戻る |
 |
次ページへ |
 |
「目次」に戻る |
 |
駅名の由来⑥へ |
|