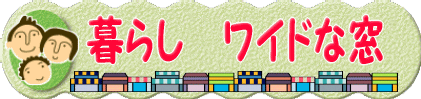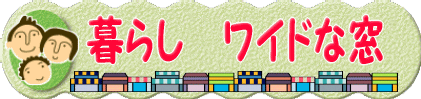|
彼は、そうめんチャンブルーの味付けに熱中していた。歌の味付けも上々だった。わが家の竃(かまど)は立ったまま調理するように、高い位置に竃が据えられていた。そのせいか、体全体で調理を楽しんでいるように見受けられた。
近所に遊び友達のいないわたしは、自然に橋本兵曹長のそばにいることになった。その日は母もいっしょだった。
「うちの兵隊さんのなかで僕は橋本兵曹長がいちばん好きだ。僕もいまにあんな兵隊さんになるんだ」
国語の読本に出てくる無性格なヘイタイサンではなく、人柄を感じさせる魅力を感じていた。
彼が語る予科練の体験談は興味深かった 。
「内地には霞ヶ浦といって、この島くらいの広さの湖があるんだよ」
湖を見たことのないわたしには雲をつかむような話だった。それだけに想像の翼がますます広がるのだった。
橋本兵曹長を慕いながらも、わたしは彼の経歴(戦歴を含む)や係累について何一つ知らないのだった。
突然、招集を伝える伝令が駆け込んできた。一瞬緊張が走った。
「アメリカの艦隊が接近中らしいです」
橋本兵曹長は、小声で母に耳打ちすると火の始末を終え身支度を調えた。いざというときの兵隊さんたちの行動は、実に素早かった。たちまちアスリート飛行場の護りを任務とする頼もしい兵に立ち戻ったのだった。
構築されたばかりの高射砲陣地に向かって走る12名の背中を見送ったあと、一家はホウオウボクの繁りが陰を落とす防空壕に身を潜めた。
屋根の上を高く飛ぶ1機のグラマンが急降下して視界から消えた。波状攻撃の先触れだった。
|