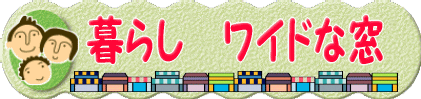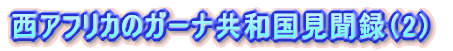案内人の説明に耐えられない白人も・・・
奴隷を搬出した港の要塞が現在世界遺産に登録されています。ゴールドコーストに2か所あり、エルミナ城とケープコースト城です。
これらの城は“城”と呼んでいますが、一般に考えられる城ではなく、要塞です。
城の内部に軍人のトレーニング場などもあり、とらわれた黒人が収容された各部屋は窓もなく、あっても高いところに小さい窓があるくらいのもので、部屋の中は少ない人間でも蒸し暑くなっています。絶対に逃走できないような構造になっており、狭い通路から直接岸壁の船に乗せるようになっています。城の案内人は、いかに搬出前の奴隷がひどい状況であったかを説明します。
それは想像に絶するものであったようです。まるで動物を船に積みこむような感じでした。一緒に見学していた白人は、説明に耐えられず外へ出て行きました。
制服を着たガーナの小中学生がたくさん見学していました。自国の歴史を知ることは良いことだと考えますが、子どもたちはどんな心境で案内人の説明を聞き、どんな印象を持って帰るのでしょうか。
白人がすべて連れ去ったように言われていますが、黒人も黒人同士の部族闘争で敗れた部族の人たちを送り出したようです。
世界遺産で有名な城を見学しても後味の悪い、悲しみのみが残る見学でした。
|

世界遺産「ケープコースト城」 2013年2月
城の反対側が岸壁になっています。この城の外国人入場料は高い。たぶん日本円で4000円くらいだったと思います。それに内部の写真を撮ると、さらに数千円の料金が必要になります
|
|
|