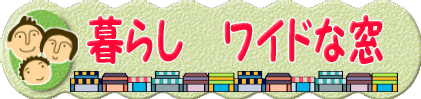
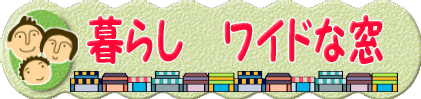
NO.41 2014.5.10 掲載
★画像の上でクリックし拡大してご覧ください。
歴史ある建物を残すエネルギー |
|||||||||||||||
まず建物の調査観察と評価 古い建物を残す手始めとして、我々にはその建物の価値が判らなければなりません。それには、その時代の背景やその地域の歴史、建築史も建築技術史も知らねばなりません。 調査や観察して建物の評価をきちんとし、我々が素晴らしさを理解してから所有者へ説明しなければなりません。昔の建物はそれぞれ個性や特性を有し、同じ造りの建物は決してありませんので、丹念に調査観察します。 次に所有者との話し合い 多くの建物所有者はご高齢者が多く、古さと汚さや不便さで恥ずかしいという思いをお持ちですから、建物とそこでの生活に誇りを持っていただけるようにお話します。でも、これが第一義ではありません。 肝心なのは、所有者の方と話し合い、『所有者も建物もより幸せになるために』、どのような考え方や方法が可能か、経済的負担を鑑み、あらゆる手段を模索します。両者ともに大変なエネルギーと時間が必要になります。本業の合間に可能な限りの時間を当ててでも、このエネルギーを惜しんでいては残りません。 伝統的建築工法の現状 ちなみに、特に木造住宅は昭和30年代後期より徐々に、建築工法の変化や各職種の電動工具の普及、工場生産建設材料の広汎な使用、職人不足、技量不足など大きく変化してきて、効率化が優先し、伝統工法的要素が薄れだしました。 さらに、耐震基準や防火基準が強化されて、行政の過去の伝統工法に対する認識不足の影響もあって、古き良き伝統的工法が廃れてきています。 |
|||||||||||||||
歴史的建造物の保全活動 |
|||||||||||||||
我々のグループ活動 このような「築50年以上の建物を歴史的建造物」と総称されています。 洋館付き住宅や文化住宅から農家や民家、洋館など古い興味深い建物を中心に歴史的建造物の保全活用に携わっています。 歴史的建造物の調査やその報告書の作成、有形文化財への登録申請、保全改修や保全活用の支援や協力、日ごろの研鑚など実業とは若干視点の異なる活動をしています。
|
|||||||||||||||
| 歴史ある建物に寄り添って(4) |