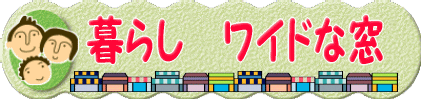
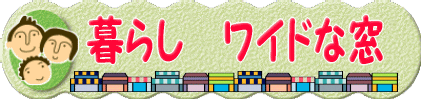
NO.40 2014.5.10 掲載
文・写真:越智英夫(建築家 横浜市神奈川区神大寺在住)
★画像の上でクリックし拡大してご覧ください。
歴史ある建物に寄り添って(3) |
文化住宅ってなんだ! |
||||||||||
中流層に広がる、和風住宅から洋式生活にマッチした住宅改良の機運 日本の近年までの和風住宅の原型は江戸時代の武家屋敷を色濃く継承してきた、書院造り系の接客本位の造りで封建制を引きずった住宅でした。 モダン流行りの大正期になり増えだしたサラリーマン、中流層や社会進出してきた女性も昼間の勤務生活などは洋装で、家庭では従来の和装などの二重生活でした。それは食生活も和洋の違いで食器類にも表れています。そして、知識人が日常的な生活改善や健康生活、合理的な生活、経済性など二重生活の不合理を指摘して改善を奨めました。新聞や婦人雑誌も生活改善を啓蒙し、家族本位の洋式生活を推奨して、それに合う住宅改良運動が中流層の人々に受け入れられてきました。 住宅改良団体、雑誌や新聞社などの後援もあり都市部で住宅博覧会が開催され、実物大の改良住宅が展示されました。更に、国家的建築事業にまい進してきた建築家が市民の生活や住宅にも目を向け、住宅改良の提案を始めました。同時に、東京は人口過密となり住宅難が深刻な社会問題でした。そして政府は住宅建設資金融資制(住宅組合融資)を設けました。また、交通網の発達により郊外住宅地の開発も増えて、持ち家願望も高まりました。 大正11年(1922)東京博覧会場にモデル住宅の展示 そこで、東京府と建築学会は大正11年春、東京上野公園で平和記念東京博覧会場の一画に「文化村」と名付け、14棟の小規模の実物モデル住宅を「文化住宅」という名称で建設展示しました。それらの住宅は20坪以内、居間・食堂・客間は椅子座式、子供室、寝室、機能的な台所、洗面所・浴室・衛生的な便所、家具や照明器具、敷物まで揃え、工事費も表記されていました。家族本位の生活が望めるモダンなデザインのコンパクトな洋風住宅が主でした。これは現在の我々の住まいそのものです。 「文化」の名がつくモノの氾濫 これらの住宅が「文化住宅」と一般にも称され、これを発祥として「文化」の名が冠する鍋、包丁、風呂から学校名、アパート、そして郊外住宅分譲地にも付けられました。 当時建てられた文化住宅は平成直前には殆ど滅失したようですが、残存も僅かにあります。 余談ですが、昭和23年戦後の住宅難に応えて、東急電鉄が世田谷に敷地20坪に建坪3坪(2.5畳の居間、2畳のDK)の超狭小の「文化住宅」を独身や新婚者対象に売り出したが、狭すぎて敬遠され、16戸で販売中止になりました。 ※平和記念東京博覧会の文化住宅古写真は手元に良いものが無いため下記ホームページをご覧ください。 http://chinchiko.blog.so-net.ne.jp/ 2010-11-18 落合道人
|
||||||||||