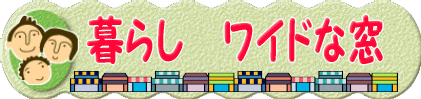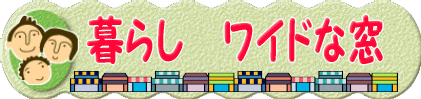伝統的和風住宅と少々異なる住宅の出現
皆さんはトトロの家(メイとサツキの家)をご存じですか。
伝統的和風住宅の玄関脇の目立つところに高い屋根の小さい洋館が付いている住宅です。このように全く氏素性が異なり、和洋異なる様式の結合付加した建物は世界広しと言えども日本だけの特異な建築史的現象です。大正期から昭和初期太平洋戦争前まで、全国的に多くの郊外住宅地に建てられ、現在でも下町から古い住宅地に見られます。
なぜこのような変テコな住宅が流行ったのでしょうか。
ことの起こりは明治天皇が旧江戸城の皇居で洋装、靴履、椅子、机、寝台の使用など率先して洋式生活をされた影響なのです。
明治天皇は全国各地を精力的に頻繁に行幸しました。行幸先の休憩や宿泊先は各地の名士、地元政財界の要人、貴顕の人々の邸宅や企業の迎賓館になります。天皇を迎える人は天皇の洋式生活を考慮し、洋館が無ければ和館に併設して洋館の新築や増築をしたり、和洋館併設の新邸宅を建てて行幸を待ちました。洋館は賓客の接待用に、併設の和館は家族と使用人の日常生活の場になっていた例が殆どでした。当時の洋館の残存例は多いのですが、併設の和館は現在では余り残っていません。
近場で和洋館併設住宅が見ることの出来るのは、上野茅町旧岩崎邸と駒場公園内の旧前田侯爵邸になります。
|
|
|
|
左右2枚の写真は旧岩崎邸。和館は一部のみです
|
|

旧前田侯爵邸の洋館正面
|
|

旧前田侯爵邸の和館正面
|
|
|
高級軍人や高級官吏の官舎にも規模の大きい洋館付き住宅が採用
その洋館は地方でも都市部でもひと際目立ち、世間の話題にのぼる建物になります。
そんな洋館は庶民の憧れや羨望となり、世の中のステイタスやブランドは上流から下流へ、それなりの過程を経て普及します。
大正初期交通網の発達による郊外住宅開発地に念願の住宅を建てるに当たり、従来の和式生活を捨てきれない新興中流層は和風住宅の脇に応接間や書斎として、一室から二室の洋室を入れた憧れの洋館を付け加えて建てました。
洋館の建築費は和風住宅の1.5倍から2倍以上するため、小規模な洋館なら総コストは抑えられ、見映えもして自慢できます。こうして、大工と施主が相談して、見よう見まねで建てたいろいろな洋風意匠の洋館付き住宅が大変流行りました。流行りすぎてその建築的グレードはピンからキリまであります。
その用途は通常の住宅以外、富裕者の別邸や医院の診療室としての洋館付き住宅も結構ありました。
また、調査の結果、流行遅れながら、戦後に建てられた多少印象の異なる洋館付き住宅も意外とあります。
|
|
|
|

写真左も同じ鎌倉S邸
|
|
|
上の鎌倉S邸は昭和2年築の総2階建て洋館と和館の規模大きい洋館付き住宅です。当初は別邸として使われていました。保存活用や補修に当たり我々が 調査や煩雑な建物用途変更手続きなどに協力をしました
|
|
|
 |
 |
 |
|
上の3枚の絵は横浜市内の洋館付き住宅のスケッチ(絵の拡大はできません)。「よこはま洋館付住宅を考える会」出版『洋館付き住宅の魅力がわかる本』より
|
|

我々が有形文化財登録申請、改築工事した神奈川区の昭和7年築T邸
|
|

私が保全改修した横浜市歴史的建造物認定、戸塚区の昭和8年築I邸
|
|
|
|
 |
「とうよこ沿線」TOPに戻る |
 |
次ページへ |
 |
「目次」に戻る |
|
|
|
|
|