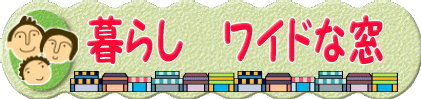古い建物を壊すのはとても簡単で、アッという間に消滅します。それと同時に、その建物に生活した方々の思いや家族の歴史、そして、周辺の景観も、その町や住宅地の趣も一挙に変貌してしまいます。
古い建物にはその時代ならではの材料や建築技術、形態意匠、生活様式が詰め込まれていた建築文化です。同時に、個人的資産でありながら、周辺地域の景観的資産でもあり、その歴史的証人でもある地域文化でもあります。
古い建物でも、補修や改修、耐震補強すれば快適安心に暮らせて、エコにもなります。今は営利主義や効率ばかりが求められるビルドアンドスクラップの時代ではありません。
建物も世につれ、時につれ変わりますが、どれもその時代でなければできなかったものです。
そんな歴史ある建物を一軒でも残すための応援やお手伝いが出来ないものかと、所有者や仲間と話し合い、微力ながら活動をしています。
そこで、ここでは古い和風住宅建築に関しての大きな流れを辿ってみます。
明治以降の和風住宅は「近代和風住宅」と建築史の上では明治以前のものと分けています。
明治以降でも一般の伝統的和風住宅が最も普及していました。興味深いことに、この近代和風建築の技術、意匠、規模、盛期などに絶頂期が近代に2回ありました。
第1期目が明治半ば頃、封建的建築規制も撤廃され、維新後の新しい特権階級(皇族、華族、政治家、事業成功者)も増え、秘伝とされた建築技術も飛躍的に広がり、東京では放出された広い大名屋敷跡地などに富裕層がこぞって大規模で贅を尽くした和風住宅を建てました。地方でも3階建ての大規模な木造旅館などが建てられたり、大富豪によるお助け普請などの雇用創出もありました。
第2期目は大正末から昭和10年頃まで、政財界人の財力と和風回帰の潮流影響もあり、工場生産されだした各種の国産材料(セメントや硝子、タイル、鋼材等)の普及や豊富な輸入材の入手、幅広い熟練の職人層を駆使した、数寄屋風から民家風に至る良質な和風住宅が多く建てられました。職人の人件費が低かったとはいえ、当時の富豪層は現代よりはるかに優る経済力を有していたようです。
和風回帰の風潮は鉄筋コンクリート造りの和風スタイルの学校やホテル、庁舎、駅舎など、この時期は和風建築花盛りでもありました。
そして、長屋住まい以外の庶民の住宅や一般の商家や農家の住居部分もこのような近代和風の縮小版や廉価版であったわけです。小さい門、入母屋屋根の小さい玄関、書院造りのある続き座敷、家族専用の暗い部屋や水回りなど定番の接客優先の伝統家屋が殆どでした。
近代和風住宅の大邸宅ともなるとその庭園も大きな見どころで、大正初期から昭和までの遺構例として、代官山の旧朝倉家住宅に一度立ち寄ってみてください。また、現存の大名屋敷造りもあります。
|

代官山の朝倉家住宅正面
大正8年築〜昭和30年頃まで増改築
|
|

朝倉家南面
|
|
|

啓明学園北泉寮の正面玄関側
規模大、複雑な屋根構成が見える
|
|

啓明学園北泉寮の南側
広々とした続き座敷が並ぶ
|
|
|
明治25年築。永田町の旧鍋島家和洋館併設住宅。関東大震災で洋館倒壊・・・その和館部を旧三井家が拝島へ昭和2年移築した大名屋敷造り
|
|