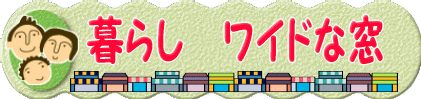|
校長の給与の20倍から60倍の高給
なぜ、そんな野蛮国、ジャパンに彼らは来たのでしょうか? その魅力は、お給料の高さにありました。
当時、中学校の日本人の校長が月給10円、お雇い外国人の標準的月給200円、非常に高給で600円だったそうです。じつに20倍と60倍でした。
当時の明治政府は、そんなに財政が豊かかといえば貿易も盛んでなく外貨の手持ちもありません。たとえ支払えたとしても、後進国日本の紙幣を彼らが母国に持ち帰っても紙ペラ、使えません。
|

明治時代後期、八雲尋常高等小学校児童
男女児童が左右別々に並び、全員がハカマ姿で壇上の先生に合わせ体操、それとも万歳、どちらなのでしょう?
八雲尋常高等小学校は明治5年東京府から認可された目黒区最古の学校です。明治期の小説家、国木田独歩の小説『酒中日記』に同校教師が主人公で登場しています。 当サイト「写真が語る沿線」(都立大学編)から
提供:八雲小学校(八雲2丁目) |
|