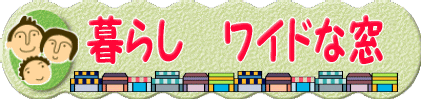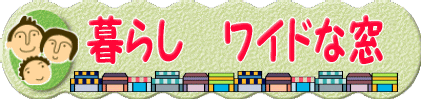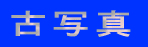|
苦戦した青葉区担当のM・Kさん
青葉区地域は田園都市線がほぼ真ん中を東西に横断し、東横線とは交差せず、並行に走っています。わが『とうよこ沿線』とは馴染みがなく、知っている人が少ない。
そんな青葉区を担当したのが、車を持たないM・Kさん。 『とうよこ沿線』の創刊当時から編集委員として活躍してきた彼です。毎日まじめに青葉区へ通いました。当時はまだ地下鉄グリーンライン(開通2008年3月30日)が開通していない。東横線綱島駅で下車してバスに乗り換え、青葉区内へ行ったのでした。来る日も来る日も、写真の収穫が一枚も無く、編集室に帰って来ては、ションボリしていました。その落胆ぶりは余りにも不憫で、私が代わることができるなら代わってあげたいほどでした。
|
|
1カ月ぶりに見つかった昔の写真
でも私は、都筑区担当。都筑区内を古写真探しに連日奔走しています。 そんなションボリするM・Kさんの日々が丸1カ月になろうという或る日、久しぶりに笑顔で私にこう話すのでした。
「編集長、やっと写真が見つかりそうです。一緒に鉄町まで行ってくれませんか?」
「蔵の中から探しておく」と約束した鉄町の旧家・村田家を、さっそく二人で訪ねました。と、主人がニコニコしながら奥から厚紙に貼った大判の写真を大事そうに抱えて現れました。そのときのM・Kさんの今にも泣き出しそうな表情が今でも頭に浮かびます。
以下の2点は、そのときの写真の一部です。
|
|