

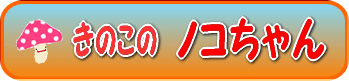
NO.6
| 04. 第一級の食菌、クリフウセンタケ(栗風船茸) 別名:ニセアブラシメジ | ||||||
|
所在地 | 川崎市中原区井田 井田山 | ||||
| 科・属 | フウセンタケ科クリフウセン属 | 食用可否 | 食用 | |||
| 見どころ | ||||||
| 担当者 | 岩田忠利 | 撮影日 | 2012.10.19 | |||
| 01. 5種あるナラタケの中の、ワタゲナラタケ(綿毛楢茸) | |||||||||
|
所在地 | 川崎市中原区井田 井田山 | |||||||
| 科・属 | キシメジ科ナラタケ属 | 食用可否 | 食用 | ||||||
| 見どころ |
|
||||||||
| 担当者 | 岩田忠利 | 撮影日 | 2012.10.22 | ||||||
| 09. サルノコシカケ科では珍しい、傘の裏がヒダ状の、カイガラタケ(貝殻茸) | |||||||||
|
所在地 | つくば市天久保4-1-1 筑波実験植物園 | |||||||
| 科・属 | サルノコシカケ科カイガラタケ属 | 食用可否 | 食不可 薬用 | ||||||
| 見どころ |
|
||||||||
| 担当者 | 石川佐智子 | 撮影日 | 2012.10.24 | ||||||
| 05. 庭園や路傍の腐植質の多い地上に生える、スッポンタケ | ||||||||||||
|
所在地 | 横浜市港北区樽町 鶴見川沿いの土手 | ||||||||||
| 科・属 | スッポン科スッポン属 | 食用可否 | 幼菌は食可 | |||||||||
| 見どころ |
|
|||||||||||
| 担当者 | 大田孝子 | 撮影日 | 2012.10.24 | |||||||||
| 06. 傘裏は管孔ではなくヒダ状である、チャカイガラタケ(茶貝殻茸) | ||||||
|
所在地 | 秦野市寺山 道沿いの林 | ||||
| 科・属 | サルノコシカケ科(タコウキン科) チャミダレアミタケ属 |
食用可否 | 食不適 | |||
| 見どころ |
|
|||||
| 担当者 | 北澤美代子 | 撮影日 | 2012.10.22 | |||
| 03. 傘を広げた姿がマツタケに似ている、ショウゲンジ(正玄(or源)寺) | |||||||||
|
所在地 | 川崎市中原区井田 井田山 | |||||||
| 科・属 | フウセンタケ科ショウゲンジ属 | 食用可否 | 食用 | ||||||
| 見どころ |
|
||||||||
| 担当者 | 岩田忠利 | 撮影日 | 2012.10.19 | ||||||
「きのこのノコちゃん」TOPに戻る
「とうよこ沿線」TOPに戻る
| 10. 表面に尖った錘状のイボが密生する、シロオニタケ(白鬼茸) | ||||||
|
所在地 | つくば市天久保4-1-1 筑波実験植物園 | ||||
| 科・属 | テングタケ科テングタケ属 | 食用可否 | 有毒 | |||
| 見どころ | 夏から秋にかけて、おもにブナ科あるいはマツ科の樹下に生えます。傘は半球形から開いてほとんど平らになり、径5〜30センチほどになりますが、私が見たのは半球形。まだ幼菌なのでしょう。 径は7センチ、柄の長さは8センチくらいで、可愛らしく毒を含んでいるように見えませんが…。家の中に飾っておきたいくらい愛嬌があります。成菌になると白色ですが老熟したものでは、僅かに黄色みを帯びることがあります。柄は長さ8〜13センチくらいに達し、もっとも太い部分の径は1〜4センチ程度、下方に向かって大きくふくれ、ボーリングのビン状みたいな形です。表面に尖った錘状のイボが密生し、白色、条線はありません。このイボは脱落しやすく、成菌になるまでの間に雨で流れ落ちてしまうことがあります。 最大の特徴はその白さと全体を覆う白いトゲ状のツボの破片「白鬼茸」。シロオニタケはトゲトゲの姿がなかなか愛らしい大型のキノコです。 |
|||||
| 担当者 | 石川佐智子 | 撮影日 | 2012.10.24 | |||
2012.10.22〜 掲載10種
2012.10.2 開設
| 08. 悪臭を放つ、カニノツメ(蟹爪) | ||||||
|
所在地 | つくば市天久保4-1-1 筑波実験植物園 | ||||
| 科・属 | アカカゴタケ科カニノツメ属 | 食用可否 | 食不可 | |||
| 見どころ | 初夏〜秋、各林内の地上に群生します。秋に観察できるなかなか珍しいキノコだそうです。キノコは傘を欠き、向かい合って伸びる2本の托と,白色のつぼとで構成されたカニの鋏状をなします。成熟した子実体は全体の高さは2〜6センチ。幼菌は卵型で白色。その後卵が割れるように腕が伸びてきます。赤橙色〜橙黄色ないし暗赤朱色ですが、基部に向かって淡色となります。胞子を含む粘液状のグレバは濃褐色で腕の内側にへばり付いています。このグレバは悪臭を放ちます。 隙間が狭いと、まるでカニの爪のように見えるのがこの和名の由来です。 |
|||||
| 担当者 | 石川佐智子 | 撮影日 | 2012.10.24 | |||
| 02. 微生物を摂取する動物的性質と胞子で殖える植物的性質を持つ、変形菌 | ||||||
|
所在地 | 横浜市港北区岸根町 725−1 岸根公園 | ||||
| 科・属 | 変形菌ススホコリ属 | 食用可否 | 食不可 | |||
| 見どころ | このキノコ名の正式名は、「変形菌ススホコリ(煤埃)属の一種、粘着性キノコ」です。 まさかこの白い物体がキノコとは分りませんでした。一応、撮影して帰宅して画像を会長に見ていただきましたら、キノコとのこと。会長からアドバイスをいただき図鑑で調べました。モミジバフウの樹皮の間に挟まるように生えていました。樹皮に挟まれていましたので、細長く5センチくらいの大きさでした。菌類(カビ・キノコの仲間)と藻類が深い共生関係になり、あたかも1種類の生物のように暮らしているそうです。このキノコのそばには、たくさんのコケが生えていました。そのコケと共存しているのですね。 |
|||||
| 担当者 | 石川佐智子 | 撮影日 | 2012.10.22 | |||
画像をクリックし拡大してご覧ください。連続して見るには左上の「戻る」を
クリックして戻ってきてください。
| 07. ボールみたいな、ホコリタケ(埃茸) 別名:キツネノチャブクロ(狐茶袋) | |||||||
|
所在地 | つくば市天久保4-1-1 筑波実験植物園 | |||||
| 科・属 | ホコリタケ科ホコリタケ属 | 食用可否 | 幼菌のみ食可 | ||||
| 見どころ | 先日、筑波実験植物園で「きのこ展」がありましたので、行ってきました。会場には、ずらりと植物園で採取したキノコが机上に並べてあり、写真撮影、匂いを嗅ぐ、手で触るのは良い。が、園内の植物は採取禁止で写真撮影だけはOK。講師の先生が最初30分くらいキノコについてのお話。その後、植物園へ。4ヵ所くらいまわり解散。 初夏〜秋、各林内の地上に群生します。 頭部と柄とで構成されていますが、両者の境界はしばしば不明瞭です。頭部はほぼ球形で、普通は径5〜8センチ程度、白色〜クリーム色を呈し、初めは黒褐色・円錐状の細かい鱗片を密布します。次第に汚褐色〜灰褐色に変わります。頭部の内部組織は、成熟するにつれて次第に黄変しながら古綿状の塊となります。柄は倒円錐状をなし、表面は頭部とほぼ同色でざらつき、内部は丈夫なスポンジ状で腐りにくく、子実体が成熟して胞子を分散させてしまった後も長く残ります。 キノコが成熟すると茶褐色から灰褐色に変色し、頂部に孔ががあいて、そこから胞子が飛び出します。表面には初め、トゲがついていますが、やがて脱落してしまいます。 |
||||||
|
|||||||
| 担当者 | 石川佐智子 | 撮影日 | 2012.10.24 | ||||