

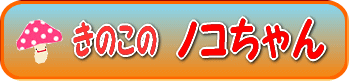
NO.5
2012.10.19〜 掲載10種
| 08. 樹木に不思議な物体、ニカワツノタケ(膠角茸) | ||||||
|
所在地 | 東京都立川市緑町3173 昭和記念公園 | ||||
| 科・属 | シロキクラゲ科ニカワツノタケ属 | 食用可否 | 食不可 | |||
| 見どころ | ||||||
| 担当者 | 石川佐智子 | 撮影日 | 2012.10.19 | |||
| 02. ミカンを剥いて開いた感じです、エリマキツチグリ(襟巻土栗) | ||||||
|
所在地 | 東京都立川市緑町3173 昭和記念公園 | ||||
| 科・属 | ヒメツチグリ科ヒメツチグリ属 | 食用可否 | 食不可 | |||
| 見どころ | 落葉の多い暗い森林の下を好みます。私は1個だけ見つけました。図鑑ではよく「ツチツグリ」と名は覚えていましたが、正確には、分りませんでした。本物に対面でき、嬉しかったです。 ツチグリの仲間にはいくつか種類があり、エリマキツチグリの場合は老成するにつれ「実」の周りに「えりまき」ができることが多いそうです。外皮(星型の部分)が内皮(中央の球形の部分)の周りで襟巻き状に裂けることが特徴で名付けられました。 |
|||||
| 担当者 | 石川佐智子 | 撮影日 | 2012.10.19 | |||
| 01. 木の実のように見え、「晴天の旅行者」と呼ばれる、ツチグリ(土栗) | |||||||||
|
所在地 | 横浜市港北区新羽町の山道 | |||||||
| 科・属 | ツチグリ科ツチグリ属 | 食用可否 | 内部が白い幼菌は 食用可 |
||||||
| 見どころ |
|
||||||||
| 担当者 | 八城幸子 | 撮影日 | 2012.10.17 | ||||||
「きのこのノコちゃん」TOPに戻る
「とうよこ沿線」TOPに戻る
| 10. 傘と柄は白。幼菌時、傘の中央にイボがある、シロイボカサタケ(白疣傘茸) | |||||||||
|
所在地 | 川崎市中原区井田1丁目 井田山 | |||||||
| 科・属 | イッポンシメジ科イッポンシメジ属 | 食用可否 | 食不可 | ||||||
| 見どころ |
|
||||||||
| 担当者 | 岩田忠利 | 撮影日 | 2012.10.19 | ||||||
| 09.高級な中華料理に利用される、シロキクラゲ(白木耳) | ||||||
|
所在地 | 横浜市港北区岸根町725−1 岸根公園 | ||||
| 科・属 | シロキクラゲ科 シロキクラゲ属 | 食用可否 | 食用(美味) 薬用 | |||
| 見どころ | 遠くから目立ち、これ何? 樹木に生えていました。これが中華料理などの材料になる「シロキクラゲ」だと分りました。 春から秋にかけて、広葉樹倒木や枯枝に発生します。形は不規則で、花びら状。子実体はゼリー質で白く、半透明です。高さは5センチくらいになります。裂片の表面は平滑で外縁部は波打つか不規則に切れ込みます。シロキクラゲから抽出され、高い保湿力を持った安全な純天然の植物性多糖体です。 美容を維持するためには良いですね。中国では現在でも不老不死、美肌の高級食材として珍重されています。 |
|||||
| 担当者 | 石川佐智子 | 撮影日 | 2012.10.21 | |||
2012.10.2 開設
| 07. 赤くてかわいいが毒キノコ、ドクベニタケ(毒紅茸) | ||||||
|
所在地 | 横浜市青葉区寺家町 里山の雑木林 | ||||
| 科・属 | ベニタケ科ベニタケ属 | 食用可否 | 毒キノコ | |||
| 見どころ |
|
|||||
| 担当者 | 北澤美代子 | 撮影日 | 2012.10.15 | |||
| 06. ヌメリが凄い、ヌメリササタケ(滑り笹茸) | ||||||
|
所在地 | 川崎市中原区井田1丁目 井田山 | ||||
| 科・属 | フウセンタケ科フウセンタケ属 | 食用可否 | 食用 | |||
| 見どころ |
|
|||||
| 担当者 | 岩田忠利 | 撮影日 | 2012.10.19 | |||
| 05. 味良し、歯切れ・舌触り良し、キツブナラタケ(黄粒楢茸) | |||||||||
|
所在地 | 川崎市中原区井田1丁目 井田山 | |||||||
| 科・属 | キシメジ科ナラタケ属 | 食用可否 | 食用 | ||||||
| 見どころ |
|
||||||||
| 担当者 | 岩田忠利 | 撮影日 | 2012.10.19 | ||||||
| 04. 珊瑚状のキノコ、コガネホウキタケ(黄金箒茸) | ||||||
|
所在地 | 東京都立川市緑町3173 昭和記念公園 | ||||
| 科・属 | ラッパタケ科ホウキタケ属 | 食用可否 | 食不可 | |||
| 見どころ | 公園の雑木林のなか1ヵ所に散らばって生えていました。子実体は黄金色で根元は白色。高さは5〜12センチ程度。胞子は長楕円形。胞子紋はくすんだクリーム色。根元は白くて太く、サンゴ状です。食べられません。 | |||||
| 担当者 | 石川佐智子 | 撮影日 | 2012.10.19 | |||
| 03. 毒キノコ集団、テングタケ(天狗茸)属の一種 | |||||||||
|
所在地 | 川崎市中原区井田1丁目 井田山 | |||||||
| 科・属 | テングタケ科テングタケ属 | 食用可否 | 毒 | ||||||
| 見どころ |
|
||||||||
| 担当者 | 岩田忠利 | 撮影日 | 2012.10.19 | ||||||
画像をクリックし拡大してご覧ください。連続して見るには左上の「戻る」を
クリックして戻ってきてください。