

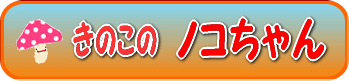
NO.4
| 01. 傘に赤褐色の鱗片を密生する、サマツモドキ(早松擬) 別名:アカゲタケ | ||||||
|
所在地 | 横浜市港北区大倉山 大倉山公園の緑地 | ||||
| 科・属 | キシメジ科 サマツモドキ属 | 食用可否 | 食用不可 | |||
| 見どころ | ||||||
| 担当者 | 大田孝子 | 撮影日 | 2012.10.12 | |||
「とうよこ沿線」TOPに戻る
| 10. キノコの大先生も初めて見たという、アンズタケ(杏茸)属の一種 | |||||||||
|
所在地 | 川崎市中原区井田1丁目 井田山 | |||||||
| 科・属 | アンズタケ科アンズタケ属 | 食用可否 | 食不可 | ||||||
| 見どころ |
|
||||||||
| 担当者 | 岩田忠利 | 撮影日 | 2012.10.16 | ||||||
| 02. 猛毒です! コテングタケモドキ(小天狗茸擬) | |||||||||
|
所在地 | 横浜市港北区箕輪町3丁目 日吉の丘公園 | |||||||
| 科・属 | テングタケ科、テングタケ属 | 食用可否 | 食用不可 猛毒 | ||||||
| 見どころ |
|
||||||||
| 担当者 | 石川佐智子 | 撮影日 | 2012.10.12 | ||||||
| 04. 茸の中でも知名度・人気度抜群の、シイタケ(椎茸) | |||||||||
|
所在地 | 川崎市中原区井田1丁目 井田山 | |||||||
| 科・属 | キシメジ科シイタケ属 | 食用可否 | 食用 | ||||||
| 見どころ |
|
||||||||
| 担当者 | 岩田忠利 | 撮影日 | 2012.10.16 | ||||||
| 05. 傘は黒褐色、根元が太い幼菌、ススケヤマドリタケ(煤け山鳥茸) | |||||||||
|
所在地 | 川崎市中原区井田1丁目 井田山 | |||||||
| 科・属 | イグチ科ヤマドリ属 | 食用可否 | 食用 | ||||||
| 見どころ |
|
||||||||
| 担当者 | 岩田忠利 | 撮影日 | 2012.10.16 | ||||||
| 06. 生長すると傘が反り返って漏斗状になる、クロハツモドキ (黒初擬) | |||||||||
|
所在地 | 川崎市中原区井田1丁目 井田山 | |||||||
| 科・属 | ベニタケ科ベニタケ属 | 食用可否 | 食可 | ||||||
| 見どころ |
|
||||||||
| 担当者 | 岩田忠利 | 撮影日 | 2012.10.16 | ||||||
| 08. キノコらしからぬ筆のような形の、キツネノタイマツ(狐の松明) | ||||||
|
所在地 | 東京都立川市緑町3173 昭和記念公園 | ||||
| 科・属 | スッポンタケ科キツネノタイマツ属 | 食用可否 | 食不可 | |||
| 見どころ | こんなキノコがあるのですね。残念ながらもう萎びていましたが……。もう会えないかもしれませんので、記念に撮影しました。 灰白色の卵形の幼菌から、6〜12センチほどの長さの子実体が伸びます。橙色の子実体の頂部には、グレバと呼ばれる胞子を含んだ粘着性物質があります。穂先の黒っぽい部分に胞子ができるのですが、ネバネバしていて悪臭がします。この胞子塊がハエを惹きつける悪臭を放つことで、ハエによって胞子を分散させます。森林の朽ちた切り株付近の落葉に生育するそうです。 |
|||||
| 担当者 | 石川佐智子 | 撮影日 | 2012.10.17 | |||
2012.10.2 開設
「きのこのノコちゃん」TOPに戻る
2012.10.15〜 掲載10種
| 03. 猛毒です! テングタケ(天狗茸)科テングタケ属の一種 | |||||||||
|
所在地 | 横浜市港北区箕輪町3丁目 日吉の丘公園 | |||||||
| 科・属 | テングタケ科テングタケ属 | 食用可否 | 猛毒 | ||||||
| 見どころ |
|
||||||||
| 担当者 | 石川佐智子 | 撮影日 | 2012.10.12 | ||||||
| 09. キノコの緋色がまず目につきます、ヒイロタケ(緋色茸) | ||||||
|
所在地 | 横浜市青葉区寺家町 里山藪の中 | ||||
| 科・属 | サルノコシカケ科シュタケ属 | 食用可否 | 食不可。 薬種or染料 |
|||
| 見どころ |
|
|||||
| 担当者 | 北澤美代子 | 撮影日 | 2012.10.15 | |||
| 07. 黄色いキノコを見つけた! キイロイグチ(黄色猪口) | |||||||||
|
所在地 | 横浜市青葉区寺家町 里山の雑木林 | |||||||
| 科・属 | イグチ科キイロイグチ属 | 食用可否 | 食用 | ||||||
| 見どころ |
|
||||||||
| 担当者 | 北澤美代子 | 撮影日 | 2012.10.15 | ||||||
画像をクリックし拡大してご覧ください。連続して見るには左上の「戻る」を
クリックして戻ってきてください。