

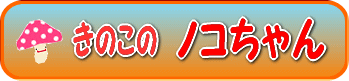
NO.2
2012.10.2 開設
2012.10.6〜 掲載10種
| 01 3日連続で出合った純白のきのこ、オオイチョウタケ(大銀杏茸) | ||||||
|
所在地 | 横浜市鶴見区獅子ヶ谷の山道 | ||||
| 科・属 | キシメジ科オオイチョウタケ属 | 食用可否 | 食用 | |||
| 見どころ | ||||||
| 担当者 | 岩田忠利 | 撮影日 | 2012.10.5 | |||
| 10 初訪問の森で30分歩いて最初に出合った、ザラエノハラタケ | ||||||
|
所在地 | 横浜市鶴見区獅子ヶ谷 森の山道 | ||||
| 科・属 | ハラタケ科ハラタケ属 | 食用可否 | 食用。人により胃痛を起こす | |||
| 見どころ |
|
|||||
| 担当者 | 岩田忠利 | 撮影日 | 2012.10.5 | |||
| 08. 傘にやわらかいトゲ状の突起が見られる、ダイダイガサ(橙笠) | |||||||||
|
所在地 | 横浜市港北区新吉田町 第三京浜入り口近くの山道 | |||||||
| 科・属 | キシメジ科 ダイダイガサ属 | 食用可否 | 無毒だが食用不可 | ||||||
| 見どころ |
|
||||||||
| 担当者 | 八城幸子 | 撮影日 | 2012.10.8 | ||||||
| 04 外観も感触も美味しいパンのような、ノウタケ(脳茸) | |||||||||
|
所在地 | 横浜市港北区新吉田町 第3京浜入り口近くの山道 | |||||||
| 科・属 | ホコリタケ科orキツネノジャブクロ科ノウタケ属 | 食用可否 | 食用可 | ||||||
| 見どころ |
|
||||||||
| 担当者 | 八城幸子 | 撮影日 | 2012.10.5 | ||||||
| 02 柄が地中深く入っていてツルタケより大型、オオツルタケ(大鶴茸) | |||||||||
|
所在地 | 横浜市鶴見区獅子ヶ谷 森の山道 | |||||||
| 科・属 | テングタケ科、テングタケ属 | 食用可否 | 毒? | ||||||
| 見どころ |
|
||||||||
| 担当者 | 岩田忠利 | 撮影日 | 2012.10.6 | ||||||
「きのこのノコちゃん」TOPに戻る
| 05 ハツタケの仲間で成菌の傘が黒くなる、クロハツ(黒初) | |||||||||
|
所在地 | 横浜市鶴見区獅子ヶ谷 森の山道 | |||||||
| 科・属 | ベニタケ科ベニタケ属 | 食用可否 | 食不可 | ||||||
| 見どころ |
|
||||||||
| 担当者 | 岩田忠利 | 撮影日 | 2012.10.8 | ||||||
| 09 江戸時代はバボツ(馬勃)とも呼ばれた、オニフスベ(鬼燻、鬼瘤) | |||||||||
|
所在地 | 横浜市港北区新吉田町 第三京浜入り口近くの山道 | |||||||
| 科・属 | ハラタケ科ノウタケ属 | 食用可否 | 食用可 | ||||||
| 見どころ |
|
||||||||
| 担当者 | 八城幸子 | 撮影日 | 2012.10.8 | ||||||
| 03 柄が紐のように強靭、傘の色が茶褐色の狐色の、キツネタケ(狐茸) | |||||||||
|
所在地 | 横浜市鶴見区獅子ヶ谷 森の山道 | |||||||
| 科・属 | キシメジ科 キツネタケ属 | 食用可否 | 食用可 | ||||||
| 見どころ |
|
||||||||
| 担当者 | 岩田忠利 | 撮影日 | 2012.10.6 | ||||||
「とうよこ沿線」TOPに戻る
| 06 柄の長さが16センチで白色。スマートな、コテングタケ(小天狗茸) | |||||||||
|
所在地 | 横浜市鶴見区獅子ヶ谷 森の山道 | |||||||
| 科・属 | テングタケ科テングタケ属 | 食用可否 | 食不可 | ||||||
| 見どころ |
|
||||||||
| 担当者 | 岩田忠利 | 撮影日 | 2012.10.5 | ||||||
| 07 この可愛い茸も身を守るため猛毒があります、ニガクリタケ(苦栗茸) | |||||||||
|
所在地 | 横浜市鶴見区獅子ヶ谷 森の山道 | |||||||
| 科・属 | モエギタケ科クリタケ属 | 食用可否 | 毒 | ||||||
| 見どころ |
|
||||||||
| 担当者 | 岩田忠利 | 撮影日 | 2012.10.8 | ||||||
画像をクリックし拡大してご覧ください。連続して見るには左上の「戻る」を
クリックして戻ってきてください。