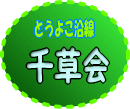
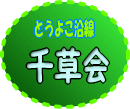
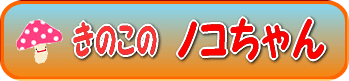
| 04 味と風味はエノキタケに似ている、モリノカレバタケ(森の枯葉茸)の一種 | ||||||
|
所在地 | 大田区田園調布1丁目 多摩川台公園 | ||||
| 科・属 | キシメジ科 モリノカレバタケ属 モリノカレバタケの一種 |
食用可否 | 食用可 | |||
| 見どころ |
|
|||||
| 担当者 | 岩田忠利 | 撮影日 | 2012.10.2 | |||
| 09 傘がほぼ半円形で年輪のような模様がある、カワラタケ(瓦茸) | ||||||
|
所在地 | 横浜市港北区樽町 鶴見川岸のグラウンド | ||||
| 科・属 | サルノコシカケ科カワラタケ属 (旧タマチョレイタケ科) |
食用可否 | 食用不可 薬用可 | |||
| 見どころ | ||||||
| 担当者 | 大田孝子 | 撮影日 | 2012.9.29 | |||
NO.1
2012.10.2 開設
画像をクリックし拡大してご覧ください。連続して見るには左上の「戻る」を
クリックして戻ってきてください。
| 01 サルノコシカケ類の中の、ツガサルノコシカケ(栂猿の腰掛) | |||||||||
|
所在地 | 横浜市港北区日吉4丁目 慶應日吉キャンパス・まむし谷 | |||||||
| 科・属 | サルノコシカケ科 | 食用可否 | 不明 | ||||||
| 見どころ |
|
||||||||
| 担当者 | 岩田忠利 | 撮影日 | 2012.9.23 | ||||||
| 06 柄はすらっと長く白い。ヒダも白い。鶴の首のような、ツルダケ(鶴茸) | |||||||||
|
所在地 | 大田区田園調布1丁目 多摩川台公園 | |||||||
| 科・属 | テングタケ科 | 食用可否 | 可 | ||||||
| 見どころ |
|
||||||||
| 担当者 | 岩田忠利 | 撮影日 | 2012.10.2 | ||||||
「きのこのノコちゃん」TOPに戻る
「とうよこ沿線」TOPに戻る
| 05 一夜で溶けて消えてしまう、ヒトヨタケ(一夜茸) | ||||||
|
所在地 | 大田区田園調布1丁目 多摩川台公園 | ||||
| 科・属 | ナヨタケ科ヒトヨタケ属 | 食用可否 | 毒。 幼菌は食用可 |
|||
| 見どころ | 春から秋に広葉樹の枯れ木や埋もれ木などどこにでも発生する腐生菌です。傘は灰色の円筒形で3センチほど、初め卵型ですが、開ききる前に周りから黒くなり、インクを垂らしたように溶けてしまう。 液化する前の幼菌は食用になり、美味だそうですが、飲酒前後に食べると中毒症状を起こします。ヒトヨタケやササクレヒトヨタケ、ネナガノヒトヨタケ(無毒)などいくつかの近縁種は腐った古畳や藁など、腐敗した植物質によく発生するのを見かけます。 どこにでも発生するといえば、「銀河鉄道999」で有名になった漫画家・松本零士は若い頃、洗濯しないパンツ(猿股)を押入れに入れたままにしておいたらヒトヨタケが生えてきたそうです。それを彼は「サルマタケ」の名にして自らの漫画作品の題材にしたりしたそうです。 |
|||||
|
||||||
| 担当者 | 岩田忠利 | 撮影日 | 2012.10.2 | |||
| 10 幼菌のときは傘の色が緑色という珍しいきのこ、アイタケ(藍茸) | ||||||
|
所在地 | 横浜市鶴見区獅子ヶ谷 獅子ヶ谷市民の森 | ||||
| 科・属 | ベニタケ科ベニタケ属 | 食用可否 | 食用 | |||
| 見どころ |
|
|||||
| 担当者 | 岩田忠利 | 撮影日 | 2012.10.5 | |||
| 03 コナラとクヌギの落ち葉の中に生えていた、カラカサタケ(唐傘茸) | ||||||
|
所在地 | 川崎市中原区井田 中原区区民健康の森 | ||||
| 科・属 | ハラタケ科カラカサタケ属 | 食用可否 | 食用可 | |||
| 見どころ |
|
|||||
| 担当者 | 岩田忠利 | 撮影日 | 2012.9.28 | |||
| 08 イタリアやポーランドで珍重される、ヤマドリタケモドキ(山鳥茸擬)の一種 | |||||||||
|
所在地 | 横浜市港北区師岡町 師岡熊野神社・社叢林(神社の裏山) | |||||||
| 科・属 | イグチ科ヤマドリタケ属 | 食用可否 | 食用 | ||||||
| 見どころ |
|
||||||||
| 担当者 | 岩田忠利 | 撮影日 | 2012.10.4 | ||||||
| 02 傘の中央が淡褐色、ヒダも柄も白い、ツブエノシメジ 別名:アマタケ | |||||||||
|
所在地 | 川崎市中原区井田 中原区区民健康の森 | |||||||
| 科・属 | キシメジ科ザラメノシメジ属 | 食用可否 | 食用可 | ||||||
| 見どころ |
|
||||||||
| 担当者 | 岩田忠利 | 撮影日 | 2012.9.28 | ||||||
| 07 傘は円錐形のチョコレートケーキのような、ガンタケ(雁茸) | |||||||||
|
所在地 | 横浜市港北区師岡町 師岡熊野神社・社叢林(神社の裏山) | |||||||
| 科・属 | テングタケ科テングタケ属 | 食用可否 | 不可 | ||||||
| 見どころ |
|
||||||||
| 担当者 | 岩田忠利 | 撮影日 | 2012.10.2 | ||||||
2012.10.2〜10.5 掲載10種